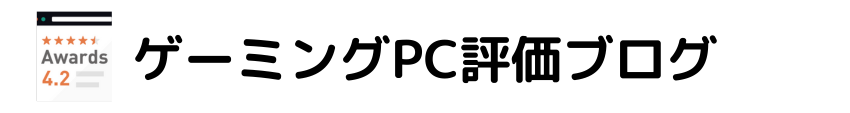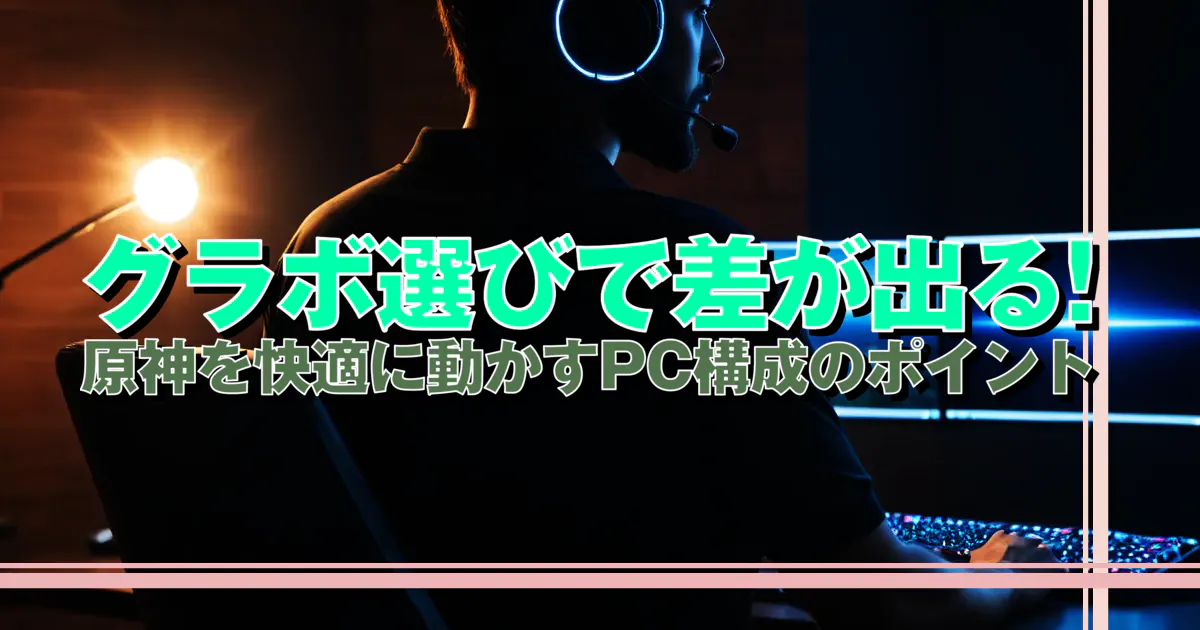はじめてでもわかる! 原神を快適に遊ぶためのGPU選び
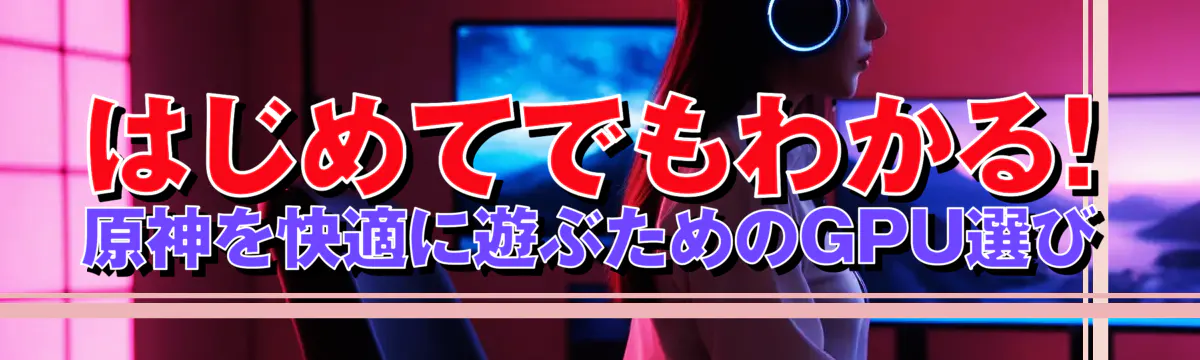
RTX 4060 TiとRX 7600 XT、実際に触って感じた使い心地の差
理由はとてもシンプルで、日々の仕事の後に短い時間でもゲームを楽しむとき、カクつくことなく快適に動作してほしかったからです。
しかし使っているうちに、数字だけでは測れない違いがあることに気づいたのです。
それが判断の分かれ目になりました。
RTX 4060 Tiを使った瞬間、まず感じたのは滑らかさです。
読み込みや負荷の高い場面で突然止まるような動きが少なく、テンポが崩れない。
そのおかげで、ちょっとしたミスやストレスを感じずに夢中で遊べました。
ゲームの世界を遮られることなく没頭できる。
それがどれだけ快適なことか、実際に味わって初めて実感しました。
「これは頼りになるな」と心の中で思わず呟いてしまったほどです。
一方でRX 7600 XTは、とにかく映像の色合いに強みを感じました。
鮮やかで自然。
原神の淡い光や柔らかな陰影が、より繊細に目に飛び込んでくるんです。
HDR画面を通して草原や水面を見た時、まるでアニメのワンシーンに入り込んだ気分になったのは驚きでした。
映像の美しさに関しては「これで十分だ」と思う瞬間も多くありました。
静音性に関しても違いははっきりしていました。
私は仕事用のPCをそのままゲームに使うので、静かに動作するかどうかは非常に大切なんです。
RTX 4060 Tiはファンの音が静かで、つけっぱなしにしていても気にならない。
小さめのケースに組み込んでも温度管理の余裕があり、実用面ではまさに安心感がありました。
それに対してRX 7600 XTは排熱のためにケースや冷却に工夫が必要で、夏場の長時間使用には気を遣う必要があると感じました。
ちょっと手間がかかるな、というのが率直な印象です。
面白いと思ったのは、数値と実際の体験では印象が食い違うことです。
ベンチマークではRTXが優位だとすぐ判断できるでしょう。
しかし日常的に遊んでみると、どのポイントに価値を置くかで結論はまるで変わります。
例えばアニメ作品を観る時、シャープな画質が良いのか、鮮やかな色合いが良いのか、その違いに似ています。
単純にスペック順で優劣を語れない。
それが今回一番大きな気づきでした。
私の日常を例にすると、メインPCにはRTX 4060 Tiを選びました。
仕事の合間に遊ぶときは動作が止まらないことを優先したかったからです。
その一方で、リビングで家族と遊ぶ用のPCにはRX 7600 XTを選びました。
大きなテレビに映したときの鮮やかな世界が、とても心を豊かにしてくれたからです。
そんな体験を与えてくれるカードだと感じました。
贅沢な時間ですね。
価格についても触れておきます。
RTX 4060 Tiはやや高め。
そのとき正直「もうちょっと下がると思ったのに」と苦笑いしました。
コストパフォーマンスを大切にする人にとっては非常にありがたい存在でしょう。
結局のところ、どちらも良いカードです。
RTXは安心できる相棒。
RXは映像の楽しさを広げてくれる存在。
それぞれに違った魅力があるので、人によって答えが違うのは当然のことです。
自分のスタイルにあった相性こそが大事なんです。
私は実際に両方を使ってそう感じました。
安定性を求めるならRTX、美しい景色を心ゆくまで堪能したいならRX。
選択には迷いが伴いますが、その迷いの時間こそ、自分が大事にしたいものを確かめる良い瞬間なのではないでしょうか。
私はそう強く思いました。
フルHDと4K、それぞれの解像度で現実的に必要なGPU性能
その違いを体験してきた今の私の率直な考えとしては、フルHDなら十分現実的でコストに合った満足が得られ、4Kを狙うなら覚悟と投資が必要になる、ということに尽きます。
言ってしまえば、フルHDは「日常的に快適に楽しめる領域」であり、4Kは「自分にご褒美をあげるような特別な体験」なのです。
まずフルHDについてですが、1920×1080の解像度なら、現行のミドルレンジGPUでも問題なく快適に動作します。
実際に私が試した環境はRTX 5060でしたが、人気のある原神をプレイしても60fpsは余裕で維持し、場面によってはさらに高いフレームレートも安定して出せました。
戦闘中の派手な演出も処理落ちしないで済み、安心して没頭できます。
この「何も気にせず遊べる環境」は大きな強みです。
しかも裏で作業用のアプリを動かしても快適さが揺らがない。
ただし、ここから先はGPUの負担が一気に増える。
私は「せっかくなら性能を出し切りたい」と思うタイプなので144fpsを狙いますが、肩の力を抜いて楽しみたい人であれば60fpsで十分満足できるのだろうと思います。
正直、ここは好みの問題です。
一方で4Kになると話は大きく変わります。
3840×2160の解像度は、描画負荷が一気に上がります。
私はRTX 5060 Tiで試しましたが、60fpsを確保するのがやっとで、正直「もう少し上のクラスが欲しい」と痛感しました。
映像美は圧巻です。
背景の緻密さ、光の表現、草や木々の揺れ方まで、まるでその場に立っているように感じられる。
しかし同時にGPUの限界がすぐ見えてきます。
ここでRTX 5070TiやRadeon RX 9070XTに切り替えてみたときの驚きは忘れられません。
画面の奥行や光の広がりが途切れずに表現され、本物の情景を前にしているようでした。
これこそが4Kの真価です。
ただし現実問題としては、4Kで遊ぶにはGPU性能以外の課題も山積みです。
電源容量やケースの大きさ、冷却性能をすべて見直す必要があります。
私は実際に組み上げてみて、冷却用ファンの音に悩まされ、発熱で頭を抱えました。
「本気でやるなら、それ相応の投資と工夫が必要なんだ」と身をもって学びましたね。
覚悟の瞬間。
自分に問うのです。
「ここまでやるか」と。
ここで一つ大事な補足になりますが、原神というゲーム自体はCPU性能を極端に必要とするものではありません。
私自身もCPUに過剰にお金をかけても効果は薄く、むしろGPUにしっかり投資したほうが満足度が高いことを実感しました。
「4Kで遊びたいならGPU最優先」。
これが答えです。
私の体験談を少し振り返ると、最初はフルHD環境でRTX 5060を用いて必要十分な満足を得ていました。
その後、好奇心に負けて4Kを導入したとき、映像の美しさに驚愕しましたが同時に「負荷のかかり方が別次元」だと悟ったのです。
ファンの風切り音がゲームの世界から引き戻してくる瞬間には、思わず苦笑してしまいました。
実際にユーザーの声を調べても、「フルHDならRTX 5060クラスで不満なし」と語る人は多く、私も同意します。
一方で4K挑戦者は口を揃えて「性能の壁」に直面している。
それでもなお4Kを選ぶ人は、やはり圧倒的な臨場感という価値を知ってしまったからでしょう。
今後のアップデートで描画負荷が増える可能性も考えれば、余裕を持ったGPU選びが賢明な判断だとあらためて思います。
120fpsを狙うならなおさらですし、GPUパワーが足りなければ結局は妥協を迫られる。
だから余裕を積んでおいたほうが、後悔が少なくなります。
私の出した答えはとてもシンプルです。
フルHDならRTX 5060程度で十分戦える。
ですが4Kを夢見るならRTX 5070TiやRadeon RX 9070XTが必要不可欠です。
中途半端に迷ってはいけない。
私はフルHDで「合理性」を知り、4Kで「憧れ」に浸りました。
その両方の体験を通じてようやく、GPUにお金をかける意味を心から理解したのです。
選ぶ基準は人それぞれですが、最後に残るのは「自分がどんな楽しさを求めているか」。
そこを明確にできれば、きっと後悔のないGPU選びができるはずです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48450 | 100766 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 31992 | 77178 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30003 | 65995 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29927 | 72584 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27029 | 68139 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26375 | 59548 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21841 | 56149 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19821 | 49904 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16479 | 38921 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15915 | 37762 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15778 | 37542 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14567 | 34520 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13675 | 30506 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13138 | 31990 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10768 | 31379 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10598 | 28257 | 115W | 公式 | 価格 |
144fpsを狙うならどんなGPU構成が現実的か
144fpsを安定させたいと思ったら、やはり一番大事なのはGPUです。
私も昔、CPUばかりに予算を割いて「きっとこれで快適に遊べるはずだ」と信じて組んだことがありました。
ところが実際はカクつきが気になって仕方なく、正直「なんで動かないんだよ」とため息をついたのを今でも鮮明に覚えています。
やっぱり土台はGPU、これに尽きます。
もしフルHDで最高設定、それでいて144fpsを安定させたいとなれば、現行世代ならRTX5060TiやRadeon RX9060XTあたりが妥当なラインになってきます。
これより下のグラボでも設定を落とせば遊べなくはないですが、フレームが不安定になると気持ちよくないんです。
ゲーム中に「なんでこんなにカクつくんだ」と感じるたびに、投資したお金が無駄になったような虚しさが募ります。
これ、本当に大事です。
解像度を上げたら話は大きく変わります。
WQHDや4Kで144fpsを狙うなら、RTX5070TiやRadeon RX9070XTといったクラスに手を伸ばす必要があります。
正直フルHDと4Kでは別世界。
以前WQHD環境からRTX5070Tiを導入したとき、あまりの安定ぶりに思わず「ここまで違うのか」と独り言をつぶやいていました。
数値以上の体感差ってこういうことかと、肌で理解した瞬間でした。
そして最近はDLSSやFSRの存在も馬鹿にできません。
私は以前「画質が落ちるのが気になるだろう」と思って避けていましたが、いざ試してみると意外と自然で驚きました。
原神のようなタイトルでも、描画をネイティブにこだわらずアップスケーリングを使ったら負荷が格段に軽くなり、さらに高いフレームを実現できました。
「技術の恩恵を活かすのも腕のうち」。
そう感じた体験です。
パワーに頼むだけじゃない工夫が、今の時代は大切なんだと思います。
BTOショップの構成をのぞいてみると、フルHD狙いにはRTX5060Ti、WQHDならRTX5070台といったように、解像度ごとにGPUが住み分けされているのがよくわかります。
これはメーカーの売り文句に踊らされた結果ではなく、実際に数え切れないユーザーの体感と検証の積み重ねが裏付けているものです。
CPUと違ってGPUの力不足はごまかせない。
構成を考える上での不動の事実です。
メモリはどうするか。
私は32GBを推したい派です。
もちろん16GBでも遊ぶだけなら問題ありません。
でも録画や配信、マルチタスクを考え始めると、余裕の違いは思った以上に大きいんです。
過去に「あと16GB積んでおけば…」と後悔した苦い経験があります。
だから今は最初から多めに準備しています。
ストレージも同様。
1TBのNVMe SSDを確保しておくと後悔しません。
最近はアップデートの容量がどんどん肥大化していますから、ぎりぎりの空き容量では更新のたびにイライラしてしまう。
これは避けたい。
余裕は安心そのものです。
実際に知人に頼まれて組んだときのことを思い出します。
Radeon RX9060XTとRyzen 7 9700Xを組み合わせた構成で、フルHDで144fpsを狙ったセットアップを用意しました。
半信半疑だった知人も、実際に数時間プレイしてみると「これなら十分だ」と笑顔。
最後に「もう少しお金をかけて正解だったね」と肩を叩かれたとき、私も安堵しました。
こういう笑顔を見られると、機材選びに真剣になる意味を実感します。
144fpsを出すこと自体は単なる数字の達成に見えるかもしれません。
しかし操作の滑らかさや視覚的な心地よさ、集中力の持続まで考えると、これは単なる性能指標以上の意味を持ちます。
まさに「ストレスなく遊べる環境づくりの核心」。
だからまずGPUに予算を割くべき。
逆にメモリやストレージは妥協しても大きな支障はありません。
とにかくグラボに軸足を置く。
ここだけは外せません。
ポイントは明快です。
それが失敗を避ける最善策です。
決して派手な裏技ではありませんが、確実性がある。
そしてゲーム中の不満を限りなく減らせる。
快適さ。
没頭感。
この二つを支えているのはGPU。
結局はそこに行き着きます。
つまり、限られた予算でもGPUだけは一歩上のグレードを見据えておくべきです。
それさえ外さなければゲームの最中に「しまった」と悔やむことはまずありません。
安心して遊べる時間を買う。
原神をサクサク動かすためのCPU選び徹底チェック
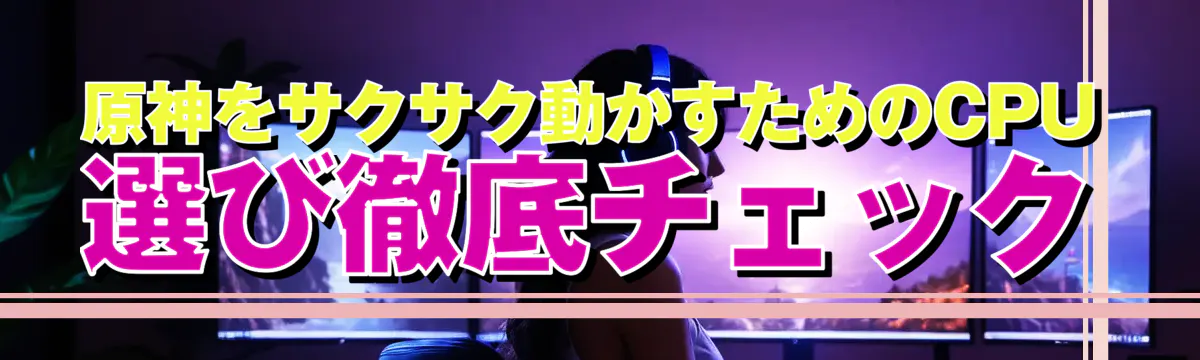
Core i7とRyzen 7、実際に試してわかった違い
私がこの二つのCPUを実際に使ってきて強く感じたのは、数字やカタログ値よりも「自分の求める使い方に合っているか」が最終的な決め手になるということです。
どちらも優れた性能を備えていますが、短時間で確実に結果を求めるのか、長く安定して走り続けられる余裕を大事にしたいのかで答えは大きく変わってきます。
それぞれのCPUに触れたときに感じたリアルな体験が、私の結論を大きく後押ししました。
初めてCore i7を使ったときの第一印象は「これは軽い」という直感でした。
特にゲームを起動した際、街のエリアに入る瞬間のサクサク感に思わず声が出たほどです。
ロードが短く、キャラクター切り替えもスムーズ。
NPCが大勢いる場面ですら処理落ちが気にならず、気持ち良さが持続しました。
ただし、空冷クーラー選びを誤ったせいでファンの音が妙に大きくなり、せっかくの没入感が削がれてしまった出来事は今も印象に残っています。
そのときは「失敗したな」と額にしわを寄せました。
Ryzen 7を同じ環境で使ったときは、印象がガラリと変わりました。
重たい大規模戦闘や同時に敵が一気に出現するようなシーンでも不思議と余力を感じられたのです。
長時間プレイしても粘り強く快適さを維持し続け、さらに配信ソフトや他の作業を並行して開いても平然と耐えてくれる姿には正直驚かされました。
一方でキャラクターの一歩目を踏み出す瞬間など、ごく細かいレスポンスはCore i7のほうがキレがあり「ここは少し遅いかも」と思うことがあったのも事実です。
とはいえ、その僅かな遅れよりも長く安心して遊べる安定感のほうが、私にとっては何倍も価値がありました。
私は正直なところ、温度管理に気を配るのがあまり得意ではありません。
長時間高負荷でCore i7を回していると「大丈夫かな」と不安がよぎる瞬間がありました。
特に一度ファンの回転音に邪魔されて集中力を欠いた経験は尾を引きました。
一方のRyzen 7は電力消費と発熱のバランスが思った以上に良く、中堅クラスの空冷クーラーでも安心して使えます。
静かに長時間快適に動いてくれる。
仕事で疲れた夜にゆったりゲームを遊ぶときなんか、本当にありがたい。
この安心感は見逃せないものでした。
車で例えるなら、Core i7は燃費そっちのけで一気に加速するスポーツタイプの車です。
ただし、長時間高速を走り続けるとなると少し無理を感じる部分が出てきます。
それに対してRyzen 7はツアラーのような存在。
安定した速度で走り続け、給油間隔も長く、安心して旅路を任せられる車のイメージです。
私は今の自分の生活スタイルを考えたときに、後者のほうにより心強さを感じました。
しかし実際に自分で長時間遊んで体感したことで、机上のデータでは測れない「快適さの質」が何よりも大切だと気づけました。
そうした体験を通じ、数字で判断するのではなく、自分の手で選んだほうが後悔も少ないと強く感じます。
Core i7の街エリアを駆け抜けたときの軽快さは本当に気持ちよく、それは仕事における即断即決のシーンを思わせます。
数分で結果を出すような大事な会議の場面と重なる。
逆にRyzen 7で続く戦闘を安定して乗り切れる耐久力は、長期プロジェクトに向き合うときの地道な粘りと同じものに思えるのです。
まさに耐久力。
現場の光景にもこれはよく表れます。
展示会場のデモPCはCore i7が使われていることが多い。
それは一秒でも止まってはいけない状況で安心感を優先した結果なのでしょう。
しかし、配信者が長時間にわたって動かし続ける環境ではRyzen 7が選ばれることも少なくありません。
止まらず持続できる。
それは放送トラブルを減らす大きな強みになります。
ビジネスの世界もまったく同じです。
表舞台のプレゼンは瞬発力が求められる。
でも裏方で長い計画を動かすには持久力が絶対に必要です。
この対比がCPU選びと重なって私は面白く感じます。
最近BTOショップの構成例を見て、改めて納得したこともありました。
Core i7とRTX 5070の組み合わせは、フルHDからWQHDまで隙なく快適に動かせるという定番の布陣。
まさに鉄板。
実際に使うと「確かにその通りだな」と実感できました。
そしてRyzen 7とRTX 5070Tiの組み合わせを「同時配信でも余裕を持って高画質で遊べる」と説明していたのですが、これは売り文句ではなく、実際に触った私の感覚と完全に一致していました。
現場感覚。
腑に落ちる瞬間でした。
以上を踏まえて、私の判断ははっきりしています。
多少音の問題があっても、それ以上に安心してレスポンスの速さを享受できる価値があるからです。
逆に、ゲームをやりながら並行して配信や別作業も欲張ってこなしたい人間、つまり昔の私のようなタイプにはRyzen 7しかない。
これを選んでからは迷いがなくなりました。
気持ちよく、長く使えるなと実感できたからです。
最後にもう一度整理すると、安心してブレのない環境を重視したいならCore i7が最適です。
安定と即応力。
これが強みです。
一方で、余裕と持続性を大切にするならRyzen 7です。
長い道のりを一緒に走れる相棒が欲しいなら、こちらを選ぶべきだと私は断言します。
CPUの差でフレームレートはどのくらい変化する?
原神のようなオープンワールドゲームを遊んでいると、ついGPUばかりに意識が向いてしまうものです。
しかし実際に遊んでみてはっきりとわかったのは、CPUの性能が思った以上にフレームレートや動作の安定に直結するという事実です。
敵が一気に湧き出してきたり、派手なエフェクトが重なったりする瞬間、CPUが追いつかずに数秒間だけ引っかかる。
ほんの一瞬でも、その違和感はゲームへの没入感を壊してしまうのです。
だからこそ「CPU選びを軽く見てはいけない」と実感しました。
数年前、私はCore Ultra 5の構成でWQHD・60fpsを目安にプレイしていました。
普段は問題ないのですが、マップを一気に駆け抜けるときや巨大ボスとの戦闘では「ん、なんかカクつくな」と思う瞬間があったのです。
その後Core Ultra 7に切り替えたとき、正直、驚きました。
GPUは同じなのにゲーム全体の安定感が見違えるほど変わった。
さらに高リフレッシュレート環境を試したときには、その差がもっと顕著になりました。
例えば144fpsや240fpsを本気で狙う場合、GPUが余裕でもCPUの処理が足を引っ張ってフレームが安定しない現象が表れます。
私は試しに配信しながらプレイしたのですが、Core Ultra 7やRyzen 7を使うと裏で録画や配信を走らせても目立ったカクつきが出ない。
妥協なんてできないな、と痛感しました。
けれどUnityエンジンの処理特性から、CPUのスレッド性能やIPCの高さは無視できない。
旧世代のCPUや省電力志向のモデルを選んでしまうと、fpsが伸びきらなくなるんです。
そして配信を伴った環境ではラグ感がそのまま視聴者に届いてしまう。
そんな体験をしたからこそ、私は声を大にして「配信を考えている人ほどCPU軽視は危険ですよ」と言いたい。
正直言って、以前の私は「ここまで差が出るなんて」と夢にも思っていませんでした。
ゲームがそもそも動くか、動かないか。
その次元の話ではありません。
快適に遊び続けられるかどうか。
fpsという数字よりも、プレイを長時間続けたときに安定性がどれだけ保たれるか、発熱や背景処理にどれほど柔軟に対応できるか。
そこに大きな違いがあるのです。
最近のCore UltraやRyzen 9000シリーズではAI処理の最適化も効いており、複数のタスクをさばく力に余裕が出てきました。
その成長を肌で感じると、技術の進歩への感動すら湧いてきます。
鮮明に覚えている出来事があります。
仲間とマルチプレイしていたとき、たった数フレームの処理落ちで操作が遅れ、敵の攻撃をまともに受けた瞬間です。
ほんの一瞬のズレですが、その悔しさは想像以上。
CPUを強化した後はそうした場面でのストレスがなくなり、プレイにぐっと集中できるようになりました。
安心感と言うより、もう一歩上の余裕とでも言いたい気持ちでした。
安定性。
この一点だけでもCPUをちゃんと見直す理由になる、と私は思います。
では最終的にどう位置づければ良いのか。
ただ、本当に滑らかなゲーム体験を求めるのであればCPUの存在を外すことはできません。
60fpsを安定して出す程度ならCore Ultra 5やRyzen 5で十分です。
ですがリフレッシュレートの高いモニターで高fpsを狙い、さらに配信や録画などの同時タスクをこなしたい。
そんな環境を描くのであれば、Core Ultra 7やRyzen 7が現実的な答えになります。
私が伝えたいのは、「GPUに投資するだけでは快適さは保証されない」ということです。
CPUを軽視すると、せっかくの高性能GPUが本領を発揮できず、パワーを余らせてしまう。
その現実を思い知らされて以来、私は常にワンランク上を意識して選ぶようになりました。
コストを抑えるより、長い時間しっかり楽しめる安心感の方がずっと価値があるからです。
それは実際に身をもって学んだことでした。
だからこれから本気で原神や他の3Dゲームに取り組むためにPCを新しく組もうとするのであれば、ぜひCPUも併せて検討してください。
快適さの基盤とはGPUだけでなく、間違いなくCPUも担っている。
私はそう信じていますし、この考えに何度も助けられてきました。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42850 | 2438 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42605 | 2244 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41641 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40937 | 2332 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38417 | 2055 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38341 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35491 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35351 | 2210 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33610 | 2184 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32755 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32389 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32279 | 2169 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29124 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 2151 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22983 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22971 | 2069 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20762 | 1839 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19418 | 1916 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17651 | 1796 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15974 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15220 | 1960 | 公式 | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R59ABF

| 【ZEFT R59ABF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CF

| 【ZEFT R60CF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DC

| 【ZEFT Z55DC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59AO

| 【ZEFT R59AO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59CF

| 【ZEFT R59CF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信や同時作業も考えたときに安心できるCPUはどれ?
配信をしながらゲームを楽しむには、やはりCPUの余裕が欠かせないと私は思います。
クロック周波数の高さだけを見て「これで大丈夫だろう」と思い込んでいた頃もありましたが、実際に試してみると限界はあっけなく訪れるものでした。
ゲームだけが動けば良い段階を過ぎたなら、少し背伸びしてでも余裕あるCPUを選ぶことが、結局一番安心につながると思います。
数年前、録画ソフトを立ち上げつつ原神をプレイしていたときのことをはっきり覚えています。
CPU使用率が振り切れ、ゲームの映像は何とか出ているのに音声が途切れ途切れになり、耳を刺すようなノイズに襲われました。
イライラしか残りませんでしたよ。
そのとき、GPUは余裕を残していたのに、CPUだけが息切れしていた。
あれは本当に苦い経験で、結局CPUをミドルから一段上のクラスに替えたら状況が嘘のように改善しました。
ケチると結局損をする。
私自身の経験から見ても、配信を前提に考えるならIntelならCore Ultra 7以上、AMDならRyzen 7以上が一つの現実的な基準です。
もちろんゲーム単体だけならミドルクラスで十分ですが、配信ソフトや動画編集ツールを同時に動かすと、一気にCPUが追い込まれて限界が露呈します。
気持ちよく遊んでいる最中にフリーズやカクつき。
同じ「動く」でも快適に楽しむか、我慢を重ねるか。
その違いはCPU選びに直結するのです。
そしてよく耳にする「コスパ」。
これを鵜呑みにすると痛い目を見ます。
安いCPUを選んでGPUにばかりお金をかけたとしても、CPUが追いつかなければ宝の持ち腐れです。
実際に私もそうでした。
数字上は立派でも、CPUが処理の足を引っ張ると快適な動作は望めません。
必要な投資をけちるかどうかは自分の首を絞めるかどうかの分かれ目。
節約と無駄遣いの境界線は思った以上に薄いんですよね。
最近では生成AIもセットで使う人が増えています。
AIアシスタントを常駐させながらゲームをしたり配信したり。
これらは当然CPU負荷をさらに積み増していきます。
だから「ゲームが快適に動くかどうか」だけを判断基準にするのは危険きわまりない。
選択の一手で未来が変わります。
新しい潮流として見過ごせないのがNPUの存在です。
AI処理に最適化された専用回路がすでに搭載され始め、動画編集ソフトや配信支援ツールが実際にそれを活用し始めています。
私は当初「そんなのはまだ先の話だ」と思っていましたが、時代の進みは想像以上に早かった。
CPUは単なる演算器ではなく、AIを支える土台へと役割を広げつつある。
その事実に気付いたとき、今後の選び方にも自然と変化が生まれました。
冷却の重要性も忘れてはいけません。
例えば原神のようにGPUに負担が大きいゲームでも、配信と組み合わせればCPUにかかる負荷は一気に増えます。
長時間高温にさらされれば、性能は落ち、結果として安定性を欠いてしまいます。
水冷にこだわる必要はありませんが、静かで性能の確かな空冷クーラーは数多くあります。
音がうるさい環境では集中力が途切れ、せっかくの時間がイライラで台無しになることもありますから、ここも妥協すべきではないでしょう。
では、最終的にどのクラスを選ぶべきなのか。
私の結論はシンプルです。
ゲームだけを楽しむならミドルレンジで十分ですが、配信や編集など複合的に楽しむならCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3Dあたりが現実的で、安心感と性能のバランスが取れた答えになると思っています。
その上でさらに余裕が欲しければハイエンドを選べばいい。
とはいえ私のような働き盛りのビジネスパーソンが日々の仕事の合間に趣味として楽しむなら、この辺りで十分満足できると感じています。
性能、温度、価格。
その三本柱。
私はこれまで何度も中途半端な選択で後悔を繰り返してきました。
だからこそ、声を大にして伝えたいのです。
CPUに余裕を持たせてやること。
それが結果として効率を高め、自分の時間を守ることにつながります。
CPUはただの数字やベンチマークではない。
生活の確実な土台を支える存在です。
安定こそ正義。
頑張った分がきちんと報われる構成。
それが理想の環境ですし、そこに到達したときの気持ちは言葉にできないくらい安心で、心地よい。
ゲームや配信、そしてAIまで含めて日常の楽しみとするならば、未来を見すえた選び方をすることこそが何より大切です。
私は自分の経験を踏まえ、やっとその考えにたどり着けました。
快適に遊ぶためのメモリ容量とストレージ選びのコツ
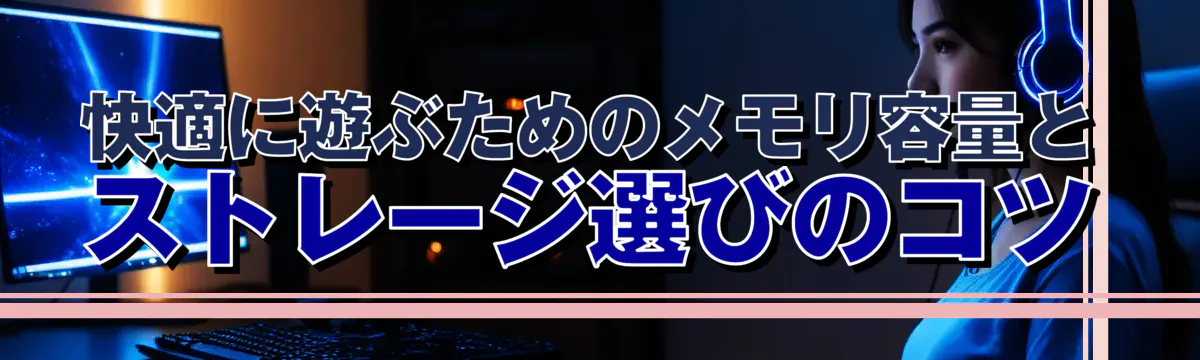
16GBメモリでどこまで快適に動くのか実際に試してみた
実際に私が16GBメモリ環境で原神を動かしてみたとき、一番強く感じたのは「普通に遊ぶだけなら本当に十分」ということです。
フルHDで璃月港や稲妻の街並みを歩いても、画面がカクついてイライラするような場面はほとんどなく、むしろ快適に遊べました。
普段のプレイでここまで動いてくれるのなら、安心して没頭できるなと素直に思ったのです。
ただ問題は、ゲーム単体ではなく組み合わせて使ったときでした。
Discordで仲間と話しながら、さらに配信用のソフトを立ち上げた瞬間、タスクマネージャーを見ればメモリ使用量は12GBをすぐ超えてしまう。
画面の切り替え操作で一瞬だけ引っかかるのを感じて、あぁ、この微妙な違和感が積み重なったらストレスになるなと痛感しました。
ほんの僅かな差。
でも気になる。
正直に言えば、私もゲームを始める前は「16GBもあれば十分に違いない」と思っていました。
ところが原神はアップデートのたびに少しずつ負荷が大きくなり、気づけば以前は平気だった場面で引っかかるようになってきたのです。
まさに痛感です。
その環境で録画を始めた途端にフレームドロップが起こり、「あぁ、ここで16GBの壁に当たるのか」と現実を突きつけられました。
ゲームだけなら不足はない。
でも配信や録画を含めると一気に限界がくる。
それが非常に明確に表面化するのです。
なぜこうもシビアに変わるのか。
特に意外なのは戦闘よりも、草木や霧の描写のほうが重くなる場面があることです。
その瞬間にわずかな遅延を感じ、「あれ?」と思って集中力が切れる。
小さな違和感ですが、人間の感覚には確かに残ります。
一方で、最近のDDR5は正直驚くほど進化しています。
容量だけ見ていると「大きいほうが当然有利」と思い込みがちですが、世代が違えば単純な比較は意味をなさないのだと痛感しました。
つまり規格の進化で、昔なら32GBが必須だった状況も、今では16GBで済ませられることが多くなっているのです。
この進歩の速さには本当に驚かされました。
だからこそ、自分の使い方を整理することが重要になります。
誰にも見せず一人で遊ぶだけなら16GBで問題なし。
でも録画したい、配信したいとなれば一気に32GBが必要になる。
欲を言えば余裕は多いに越したことはないし、実際そのほうが安心ですよね。
ただ現実はバランスをどう取るか。
この一点に尽きるのです。
昔、仕事で余ったオフィス用PCのメモリを増設し、原神を試しに動かしたことがありました。
最初はなんとか遊べたのですが、数時間でストレージのスワップが動き始め、動作全体がじわじわと重くなっていく。
正直、楽しむどころかイライラが勝ってしまいました。
そのとき私は強く実感しました。
メモリだけでなく、SSDの速度や空き容量といった要素も同じくらい大事なのだと。
ここを軽く考えると必ず足をすくわれる。
まさに苦い教訓でした。
つまり、グラフィックボードの性能がフレームレートを左右するのは当然としても、メモリとストレージの兼ね合いを無視すると快適さが崩れるということです。
私が実際に感じたのは、ボトルネックを一つでも外さない限り、ゲームを心から楽しむことはできないという現実でした。
私が今回まとめて言えるのは、原神だけで遊ぶなら16GBは十分ということです。
ただし、配信や録画を考える人にとっては、余裕を持って32GBを選ぶべきだということ。
数値上の違いよりも、実際の体感としてハッキリと差が出ます。
安心感。
私にとって16GB環境は「プレイを楽しみたいだけなら大丈夫」と胸を張って言える一線でした。
しかし、欲張って録画や配信を加えるのであれば、答えは明確に変わります。
32GB。
それが現実的な選択です。
最終的にどうするかは自分次第。
ゲームとの向き合い方が、選択を決める。
これが私、40代のビジネスパーソンが体験して導き出した、生の答えなのです。
信頼できる道しるべ。
SSDのGen4とGen5、今選ぶならどっちが賢い?
私自身もその一人でした。
ただ、自分で実際に試し比べてみて実感したことがあります。
頭で理解するよりも、日常で触れる感覚として納得せざるを得ませんでした。
正直に言えば、Gen5のスペック表を眺めたとき、あの圧倒的な数値の羅列に胸が高鳴ったのは確かです。
新しいものに触れたいという気持ちもあり、期待を込めて導入してみました。
しかし、楽しみにしていたゲームの体感はどうかと言えば、ほとんど違いはなし。
いや、それどころか熱対策という余計な課題までついてきました。
巨大なヒートシンクをケースに押し込む不自由さ。
財布が軽くなる現実。
そのあたりを肌で感じたとき「性能の数字に惑わされすぎたな」と思わされたのです。
落胆。
一方でGen4 SSDは派手さはないけれど、日常使いで確実にメリットを感じます。
例えば「原神」のように大容量のアップデートが頻繁にあるゲームでは、データ展開の待ち時間が短く済むことが非常に大きいのです。
その数分という小さな差が、仕事帰りに「さあ遊ぼう」と思ったときの気持ちを邪魔しない。
これは本当に救いなんですよね。
容量選びでも私は苦い思いをしました。
最初はコストを抑えようとして1TBを選んだのに、録画データとゲームだけで一気に圧迫。
仕事終わりに遊ぼうと思っても、不要ファイルを消す作業に追い込まれる。
疲れが倍増しました。
思わず「自分は何をやっているんだ」と声を漏らしました。
最終的には2TBに切り替えて大正解。
余裕があるって、こんなに気が楽になるのかと驚いたほどです。
毎回思うのですが、容量には妥協しない方がよかった。
Gen5を正当に活かせるのは、動画編集を日常的に行っている人や、大容量のデータを高速で処理する必要がある人だと思います。
そういう専門的な用途では、時間短縮が製作効率に直結するので理にかなっています。
ただ、ゲーミングだけの観点で見た場合、そのためにマザーボードから冷却パーツ、ケースの内部構成まで追加投資を求められるのは割に合いません。
ロード時間が数秒縮まる程度で、本当に満足できるか。
試しに「原神」でエリア切り替えを計測してみたのですが、Gen4とGen5の誤差はわずか。
もはやストップウォッチをしなければ気づけないレベルです。
その一方で、過剰な発熱から逃れる工夫をする必要がないGen4の方が、静かで快適な環境を維持できます。
騒音が減れば好きな音楽やキャラクターの声を集中して楽しめる。
それこそがゲームの醍醐味なのだと気づかされました。
静けさの価値。
私が導いた結論は明快です。
ゲームを快適に楽しむためならGen4 SSDを選べば間違いない。
性能、コスト、発熱のバランスが取れており、安心して長く付き合える。
特に40代になった今の私には、この「バランス」が一番ありがたいのです。
最新規格を試すことがステータスであり、そこにロマンを感じたのです。
しかし家庭を持ち、時間が限られる生活の中で、無駄な投資や余計な手間がどれだけ心をすり減らすのかを学びました。
快適さを数値でなく体験で計る。
その視点は年齢とともに強まる一方です。
無理をせず、自分に必要な機能をちゃんと選ぶこと。
それが豊かさにつながると感じるようになりました。
だから私は、人からSSDについて相談されたときには必ず自分の経験を踏まえて話します。
これは試行錯誤の末にたどり着いた確信です。
最新スペックを追いかけて息切れする人生よりも、実感できる快適さを大事にした方がよほど幸せだと強く思っています。
最終的にここまで悩み、試し、失敗を経て得た答えは一つです。
私の心からの実感です。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |










2TBストレージは本当に必要?アップデートや他ゲーも想定して考える
PCを新しく組む時、ストレージの容量をどうするかは真っ先に考えるべきことだと、今になって強く感じています。
私は過去に「まあ、1TBで十分だろう」と軽く判断して、その結果、何度も後悔してきました。
だから最初から2TBにしておけば良かった、と今でも思います。
少し大きめの容量を選んでおくことで、日常の余計なストレスから解放される。
これが私が伝えたい一番の結論です。
ゲーム好きな私は、アップデートや別タイトルの追加でストレージを圧迫する場面を何度も経験しました。
数字だけで言えば、例えば原神は約100GB前後。
他の大型タイトルを2本足せばそれだけで300GB近くになります。
そのうえアップデートのパッチや一時展開用の領域なんて加われば、空いているはずの領域がすぐに不安定になってしまう。
そうなると、1TBではあっという間に残りが心もとない。
実際、私の環境ではアクションRPGとシューターを並行して遊んでいたとき、残り容量が150GBを切った瞬間から、アップデート中にパフォーマンスが落ち込み、ゲームがまともに動かなくなったこともありました。
あのときの苛立ちは、忘れられませんね。
「空き容量なんて整理すればいい」と若い頃の私は思っていました。
でも実際は、削除と整理に時間をとられて、せっかく確保した余暇の気持ちが削れていくばかり。
遊ぶどころじゃなかった。
正直、やるせなかったです。
貴重な土曜の夜を、不要データを選んで削除するだけで終わらせた時の虚しさ。
あれは本当に無駄でした。
2TBを選ぶ意味は、単に容量が大きいというだけではありません。
心の余裕です。
私は今ではシステム用に1TB、データとゲーム用に2TBを積んでいます。
その結果、試しに新作をインストールする余裕が持てるようになり、わざわざアンインストールを繰り返す必要もなくなりました。
おかげで何より精神的に楽になりました。
空き容量に怯えながら遊ぶなんて、本末転倒じゃないですか。
購入コストも、今は昔と違って2TBが現実的な選択肢になっています。
Gen.4 SSDも随分安くなり、1TBとの差は以前のような大きなハードルではなくなりました。
それなら余裕を持って2TBにしておく方が、明らかに賢い投資です。
しかも2TBにしたところで、数年はストレージ不足に悩まずに済むと思えば、費用の価値は十分すぎるくらいあると感じています。
特に忘れてならないのは、動画データや作業データを扱う人の存在です。
それを編集ソフトで扱うとき、空きが足りないと処理が止まるんです。
その時の悔しさは今でもはっきり覚えています。
遊びでも仕事でも、ストレージの不足は全てのやる気を削ぐ。
これは断言できます。
だから私は声を大にしたい。
ストレージは余裕を見て2TBを用意すべきです。
途中で増設するにしても、その間に感じるストレスや、無駄にした時間の大きさはお金で換算できません。
余裕とは、安心です。
ちょっと大げさかもしれませんが、本当に心を軽くします。
もちろんすべての人に2TBが絶対必須だとは言いません。
軽めの用途なら1TBで十分でしょう。
むしろ安心感が得られますし、「あ、あのタイトル気になる」と思った瞬間にインストールして遊べる気軽さは何よりも大きな魅力です。
容量を理由にインストールを諦めるなんて、考えるだけでもつまらないですから。
私が本当に求めていたのは、安心して遊び続けられる環境でした。
容量不足で焦ることもなく、削除や再インストールで貴重な時間を無駄にしない環境。
それが整ってはじめて、自由に遊べる喜びを感じられる。
遊びたくなったらすぐに起動できる。
私はただ、それが欲しかったんです。
これから数年、私は2TB SSDと共に原神や他の大作を余裕を持って楽しみ続けるつもりです。
容量に振り回されず、時間を削られず、心を重くしない。
そのためには最初から2TB。
私は皆さんにこれを強くおすすめしたいと思います。
遊びや仕事を問わず、PCをストレスなく使いたい方には、これが一番の近道です。
もう、容量不足で悩む暮らしには戻りたくありません。
冷却とケースの違いでここまで変わる! 原神用ゲーミングPCの安定性


静音重視なら空冷?それとも水冷のほうが安心?
静音と冷却、どちらを優先するかを考えると、やはり用途や状況によって答えは変わってくると私は思います。
特にGPUの発熱が強烈に効いてくるゲームをやっていると、ケース内にこもる熱が厄介で、空冷だけだとファンが急に高回転になり「うるさいな…」とイライラした経験が何度もありました。
夜中の静かな時間ほど音は敏感に響いてきますからね。
ただ、これはあくまで一面にすぎません。
空冷のパフォーマンスだって今は侮れないんです。
CPU用の大型空冷クーラーはとにかく冷えるし、正しくエアフローを設計すれば驚くほど静かに動いてくれる。
私も以前「空冷はどうせうるさいだろう」と決めつけていたんですが、その考えを覆された瞬間がありました。
「やっぱり食わず嫌いはよくないな」としみじみ思いましたね。
水冷には水冷ならではの魅力もあります。
ラジエーターに熱を流すことでケース全体が熱気に包まれるのを防ぎ、ファンをゆったり回すだけで安定した冷却を得られる。
これは本当に快適です。
設置の仕方やラジエーターとファンの組み合わせ次第で音の質は大きく変わってしまう。
実際、ポンプの微妙な駆動音が気になることもあって、その意味では空冷の安心感に惹かれる人が多いのもうなずけます。
しかも水冷は定期的なメンテナンスや数年ごとの交換を意識しなくてはいけない。
ポンプの寿命や冷却液の劣化は避けて通れない宿命です。
それに対して空冷は構造がシンプルで、ほこりさえ取り除けば長年問題なく動いてくれる。
耐久性を重視するなら空冷に軍配が上がるのは間違いありません。
気楽さ。
一方で、ハイエンドGPUを積んで4K環境や高リフレッシュレートで動かすなら私は水冷を選びます。
GPUからの発熱が部屋の空気を押し上げるようにケースに重くこもり、それがファンを急激に回させる。
結果的に「静音性重視」という前提が崩れてしまうんです。
静かなまま安定したパフォーマンスを維持できるのは、大きなアドバンテージです。
こうして両方を見比べた結果、私の中ではある程度明確な線引きができました。
フルHDやWQHD、つまり通常プレイで楽しむ程度であれば、空冷で十分静かで安定した環境が作れる。
それに必要以上の費用もかかりません。
一方で4Kや配信同時進行、さらに144fps以上を狙うヘビーなプレイを前提にするなら水冷が必要になる。
結局のところ「性能帯とプレイスタイル次第で選べばいい」というシンプルな答えに落ち着いたわけです。
最近私が組んだマシンでもそれを痛感しました。
初めは水冷を想定していたのですが、正直あえて空冷にして大正解でしたね。
CPUも十分冷え、音もまったく気にならない。
配線もシンプルで、整理がとにかく楽になった。
「これならもう十分だ」と強く実感しました。
妙に心が落ち着くんですよ、そういうのって。
ただ、次にやりたいことがもし高解像度配信や複数アプリを重ねての負荷処理なら、そのときは迷わず水冷を選ぶと思います。
私の経験上、仕事で長時間負荷をかけながら使っても快適さが続くのは水冷。
でもこれが現実的なところです。
静けさを求めるなら、どちらを選んでも工夫次第で結果は変わる。
本当にそう思います。
大事なのは自分が何を優先したいかを見極めることなんですよね。
私はそのたびに自分の使い方を振り返りながら、次の構成を考えるようにしています。
試行錯誤。
そして失敗も学びになる。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EE


| 【ZEFT Z55EE スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (FSP製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DU


最新技術で魅了するエクストリームゲーミングPC、勝利をさらに美しく演出
バランス感覚が光る、驚異の32GBメモリ&1TB SSD, 快速体験をデスクトップへ
透明な風を彩るCorsair 4000Dケース、スタイリッシュな透過美を堪能するデザインモデル
Ryzen 7 7800X3Dで、PCの心臓部もパワフルアップ、次世代の速さを体感
| 【ZEFT R56DU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61C


| 【ZEFT R61C スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45CFP


| 【ZEFT Z45CFP スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN EFFA G08IB


| 【EFFA G08IB スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
エアフローのしっかりしたケースは実際にフレーム安定に効くのか
エアフローの良いケースを選ぶことは、最終的に快適なゲーム体験そのものを左右する重要な要素だと、私は身をもって痛感しました。
性能の数字やベンチマーク結果に安心してしまいがちですが、実際のところは数字以上に「体感の快適さ」を決めるのが冷却であり、空気の流れなのです。
昔の私は、ベンチマークの数値ばかりを追いかけ、「これなら十分いける」と自信満々でしたが、実際にゲームをすると、どうにも小さな引っかかり感が頻発し、集中力をそがれていました。
その時の違和感は些細なものでも、長時間プレイすればするほど積み重なって、大きなストレスになっていったのです。
私がかつて使っていたケースは、正面のデザインが密閉気味で、フロントパネルがほとんど塞がれていました。
当時は見た目重視で「格好いい」と思って飛びついたのですが、いざ使ってみるとGPUの温度は高めに推移し、敵が大量に出てくるシーンやエフェクトが重なる瞬間に、映像のカクつきが目立ちました。
そのとき思ったのです、「これは数字だけじゃ測れないものがあるな」と。
あのガタッと一瞬止まったように感じる不快さは、まさに現実を突きつけられる瞬間でした。
その後、思い切ってエアフローを重視したケースに買い替えたのですが、正直ここまで違うものかと驚かされました。
前面がしっかりメッシュになっていて吸気が自然に行われ、さらに天板の排気も効率よく機能する構造。
同じGPUと同じCPUを使っているのに、温度が平均して10度近く下がり、プレイがとにかく安定したのです。
数字以上に大きな変化を感じたのは、「安心してプレイできる」という感覚でした。
安定感。
違いは体で分かります。
放熱の意識は、ハイエンドPC環境だけの話ではありません。
中堅クラスの構成でも、ケースが通気性に優れていれば、プレイの安定性は大きく変わります。
Core Ultra 5とRTX 5060のような構成でも、エアフローの有無によって長時間プレイ時の快適さには大きな差が出る。
逆に閉塞的なケースを使えば熱がこもり、ファンの音がうるさくなる。
せっかくの静音設計のはずが、熱に追い込まれてファンが全力で回り続ける……これほど本末転倒なことはありません。
静音性は冷却と表裏一体です。
最近は「CPUやGPUの効率が上がっているからそこまで冷却に神経質にならなくてもいいのでは?」という声もあるのですが、私は全くそうは思いません。
電力効率が良くなっても、熱は必ず発生しますし、ゲームのような高負荷のシーンでは、その差が顕著に現れます。
温度が上がれば転送速度の低下や寿命の縮みにつながる。
メモリや電源回路なども含め、全体の快適性を維持するためにエアフローが縁の下で支えているのです。
思い出すのは、以前SSDの速度が妙に不安定になった時のことです。
ベンチマークでは速いのに、ゲーム内のロードで「あれ?」と感じる場面が増えました。
原因はケース内の通気不足でSSDが熱を持ってしまっていたことでした。
ケースを換えて十分な風が流れるようにしたら、その不安定さはきれいに解消された。
それを体感したとき、「あぁ、ここまで冷却の差が効くのか」と感心しましたね。
外観も大事ですが、やっぱり見た目に流されてはいけません。
ガラスパネルや光るファンに惹かれる気持ちは私にもありますが、それに夢中になるあまり吸気と排気の通り道を忘れたら本末転倒です。
派手な格好をしていても、肝心の中身が熱で性能を引き出せないなら宝の持ち腐れですし、むしろ過剰にお金をかけたスペックを自ら潰しているようなものです。
見た目と機能のバランス。
これが大事です。
私が学んだ一番のことは、数字を読むだけでは分からない「実感の価値」です。
私はケースを替えて、映像がスムーズに動く瞬間に「あぁ、これが本当の姿なのか」と心から納得しました。
あのときの嬉しさは、数字では測れないものでした。
もう戻れない。
強くそう思いました。
FPSが安定して、熱の心配に振り回されない環境。
これは、単にパフォーマンスが高いという以上に安心感をもたらします。
原神のように動きが忙しいタイトルや、FPSのように一瞬の精度が勝負を分けるゲームであればあるほど、この差は決定的です。
144fpsを狙いたい、それをずっと維持したい、そう思うならエアフローを決して軽く見てはならないのです。
グラフィックカードやCPUと同じくらい、いや、それ以上に慎重に選ぶ対象だと私は考えています。
私は今、自分のPC環境に本当に満足しています。
その満足の理由を突き詰めれば、行き着く答えは「冷却に対する真剣さ」でした。
スペックを選ぶ熱意は誰もが持っていますが、最後に土台を固める冷却にこそ本当の価値がある。
見た目と扱いやすさを両立するケースの選び方
最終的に答えはひとつで、デザイン性と実用性を両立できるケースを選ぶことが最善なのです。
これは口で言うほど簡単ではありませんが、私自身が経験してきた中で強く実感したことです。
過去に私は見た目に惚れ込み、勢いでケースを買ったことがありました。
フロントパネルのデザインが格好良くて、一目見ただけで心を奪われたのです。
しかし、真夏のゲーム環境でその選択が裏目に出ました。
GPUの温度が急上昇し、気がつけば快適に遊べず、処理落ちに悩まされる始末。
デザイン性は抜群でも実際の快適さを失ってしまえば後悔するしかない。
あのときの苦い記憶は今も鮮明です。
やはり温度管理が全ての軸になります。
原神のように負荷が高いゲームを長時間プレイすればGPUもCPUも必然的に熱を帯びます。
ですから、ケース内部は広く、複数のファンを設置でき、配線をスッキリまとめられる構造であることが欠かせません。
ここを妥協すると冷却効率が極端に落ち、パーツの寿命にも影響する可能性があるのです。
私は一度配線処理を軽視した結果、空気の流れが滞り、夏場はPCが悲鳴を上げるような動作をしたことがありました。
そのときほど「面倒でも配線に気を配るべきだ」と強く思ったことはありません。
さらに忘れてはいけないのが掃除のしやすさです。
以前、私はメンテナンス性を無視してケースを選んだ結果、毎回の清掃が大変で、ため息ばかりついていました。
フロントパネルを外すのに工具が必要で、埃フィルターも複雑に固定されていて、気軽に掃除をする気になれなかったのです。
埃は溜まる一方、ゲーム中にファンの音がやかましくなり、「なんでこんなケースにしたんだろう」と思わずつぶやきました。
歳を重ねれば、ますますこうした小さなストレスが効いてきます。
手軽に分解できてフィルターを丸洗いできるケースのありがたさは、時間が経てば経つほど身に染みてきます。
外観の要素も見逃せません。
今流行の三面ガラスのピラーレスケースは、内部パーツを魅せる演出に優れていて、RGBファンと組み合わせればまるでアートのような美しさを楽しむことができます。
最近は木製パネルをあしらったケースも目立つようになりました。
知人の自宅で見た木調のケースは、観葉植物と馴染んでいて、まるで家具のようでした。
ぱっと見ではゲーミングPCだと分からない自然な存在感。
私も「これなら仕事部屋に置いても違和感がないな」と感じました。
一方で、私の自宅に一時期きらびやかなケースを置いたときは、木目調のデスクやモニターアームと全く調和せず、どうにも落ち着かなくて仕方なかったのです。
それがきっかけで、今では毎日眺めても疲れないことを選択基準の一つにしています。
違和感のない存在。
それが思った以上に大切です。
性能面で考えると、フルHDで遊ぶ程度ならミドルタワーケースで十分です。
私もかつて「大きなケースは場所を取るだけ」と思っていた時期がありましたが、実際に大型ケースを導入してからは空気の流れも改善され、掃除も楽になり、結果的にゲームも安定してプレイできるようになりました。
だから、大型ケースを選ぶことは無駄な贅沢ではなく、必要な投資だと今では心から感じています。
結局のところ、PCケースはゲーミングPCの土台に他なりません。
外観のかっこよさ、冷却効率、掃除のしやすさ。
これらすべてを意識しなければ、真に扱いやすい環境は整いません。
私はこの「地味だけれど欠かせない部分」をないがしろにして後悔した経験があるからこそ、強く声を大にして伝えたいのです。
見た目の華やかさに惑わされず、長期的に快適に使えるケースこそが本当に価値のある選択なのだと。
毎日の作業や遊びがスムーズに進むという何気ない安心が、実は一番の宝物なんだと気づきます。
そして最後に私が強く思うのは、ケース選びに妥協しないこと。
ただそれだけなのです。
自分の生活に調和し、感性に響くデザインであり、扱いやすくて掃除も容易。
長く一緒に過ごす存在だからこそ、そこに熱い想いを注ぐ価値があるのです。
原神用ゲーミングPC購入前によくある疑問に答える


入門クラスのゲーミングPCで原神は動かせる?
入門向けのゲーミングPCで原神を遊ぶことについて、私の率直な結論は「動くことは動くが、快適さとは別物」ということです。
最初に期待を込めて安いPCを買ったとき、確かに原神は起動しましたし、街を歩いたり軽い探索であればスムーズに動いていました。
しかし戦闘でエフェクトが激しく飛び交う瞬間になると、途端にフレームレートが落ち、カクつきがひどくなりました。
それが最初の挫折でした。
胸の内で「二度と妥協するものか」と固く誓ったのを、今でも覚えています。
当時使ったのはBTOで組まれた比較的安価なモデルでした。
仕様は世間で「入門機」と呼ばれる程度のスペックで、CPUはCore i5クラス、GPUはRTX3050に近いもの。
数字上では十分に見えても、実際にプレイしてみると要求の厳しさを思い知らされました。
原神は一見軽そうでいて、シーンによって負荷が急に高まる。
そしてそのギャップこそが、入門機で感じる一番の落とし穴だったのです。
目の前で画面がもたつくたび、ああこれが現実かと肩を落としました。
設定を低めに調整すればフルHDで60fpsを出すことは可能です。
ですが、それ以上を求めるなら途端に限界が見えます。
美しいグラフィックを高リフレッシュレートのモニターで楽しみたいと願っても、入門機の力では到底追いつかない。
そこで必要になるのは冷静な割り切りです。
フルHDで動けば十分と考えるか、より上を望むか。
自分の欲との折り合いをつけるしかありません。
それでも問題はゲームだけにとどまりません。
最近のアップデートで原神は次々と大きくなり、描画もより豪華になってきました。
そのたびに必要とされるリソースが増していきます。
私は一度、メモリ16GBの環境でプレイしていましたが、裏でブラウザを開いたりチャットアプリを常駐させた途端、途端に挙動が重くなり苛立ちを覚えました。
余裕は贅沢ではなく、快適に過ごすための必須条件なんだと。
最低でも32GBあった方が安心です。
ストレージも同様で、容量の少なさで苦しむのはもううんざりです。
1TBのSSDを積んでいれば、ゲームのアップデートごとに「空き容量が足りません」と言われて頭を抱えることもないでしょう。
GPUこそが一番の要となることも痛感しました。
CPUが同世代であれば少し劣っていても大きな問題はありませんが、GPUだけは性能が直結します。
RTX3050では遊べるものの、もし他にも重いゲームを触ってみたくなった時、一気に限界が来ます。
ケチってしまった結果、数年も経たずにGPUを変えたい衝動にかられ、後悔しましたね。
買い替えの無駄出費を避けたいなら、最初の投資がいちばん大切です。
思わぬ盲点だったのは、ケースの冷却性能でした。
最初は完全に軽視していましたが、夏場にGPU温度が90度近くまで跳ね上がり、画面がカクつき始めたのを見たときは背筋が凍りました。
「なんだこれ、壊れるんじゃないか?」と恐怖すら覚えました。
以来、私はケース内のエアフローや冷却構造には敏感になり、ここを軽んじるのはもう無理だと悟りました。
冷却こそ縁の下の力持ち。
軽んじてはいけません。
ゲーム配信や動画編集まで考える方にも忠告したいです。
入門機ではほぼ無理です。
ゲームをプレイするだけならまだしも、配信ソフトや編集ソフトを同時に立ち上げた瞬間、すぐに処理が追いつかなくなり、映像がズレたり音飛びが起きたりします。
私もかつて、チャレンジ精神だけで挑んだことがありましたが、数分で断念しました。
やはり欲張りすぎてはいけません。
背伸びをした結果、何も楽しめなくなる。
それが一番の失敗です。
こうして振り返ると、初心者が安心してプレイできる環境とは何かが見えてきます。
もし「フルHDで原神だけ動けばいい」というなら、入門クラスのPCでも成立します。
ただ、長く快適に遊びたいなら話は別です。
私は断言します。
メモリは32GB、GPUはワンランク上、SSDは1TB以上、ケース冷却も考慮。
それが当たり前になってきている。
ここで妥協すると未来の自分に大きな負担となって返ってきます。
私の考える理想像はこうです。
入門クラスでライトに遊ぶなら、納得の上で選びましょう。
ただ「やっぱり長く気持ちよく遊びたい」と思う人なら、ミドルクラスを最初に選ぶべきだと。
結局その方がコストも精神的負担も軽い。
だから私は声を大にして伝えたい。
「少し上を買うほうが結局は幸せだ」と。
安心感と納得。
この二つこそが最終的に残るものです。
私が振り返って強く言えるのは、失敗の経験があったからこそ今の考えがあるということです。
最初の一歩で妥協するかどうか。
その一点が未来の満足度を大きく左右します。
私にとって、それはもう間違いなく真実でした。
60fpsと144fps、体験としてどのくらい違いがある?
最初に驚かされたのはキャラクターの動作の自然さで、視点を振った瞬間に背景の奥行きがまるで別世界のように広がるんです。
60fpsでも十分だと思っていた私ですが、一度144fpsを経験すると「これはもう戻れないな」と素直に感じました。
後戻り不可。
特に戦闘シーンになると違いは顕著で、爆発のエフェクトやスキルの演出が144fps環境だと余裕を持って目に入ってくるんです。
処理落ちを気にせず敵の動きに集中でき、結果としてこちらの判断の速さまで変わってくる。
それだけでゲーム全体の迫力やテンポが1段階上に引き上げられたような感覚に包まれるんです。
気持ちの高揚感。
ただし、60fpsが悪いとは全然思いません。
むしろ実用性を考えたら十分です。
60fpsなら多くのPCで安定して遊べますし、長時間プレイしてもファンの音や熱に悩まされません。
電気代や機械の負担を気にする私の世代にはありがたい仕様で、実際「60fpsで十分現実的だな」と思える強みも確かにあるんです。
それでも144fpsで原神を遊んだあの日の衝撃は忘れられません。
RTX5070を積んだPCでフィールドを歩くだけで、草木の揺れや空の表情に没頭してしまい、戦闘はもちろん歩いているだけでも心が浮き立つ。
ジャンプ攻撃から回避に繋ぐ動作一つひとつが軽やかで、ゲームの中に本当に入り込んだような錯覚すら覚えました。
投資した価値を実感した瞬間でした。
144fpsを本気で狙うならGPUがボトルネックになる。
「ここは絶対に譲ってはいけない領域だ」と、私は痛感しました。
GPU投資。
もちろん、だからといって無条件に144fpsが正解かといえばそうでもありません。
WQHDや4Kで遊びたいと欲張ると、GPUへの要求は跳ね上がり、逆にフレームレートが落ちて本末転倒になるリスクもあります。
結局は目的と解像度のバランスをどう取るかが大切で、その冷静な見極めが必要だと身をもって実感しました。
理想はフルHD環境で144fpsを安定させること。
これこそ最も実用的かつコスト効率に優れた形だと考えています。
実際に私の周りでも、まずはフルHD+144fpsを達成してから徐々に解像度を上げていく人は多く、その人たちはみな口を揃えて「これが一番満足度が高い」と話しています。
最初から高解像度を追い求めた結果、滑らかさを犠牲にしてギクシャクした映像に悩むよりも、まずは動きのスムーズさを確保した方が確実に楽しい時間が続くんです。
やっぱりそこなんですよ。
そして冷静に考えれば確かに消費電力も増えますしコストも上がります。
それでもですね、人生の中で趣味としているゲームにおいて、体験そのものの質を最優先にした方が圧倒的に満足感が違います。
画質を見栄えだけで追いかけるよりも、まずは自然で滑らかな動きを堪能できることの方が、結果的に心のゆとりや贅沢さに繋がるんです。
これは間違いないと断言できます。
私が到達した考えはシンプルです。
60fpsは安定的で安心できる選択肢です。
しかし、もし本気で原神という世界に没入したいのなら144fpsしかないと思います。
その一歩を踏み出した瞬間に、ただのゲームが圧倒的な体験へと変わり、価値そのものが塗り替えられるんです。
私の胸に刻まれたのはこの事実でした。
最終的な判断は人によって違います。
持続性を取るか、それとも没入感を選ぶか。
費用を重視するか、体験を優先するか。
私自身は「少し無理してでも144fpsを選ぶ」ことを選びましたし、それが後悔のない選択だと確信しています。
ゲームに本気で向き合うとき、結局最後に残るのは感情の満足度なんです。
究極のプレイフィール。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CG


| 【ZEFT R60CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DE


| 【ZEFT Z55DE スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61F


| 【ZEFT R61F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59BZ


| 【ZEFT R59BZ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOと自作、コストと満足度で比べたときどちらが得?
BTOパソコンと自作パソコンを比較したとき、実はコスト面だけではなく、その後の使い心地や満足度にまで大きく影響が出る、というのが私の実感です。
正直に言えば、もし「原神を本気で快適に遊ぶため」に新しいゲーミングPCを買うなら、現時点ではBTOを選ぶのが一番無難であり、結果的に得をする選択だと強く思います。
理由はシンプルで、パーツの価格変動や供給不足を考えると、個人で一つひとつの部品を買い揃えるよりも、大量に仕入れて全体価格を抑えているBTOモデルのほうが圧倒的に有利だからです。
実際に私は一度、自作を試してみようと見積もりを取りました。
しかし、結果は逆で、むしろBTOよりも2万から3万円ほど割高になってしまいました。
しかも冷却やケース設計を自分の知識だけで判断すると、排熱や騒音の問題に直面します。
そのとき数字には出ないけれど、机に座って遊んでいるとじわじわ堪えるストレスが積み上がるんですよ。
原神のように長時間プレイするゲームでは、この「小さな違和感」が大きな疲労感になって返ってきてしまう。
だから余計に現実的な選択が必要なのだと痛感しました。
とはいえ、自作の楽しさを否定するつもりはありません。
ケース越しに光るRGBライトを眺めたときの満足感や、自分で取り付けたSSDの爆発的な読み込み速度を体感した瞬間は、これまでの苦労が一気に報われるような特別な感覚があるのも事実です。
自分の手で仕上げたものがきちんと動作する――その喜びは簡単には言葉にできません。
そして最近はCPUや冷却効率も改善されていて、空冷だけで安定運用できる環境も増えてきました。
正直、「思っていたより敷居は下がってるな」と感じる部分もありました。
ただ、やっぱり壁はあります。
あの黒い画面に電源だけが回っているときの虚しさは、言葉にしなくても分かる方もいるでしょう。
正直、心が折れそうになる瞬間。
そこから追加出費やサポート依頼に進むと、計画はどんどん狂います。
最初はコスパの良さを期待していたのに、結局出費と労力がかさんでしまうのは、まさに本末転倒だと感じざるを得ませんでした。
その点、BTOの強みは揺るぎません。
まず大きいのは安心感。
出荷前に動作確認がされていて、しっかり保証もついているのですから心強いです。
最近はカスタマイズの幅も広がり、静音性を重視するか、冷却重視にするかなど、ニーズに合わせて調整可能です。
さらにメモリやSSDのメーカーを選択でき、あらかじめ実績あるブランドを指定できるので、変な不安を抱え込まずに済みます。
これは、わざわざ専門店を回って単品を探し歩くことを思えば、かなり効率的で、しかも合理的だと感じます。
一方で、自作を選ぶ人がいる理由も分かります。
BTOより濃い愛着が持てるからです。
自分の手を動かした分、完成したPCはただの道具ではなく、まるで長く付き合える相棒のように感じられる。
これは確かに大きな魅力です。
ただし「原神を快適に遊ぶ」という一点に絞るなら話は別。
安定性が高まった今のミドルクラスの構成を選べば、BTOで十分に満足できる環境は整います。
私は実際にBTOで購入したPCを半年ほど使ってみました。
そのあとでGPUだけ自分で交換したのですが、これが思いのほか快適でした。
初期のリスクを避けたうえで、後から手を加える楽しさも味わえる。
余計な費用もかからず、保証まで残っている。
まさに一石二鳥です。
このやり方、正直なところとてもバランスがいいですよ。
結局、ゲーム用のPCに求めるものは何か。
どんなに選択肢が多くても、トラブルで時間を削られてしまえば意味がないのです。
だから私は断言します。
効率よく、安心して、しっかり遊びたいならBTOが現実的な最適解です。
もちろん、好みによって結論は変わるだろうし、趣味を追求して自作に時間を費やしたい人の気持ちもよく分かります。
しかしもし「原神を快適に遊ぶ」ためにPCを選んでいるのなら、私からは迷わず「BTOがおすすめ」と声を大きくして伝えたいです。
楽しむための道具に、余計なリスクや無理な負担はいらない。
シンプルに快適を選ぶ。
それが40代になった今の私が選び取った、実感のこもった答えです。
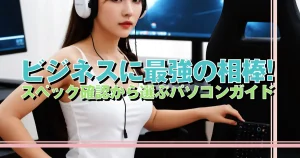
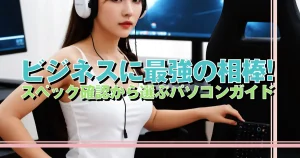
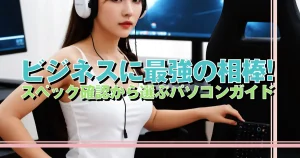



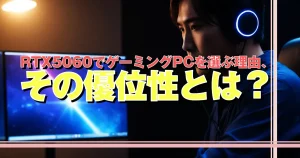
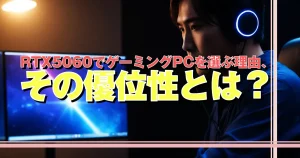
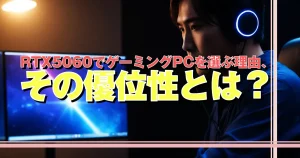
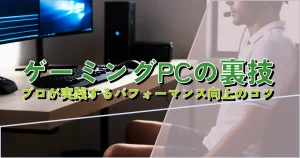
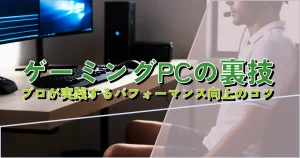
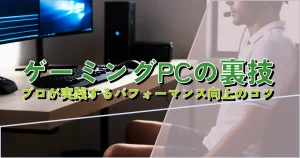
グラボ以外のパーツにどこまで予算を割くべきか
私自身が失敗を重ねた結果、CPUやメモリ、ストレージ、それに電源やケース、冷却にもきちんと予算を配分することが、最後は一番コスパの良い選択になると痛感しました。
なぜなら、それらを軽視したせいで「ちゃんと選んでおけば良かった」と何度も後悔してきたからなんです。
実際に経験して思い知ったことなので、机上の空論ではありません。
昔、私は「グラボさえ良ければ何とかなるはず」と思い込み、CPUを安価なモデルで済ませたことがありました。
その時は本気で楽観視していたのです。
しかし実際にプレイを始めると、敵が多い場面で一瞬止まったり、マップ切り替えがやけに引っかかったりして、嫌な汗をかきました。
あの「やってしまったか…」という瞬間を、今でもよく覚えています。
結局、後からCPUを交換しましたが、その作業の大変さと余分にかかった費用を考えると、最初から余裕のあるものを入れておけばよかったと心底悔やみました。
メモリも似たような体験をしました。
当時は16GBで組んで、まあこれで十分だろうと考えていました。
でも実際には、ゲームをしながらブラウザやチャットアプリを立ち上げたり、ちょっと配信を試したりする場面が多く、そういう時にカクつきが頻発したのです。
配信が途中からカクカクになると、ただの娯楽がストレスに変わります。
ストレージについては、私は幸い最初から大容量を選んだのですが、知人の500GB環境を見て痛感しました。
その知人は更新のたびに容量不足に悩まされ、古いデータを泣く泣く消しながら運用していたのです。
アップデートが来るたびに余計な神経をすり減らすなんて、本当に無駄な疲労ですよね。
私は2TBを入れたおかげで録画やスクリーンショットを気楽に保存でき、安心して遊べました。
この「余裕がある」という気持ちが、何よりの安心につながるんです。
ケースと冷却も甘く見ちゃいけない。
過去に静音性だけを基準にして通気の悪いケースを選び、夏に本体が触れないくらい熱を持ってしまったことがあります。
ゲームを楽しむよりも、パソコンが壊れないか不安で気が気じゃなくなる。
まさに本末転倒でした。
この時の経験から「環境と性能はセットで考えないと意味がない」という教訓を得ました。
冷却は目立たない存在ですが、いわば影の主役です。
軽視すればパーツが本来の力を発揮できずに終わってしまいます。
そして電源。
これをケチるのは致命的です。
私は昔、安物電源を選んで痛い目を見ました。
ある日、盛り上がっていたゲームの真っ只中で突然シャットダウン。
思わず「今かよ!」と叫んでしまいました。
あの理不尽さは二度と味わいたくありません。
後に信頼できる品質の高い電源に替えたところ、システムが嘘みたいに安定して、ようやく落ち着いた使用環境を手に入れることができました。
電源は地味でも、そこが弱いと全部ダメになる。
そういう存在です。
つまり、構成を考える時はグラボを中心に据えながらも、CPUやメモリ、ストレージ、電源、ケース、冷却にバランスよく投資すべきなのです。
昔の私は、本当にグラボさえ良ければ全て解決すると思っていました。
しかし現実はそんなに単純ではない。
パーツの足並みが揃っていなければ、どこかに隙が出て快適さが台無しになります。
経験してようやく理解しました。
だから私は今、同じ道を歩もうとする人には声を大にして伝えたい。
グラボ重視だけの構成は必ず後悔する。
それよりもバランスを選ぶ勇気を持った方がいい、と。
安心感。
信頼性。
この二つこそが、結局は最高の環境を支える土台になります。
すべてのパーツが噛み合った時、パソコンは本当の力を発揮します。
いいグラボを買っても、それ単体では宝の持ち腐れです。
ですが全体を整えれば、ゲームそのものの楽しさが変わってくる。
遊ぶことに全力で集中できて、余計な不安が一切なくなる。
その時の満足感と充実感は、まさにご褒美のような時間なのです。
グラボに注ぐ情熱を大切にしつつも、それを支える土台に手を抜かない。
ここにこそ、本当の快適さを長く楽しむ秘訣があります。
そしてそれを一度味わえば、もう後戻りはできないのです。