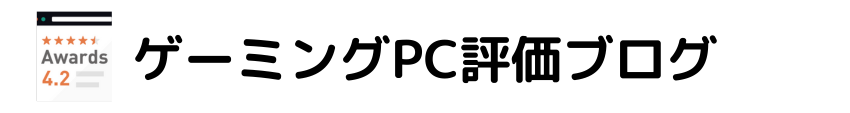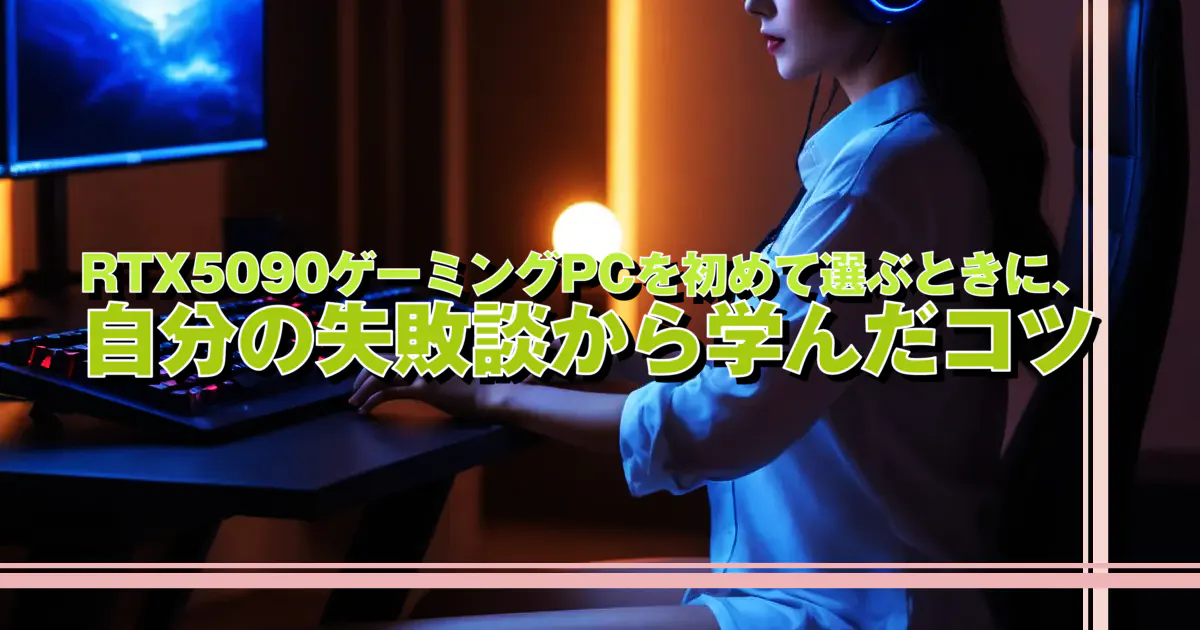RTX5090 搭載ゲーミングPC選びで初心者がつまずきやすかった実体験のポイント
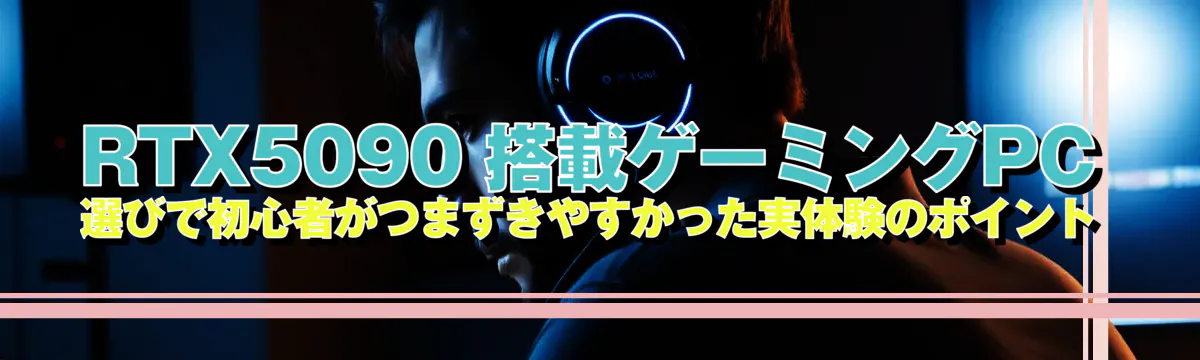
GPUばかり重視してCPUを軽視してしまった失敗体験
最新かつ最強のGPUさえあれば、これからのゲーム体験は一気に快適さを増すに違いないと、自分に言い聞かせるように信じ込んでいたのです。
ところが現実は、そんな甘い予想を冷水で打ち消す結果になり、目の前に突きつけられたのは「GPUだけでは戦えない」という苦い真実でした。
衝撃は、ある新作のオープンワールドゲームを起動したときにやってきました。
期待に胸をふくらませていたのに、GPUの稼働率は思ったほど上がらず、それに引き換えCPUは100%でフル稼働。
画面はカクカクし、遊ぶどころではありません。
「おい、嘘だろ」とつい口に出してしまったほどです。
数十万円のGPUが眠ったまま、宝の持ち腐れ。
金額のことを考えれば考えるほど、心に押し寄せるのは失望と苛立ちでした。
ゲーム体験が理想からかけ離れていくにつれ、自分の判断の甘さが身に沁みました。
私はその時、コストにばかり気を取られていたのです。
普段の用途はリモートワークや資料作成、動画視聴程度。
「まあこれで十分でしょ」と軽く考えたのが正直なところです。
その判断自体は通常の作業においては正解でした。
快適ですらありました。
しかし高フレームレートを求めるゲームになったとたん、シングルスレッド性能の不足が露骨に表れたのです。
私はここで「用途によってCPU要件はまるで違う」という当たり前の事実に、痛みを伴って気づかされるのです。
ゲーミングの主役はグラフィック性能、それは確かです。
けれどステージに立つのが主役一人では芝居がなりません。
主役が輝いても脇を固める役が力不足なら、質が下がる。
そういうことです。
華やかなライトに目を奪われて、舞台設備という基盤を後回しにしていた自分を今でも思い出して苦笑します。
CPUを上位モデルに切り替えた瞬間の体験は、今でも忘れられません。
思い切ってCore Ultra 9を導入した途端、GPUの利用率は90%台に跳ね上がり、フレームレートも驚くほど安定しました。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、その時初めてこのGPUの真価を目にしたのだと感じました。
実は、購入時に店員さんからも「このGPUならCPUも上位モデルにしたほうがいい」とアドバイスを受けていました。
しかし当時の私は聞く耳を持たなかったのです。
「GPUさえ良ければあとは問題ない」という思い込みに完全に支配されていた私は、コストを優先してCPUを妥協しました。
それが結果として余計な出費になり、あとから悔しさと情けなさでいっぱいになったのは言うまでもありません。
痛感したのは、CPUは数値以上に世代や設計思想の違いがパフォーマンスに響くという点です。
クロック数やコア数だけに縛られず、キャッシュやアーキテクチャ全体の作り込みがフレームタイムを左右していました。
そうした背景をまったく理解しないまま、GPUのベンチ結果ばかり追っていた当時の私は浅はかだったのです。
実際の体験を経て初めて、CPUがゲーム体験を「支えている」存在であると学びました。
その後は考え方を切り替えました。
つまり、「自分はどんなプレイスタイルを楽しみたいのか」を出発点にするようになったのです。
競技性の高いFPSならクロック重視、ハイレベルの応答性こそ勝敗を決める。
しかしストーリーメインのRPGで没入感を求めるならGPU中心でよい。
ただしそこでCPUを極端に落とせば、やはり滑らかさが途切れてしまうのです。
だから結局は「全体の設計」を考えない限り、本当の快適性は手に入らないと痛感しました。
ようやく理解しました。
GPUに予算をすべて投じるのではなく、CPUやその他の構成要素まで一貫して見渡す視点こそが必要だったのです。
RTX5090のような怪物級のGPUを引き出すには、それを支えるCPUも同ランクでなければならない。
頭では簡単に言えるこの理屈も、私は自分の財布と時間を使ってようやく納得したのです。
最終的に、GPUとCPUをともに高性能で揃えた結果、はじめて「心から求めていた一台」が完成しました。
その瞬間、私は心の奥で大きな安堵を覚えました。
遠回りをしましたが、その過程で得たものは大きかった。
私の中に「構成哲学」とも呼べる揺るぎない考え方が芽生えたのです。
この経験を通じて私は学びました。
性能は単なる数字やカタログ値で測れないということ。
全体の調和を見ることでしか快適さはやってこないのだということ。
そして最後に、自分にとって本当に必要な体験は何なのか、腹を割って向き合う勇気が求められるということです。
だから今なら言えます。
バランスこそが、真の力です。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42850 | 2438 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42605 | 2244 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41641 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40937 | 2332 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38417 | 2055 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38341 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35491 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35351 | 2210 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33610 | 2184 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32755 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32389 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32279 | 2169 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29124 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 2151 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22983 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22971 | 2069 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20762 | 1839 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19418 | 1916 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17651 | 1796 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15974 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15220 | 1960 | 公式 | 価格 |
電源容量を見誤って不安定になったときの話
RTX5090を搭載した私のゲーミングPCは、今でこそ驚くほど安定して動作していますが、そこにたどり着くまでには痛い失敗と学びの積み重ねがありました。
結局のところ、1500W以上かつ信頼できる品質の電源が必要だったのです。
最初から分かっていれば苦労なんてしなかったのにと、当時の自分に言ってやりたい気持ちです。
最初の組み立てでは「1200Wもあれば十分でしょう」と安直に決めてしまったのが間違いでした。
その時の私は数字だけを追いかけていて、どこかしら自信過剰だったのでしょう。
最新のGPUに高性能なCPU、そして最新規格のSSDまで積んだのに、最後の肝心な電源だけは甘く見ていた。
今思えば自分の浅はかさに苦笑するしかありません。
実際に稼働させ始めてすぐに、その見込みの甘さを突き付けられました。
ようやく落ち着いたと思ったらまた電源が落ちる。
その繰り返し。
あのときは心底参りましたね。
特に記憶に残っているのは、大容量で負荷の重いゲームを2時間ほどプレイしていた時でした。
画面がぷつっと乱れたかと思えば次の瞬間に電源が落ちる。
まるで努力を鼻で笑われたような感覚でした。
やっとの思いで組んだ私のPCが、裏切るように力尽きて消えていく。
もうやってられないよ、という気持ちになりました。
仕事から帰ってようやく落ち着いた夜に、原因解明のために検証を繰り返す。
電源が足りないのではないかと疑いつつも、はっきり断定できない。
あの時間と精神的な疲労感は今でも思い出すと胸が重くなります。
それが一番きつかった。
電源不足の挙動は、普段は問題なく見えても高負荷時に突然崩れるという厄介なものです。
たとえるなら、軽いジョギングはできる中年が急に全力疾走させられて心臓が悲鳴を上げるようなもの。
見た目は元気なのに、いざ負荷が増えた途端に倒れてしまう。
そんな危うさがそこにありました。
この経験から痛烈に学んだのは、カタログスペックの数字を鵜呑みにするのではなく、余裕を持った構成を心がける必要性です。
数字上は問題なさそうでも、余裕がなければいざというときに破綻してしまう。
ギリギリの設計なんて、結局は不安しか生まないんです。
その瞬間、すべてが変わりました。
高負荷のゲームを何時間続けても一度も電源が落ちない。
ベンチマークを夜通し回しても安定している。
もうビクビクする必要はなくなった。
安定性という安心感がこんなに心を軽くするものなのかと、深く実感しました。
さらに、副次的な効果として静音性も向上しました。
以前はゲームの負荷が上がるたびにファンが大きな音を立て、家族にも気を遣うほどだったのですが、余力のある電源に変えてからはファンが静かに回り続ける程度。
夜中に作業しても、落ち着いた環境が保てるのです。
これには本当に救われました。
昔の私なら「電源にそこまで投資する必要があるのか?」と言ったことでしょう。
でも今の私ははっきりと言えます。
RTX5090を本気で動かすなら電源を軽視してはいけない、と。
なぜなら、電源は一度良いものを選べば長く使えるし、将来的に構成をアップグレードする際にもそのまま安心して使えるからです。
表立って目立つパーツではないからといって後回しにしてはいけない。
むしろ地味だからこそ、信頼を置ける選択が欠かせません。
振り返ると、当時の私はパーツ選びのバランス感覚をすっかり欠いていました。
CPUやGPUばかりに情熱を注ぎ、電源はただ「大は小を兼ねる」という安易な発想で済ませてしまった。
正直に言えば、それは怠慢でした。
けれどその失敗がなかったら、PC構成全体において何を優先すべきか、自分の中で本当に理解することはできなかったでしょう。
だから今、これからRTX5090を導入しようと考えている方には心から伝えたいのです。
1500W以上、信頼できるメーカー製の電源を選んでほしいと。
単なる容量の数字合わせではなく、安定性や静音性、安全性を含めて総合的に判断してほしいと。
最終的に得られるのは、ただ数字で表せない心の安心なのです。
もう疑う余地はありません。
電源を妥協すれば、RTX5090の本来の性能を十分に引き出すことは絶対にできない。
最適解はただ一つ。
余裕のある大容量で信頼できる電源を選ぶことです。
それこそが快適で安心できるPCライフの条件だと、私は自信を持って言えるのです。
安心感。
静けさ。
この二つを支えてくれるのが電源の選び方なのだと、ようやく身をもって理解しました。
冷却不足で高温に悩まされたときの体験談
RTX5090を導入して最初にぶつかった壁は、冷却を甘く見てしまったことでした。
後になって考えれば、水冷とエアフローを最優先にするケースを最初から選んでおくべきだったのです。
その油断が、自らの首を絞める数か月を生むことになりました。
ゲームを始めてたった30分ほどでGPU温度は90度近くに達し、リビングにいてもファンの轟音が響いてまるで小規模なサーバールームに閉じ込められているような錯覚を覚えました。
ワクワクするはずの最新カードが、なぜか私の忍耐を試す存在へと姿を変えていたのです。
それなりに自作の経験もあったので自信がありましたが、5090の発熱の恐ろしさは完全に想定外でした。
ケース内のエアフローがわずかにでも偏れば、すぐさま内部が蒸し風呂のようになっていく。
しかもGen.5のSSDを追加で入れたことにより、状況はさらに悪化しました。
あのSSDは正直、想像以上に熱を吐きます。
積み上げてきた期待とは真逆の現実がそこにありました。
未来感どころか、不安と苛立ちの連続。
そして何よりの誤算は、水冷導入への不安でした。
「下手に触って壊したらどうしよう」「高価だから絶対に失敗できない」そんな気持ちに縛られて、挑戦する勇気を持てなかったのです。
その結果、宝の持ち腐れ。
GPUもSSDも本領発揮できず、無駄に時間とストレスだけを重ねることになりました。
なるほど効率化を求めて投資したつもりが、むしろ真逆の非効率を引き起こしていた。
痛恨の失敗です。
応急処置としてやったのは、ファン速を上げたりケースのサイドパネルを外すといった荒っぽい方法でした。
まるで素人仕事で、自分自身に「いやこれは雑すぎるだろ」と突っ込みを入れたくなる有様。
しかし確かに温度は下がるものの、安定性はゼロ。
長時間続けられる状態ではありませんでした。
ケースから風が抜けるのを手で感じても、それは「まともな設計じゃない」という証でしたね。
やがて本格的に手を打たねばならないと観念し、大型ラジエーターを備えた水冷クーラーを導入し、ケースもエアフロー重視モデルに買い替えました。
以前使っていたガラスパネル主体のケースは見た目ばかりは最高。
その反面、冷却性能では完全に失格でした。
振り返って思うのは、私は結局「デザイン重視」の罠にハマっていたということです。
環境を整えてからは世界が変わりました。
GPU温度は70度前後で安定し、ファンの耳障りな騒音からも完全に解放されたのです。
長時間でも静かに作業やプレイができる。
その快適さは、まさに肩の荷が下りたようでした。
安堵しました。
RTX5090を導入する人に伝えたいのは、このカードを扱うなら何より冷却を最優先すべきという事実です。
電源容量も、外観の美しさも大切です。
しかし冷却なしでは快適さは得られません。
Gen.5 SSDや大容量メモリなど最新構成を組むならなおさら、部品単位ではなくケース全体の空気の流れをきちんと考える必要があります。
ここを見誤ると、パーツの性能は半減してしまうのです。
最近流行しているピラーレス構造やガラスパネル主体のケースは、視覚的な美しさと所有欲を満たしてくれます。
それも確かに魅力です。
見た目にこだわりすぎると、RTX5090の真価を台無しにしてしまうのです。
長時間の高負荷運用を前提に考えるなら、投資すべきは冷却経路。
これこそ見えない部分にこそ求められる本当の価値だと、強く言いたいです。
冷却を見直して初めて、5090は本来の力を示しました。
私が学んだ教訓はシンプルです。
冷却に妥協してはいけない。
やるべきは最初から冷却重視のケースを選び、信頼できる水冷クーラーを備えること。
それだけです。
この遠回りは決して誇れるものではないけれど、その分だけ胸に刻まれ、次に活かせる糧となりました。
RTX5090 ゲーミングPCを納得して組むために考えたCPUとメモリの選び方
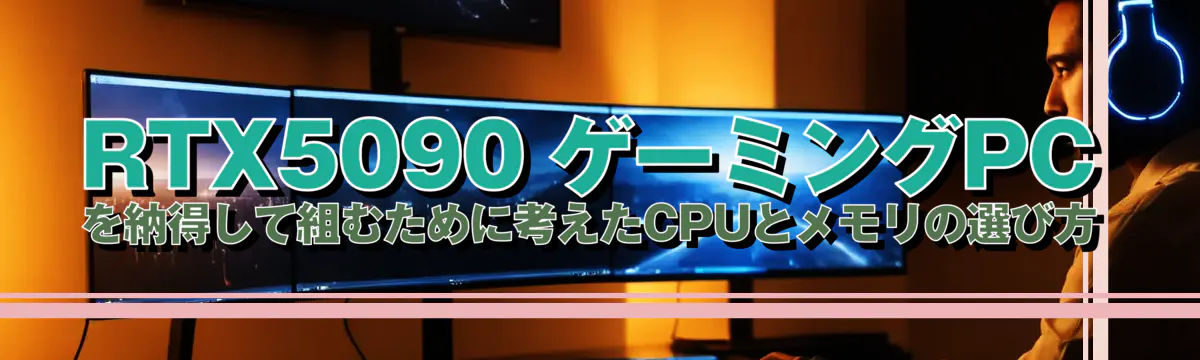
Core UltraとRyzenを実際に使い比べて感じた違い
Core Ultraにするか、それともRyzenにするか。
選び方ひとつでこのGPUが持つ力を存分に引き出せるかどうかが変わってくるのは、経験豊富な方ならご存じの通りです。
私はあえて両方を試しましたが、その体験からはっきりと言えるのは、ゲームに振り切るならCore Ultra、制作や同時並行作業を重視するならRyzenという住み分けがある、という事実でした。
Core Ultraを使ったときの第一印象は、とにかく動作の一貫性が頼もしいということでした。
RTX5090の負荷を全開にしてもフレームレートは期待以上に安定し、最新のFPSも驚くほど機敏に描画してくれる。
その挙動を身近な場面に重ねるなら、大事な会議中に即断を求められたときの反応に似ていて、迷っている余裕などない場面で一歩先を行ける安心感がありました。
この違いはゲームを日常的に楽しむ私にとって、実感できるほど大きかったです。
一方で、Ryzenが見せた力は別の意味で印象的でした。
とくに動画編集や3Dレンダリングなど、複数の工程を同時に回す作業での効率性は感動モノで、数値的な差を超えて実務に直結する快適さを感じました。
夜遅くに息を潜めるように映像を整えているとき、控えめなファンの音と共に黙々と安定動作を続ける姿勢には、本当に助けられました。
静けさの中で思考が整う、そんな感覚を得られたのです。
ただ、Ryzenにも弱みはあります。
GPUの能力を隅々まで発揮する必要がある高フレームレートのゲームタイトルでは、安定性は高くとも動きがわずかに鈍ることがありました。
逆にCore Ultraは単発の処理性能に強く、反応速度が勝敗を左右するゲームでは一歩リードする。
実際にFPSを遊んでいる最中、わずかに早い反応が取れた場面では「この瞬間的な差、確かにCore Ultraだからこそかもしれない」と思わされました。
勝負の世界は残酷です。
そして私には忘れられない失敗の記憶があります。
当初、数字の上だけで判断してCore Ultraを組み合わせたのですが、その構成で動画編集に挑んでみたところ、思った通りの効率を得られなかったのです。
結局はRyzenに組み直す羽目になり、余計な出費で心底悔しい思いをしましたね。
でもその経験がなければ、「自分は本当に何のためにRTX5090を使うのか」を徹底的に考えることはなかったでしょう。
数値やベンチだけに踊らされず、用途に軸を置くこと。
改めて両者を整理すると、Core Ultraは瞬発力、Ryzenは持久力と器用さ。
それぞれが明快なキャラクターを持っています。
私の暮らし方は、日中は会議や資料作りに追われ、夜は趣味の映像編集に少し時間を割く。
そして休日は腰を据えてゲームを遊ぶ。
そう考えると、Ryzenのバランスが自分にとって自然にフィットしたのです。
けれどもし私が毎夜ゲームに全力投球する生活なら、迷わずCore Ultraを選んだでしょう。
結局は使う人の選択です。
私が強く伝えたいのは、RTX5090クラスのGPUを選ぶならCPUを軽視してはいけないということです。
メモリも大事ですし冷却もこだわるべきですが、最後にGPUの力をまとめて受け止められるかどうかはやはりCPUにかかっている。
私は実際に財布を痛めて学んだので、この点は声を大にして言いたい。
RTX5090を真に活かしたいなら、まず自分が何に重点を置くのか。
その整理から始めるべきです。
方向を間違えたら、後悔するだけになります。
私が味わったモヤモヤや失敗談は、これから導入を考える人にとって必ずヒントになると思います。
Core UltraもRyzenも間違いなく素晴らしいCPUですが、万能ではありません。
だからこそ目的と生活スタイルに合わせて選ぶ必要がある。
そう強く思います。
安心感。
この二つをどう求めるかで、最適な選択肢は変わるのです。
私自身が学び取った結論はシンプルでした。
CPUを選ぶという行為はRTX5090を所有する喜びの基盤を作るものであり、それを軽んじると毎日の満足度に直結してしまう。
DDR5メモリは32GBで大丈夫か、それとも64GBにして安心できたか
ゲームだけであれば32GBで十分機能しましたし、当初は「これで数年は大丈夫だろう」と高を括っていたのも事実です。
ところが現実はそう甘くはありませんでした。
配信ソフトを立ち上げながら重たいゲームを同時進行すると、明らかに余裕がなくなる。
これが日常的になってしまうと、せっかく高価なGPUを入れても楽しめない。
そんな痛い経験を通して、私は64GBこそ今の時代にふさわしい選択だと腹落ちしたのです。
最初に32GBにした時は、本当に満足していました。
最新の4Kゲームを最高設定で回しても滑らかで、不満らしい不満はなかったのです。
でも一度配信を試してみると、裏で動いているソフトがガクガクし始める。
メモリ使用率を確認すれば常に頭打ち。
あの時は正直「しまった…」と声が出ました。
パソコンのスペックというのはカタログ値だけでは分からない。
実際に自分の生活に入り込んで、ストレスなく動いて初めて安心できるものなんですよ。
高性能なRTX5090を搭載しているのに、メモリ不足で全力が出せない。
これほどもったいない話はありません。
高級車に安いタイヤを履かせるようなもので、理屈では走れるけど安心はできないのです。
そんなアンバランスさに気づいた時、私は「これは投資を惜しむべきじゃない」と考え直しました。
64GBに増設してからの快適さは衝撃でした。
After Effectsとゲームを同時に開いても反応は軽く、OBSが落ちるストレスもなくなった。
何を開いても「間に合ってますよ」と言わんばかりにサクサク動く。
小さなことですが、この余裕感が気持ちをどれだけ支えてくれるか。
広い会議室をひとりで使っているような、贅沢で落ち着く安心感がありました。
精神面の違いも大きいです。
「これ以上タブを開いたら危ないかも」と不安になる必要がなくなった瞬間、挑戦できる範囲が一気に広がりました。
配信しながら横で動画をレンダリングし、それと同時にブラウザで調べ物をしてもへこたれない。
そんな頼もしい環境は、日常の自信に直結します。
安くはありません。
32GBとの差額は決して小さくない。
GPUだけ一流で足回りが二流では、全体の価値を殺してしまいます。
だから私は思い切って揃えるべきだと判断しました。
無用の贅沢ではなく、性能をきちんと引き出すための必然です。
実際、Chromeを複数タブ立ち上げながらレイトレーシングONでゲームをすると、32GBではもたつきが気になりました。
64GBに変えてからは、その不快感が消えた。
快適そのもの。
人間って不思議なもので、一度余裕を知るともう狭さには耐えられないですね。
笑うしかないけれど、「もっと早く増設しておけばよかった」と今でも思います。
初期費用をケチって結局モヤモヤし続ける、その典型でした。
ゲームも配信も、さらにはこれから登場する生成AIアプリやさらに重たい映像ソフトと向き合うなら、64GBは必ず支えてくれると実感しています。
であれば、その先を見据えて64GBを確保しておくのは、決して過剰ではありません。
未来への安心投資みたいなものです。
私は、かつて16GBが一気に主流化していく過程を見てきました。
だから余計に分かります。
32GBから64GBへの移行が始まっているのも、同じ流れなのだと。
長く安定した環境を求めるなら、その判断を迷う必要はないはずです。
私自身「そこまでいるのか」と最初は半信半疑でした。
しかし増設してからはパソコンとの距離感がまるで違う。
用途を制限せずに、やりたいことを全部突っ込んでも動いてくれる。
その度に心の底から「これで良かった」と思えます。
この構成なら、RTX5090が本来の力を存分に発揮し、毎日の作業も遊びも支えてくれる。
もう迷いはありません。
安心感。
この二文字こそが、64GBがもたらした最大の価値でした。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BW

| 【ZEFT Z55BW スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BU
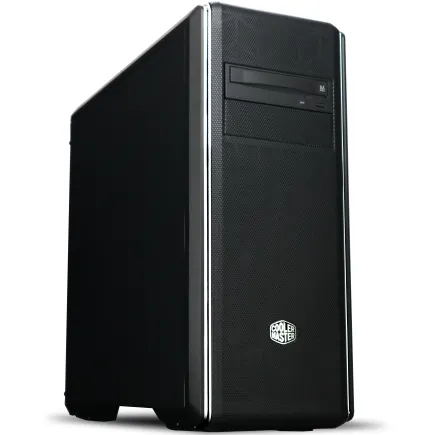
| 【ZEFT Z55BU スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
| ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | ブルーレイスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60V

| 【ZEFT R60V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASUS製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | ブルーレイスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GY

| 【ZEFT Z55GY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GA

| 【ZEFT Z55GA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6800Gbps Crucial製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
CPUとメモリの組み合わせで安定性を実感できたケース
ところが実際に使ってみると、CPUやメモリが追いつかないせいでせっかくのGPUが十分に働いてくれない。
最初は「まぁこんなものなのかな」と思っていましたが、使用時間が長くなるほど小さな引っ掛かりやフレームの乱れが表面化してきて、その違和感が日に日に気になるようになりました。
こういう経験を通じて悟ったのは、結局のところCPUとメモリの組み合わせが堅固であることこそが、RTX5090を生かすための条件だということです。
片方でも手を抜けば、高負荷時に結果は如実に表れます。
私が思い切って構成を見直したのはRyzen 9000シリーズを導入し、さらにメモリを32GBから64GBに増設した時でした。
その効果は正直、あまりに劇的すぎて笑ってしまうほどでした。
高リフレッシュレート環境でもフレームは安定し、ゲーム全体が息を吹き返したように滑らかに動くようになりました。
「今までの苛立ちは何だったのか」と呟いたのを覚えています。
以前Ryzenの旧世代を使っていた頃は、本当にGPUとCPUの噛み合わせが悪くて「GPUが余ってるな」と感じる場面ばかり。
あの時のもどかしさといったら、今振り返っても苦い思い出です。
言葉で説明すると軽く聞こえるかもしれませんが、まさに「もう別物」と言っていい変化でした。
ただ、私はIntel Core Ultra 7も試す機会を得て、その時にも驚きを覚えました。
シングルスレッド性能の高さが効いていて、RTX5090とのかみ合わせはとても良好だったのです。
でも最終的に私がAMDを選んだのは、挙動が自分のスタイルに合っていたからです。
ここはもう数字だけでは測れない部分で、完全に好みの問題だと感じます。
それでもし同じように迷う人がいたら、私はCPUの選別よりもまずメモリを64GBにすることを勧めます。
それだけで体感は大きく変わりますから。
特にシミュレーション系を数時間遊んだ時にその差がはっきりと現れました。
以前はちょっとしたロードの遅さにうんざりしていましたが、アップデート後は全くの別世界。
重いマップを展開してもスムーズで、描画遅延が消え去る快感を味わえました。
正直、感動した。
そして配信も試してみたのですが、64GBへの拡張後は録画や4K配信をしながらのプレイにも全く支障がなくなりました。
実はそれまで私は「回線が悪いせいで映像が引っかかるんだろう」と思い込んでいて、原因がメモリ不足だと気づいた時は、もう自分に苦笑いするしかありませんでしたね。
でもその学びのおかげで、やっとRTX5090の真価を引き出す土台を整えることができたと自信を持てるのです。
それにしても、最近のAAAタイトルは要求がどんどん大きくなっています。
だからこそRTX5090を選ぶ人には、CPUも最新世代のハイエンドクラスを、そしてメモリを64GBは確保することを真剣におすすめします。
ここに高速SSDを組み合わせれば、日常的な使用で不満を覚えることはほぼゼロと言っていいと感じます。
まさにこれが安定の鍵。
つまり、RTX5090を十分に使い切りたいなら、CPUは確実に高性能帯を選び、メモリは最低でも64GB。
32GBでは中途半端で、いざという時に足かせになってしまうのです。
私は試行錯誤を繰り返してその答えに辿り着きました。
安心感が違う。
私にとってこの学びは、単なるPC構成の話ではなく、自分の判断を問い直す良い機会になりました。
RTX5090 ゲーミングPCを快適に使えたストレージとケース選びの工夫
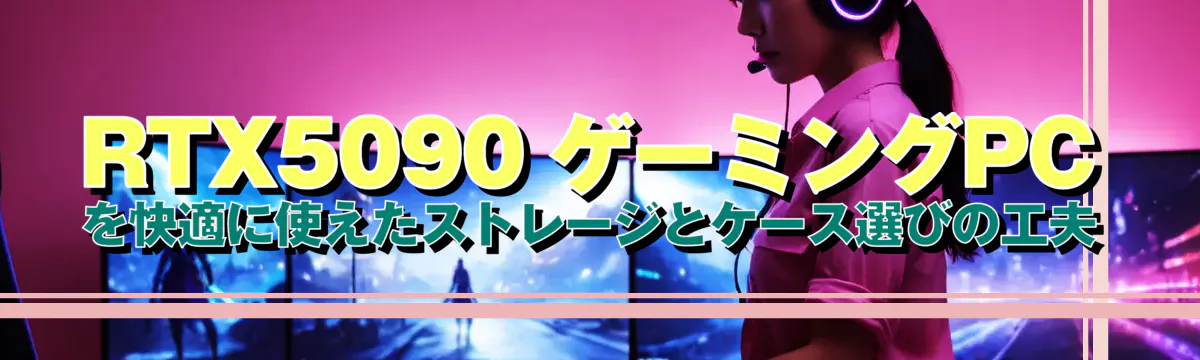
Gen4 SSDで十分と感じた場面、Gen5を選んでよかった場面
日常的なゲーム用途ではほとんどの場合Gen4で困らないどころか、むしろ快適そのものということが多いです。
実際に遊んでいるとロード時間の数秒差など気にもならず、集中してプレイしていれば体感的な差はほとんど存在しないと言っていい。
結局のところ、プレイ体験を左右するのは自分の腕前や物語への没入感で、SSDの世代差がゲームそのものの楽しさを奪うわけではないのです。
特にRTX5090搭載の環境ではGPUの性能が支配的で、正直なところストレージの違いを意識する場面はほとんどありませんでした。
だからこそ、心のどこかで「Gen4でよかったな」と思わされる瞬間が少なくないのです。
しかし仕事となると話は一変します。
動画編集やVR制作のように膨大なデータを扱う中では、Gen5の速度が確実に効いてくる。
数百GB単位の素材をコピーする際、Gen4だと気付かぬうちに作業リズムが崩れ、苛立ちが募っていきました。
特に8Kの映像レンダリングでは、キャッシュ処理の高速化を体で感じられ、投資の意味を深く理解できました。
あのとき「やっと環境が追いついた」と思ったものです。
とはいえGen5には難点もあります。
発熱の高さです。
私も導入直後に空気の流れを甘く見てしまい、ケース内部の温度が昼間のオフィスのようにじわじわ上がり、不安で仕方がない時期がありました。
発熱対策は本当に重要です。
ヒートシンクを追加し、ケースの見直しまで行い、試行錯誤の末にようやく落ち着けたとき、心底ほっとしました。
だから今なら強く言えます。
Gen5を導入するなら冷却対策と必ずセットで考えるべきです。
後でやると間違いなく後悔しますからね。
面白いもので、人間の感覚というのは本当に順応してしまう。
初めてGen5環境でAAA級ゲームをプレイしたときは、あまりのロードの速さに「おいおい、何だこれは」と笑ってしまうほど驚きました。
けれど数日後、同じゲームをGen4でプレイすると「まあ、これで十分だろう」と自然に思えてしまった。
数値的な違いは確かにあるのに、自分の体は意外なほどすぐ慣れてしまうのです。
要は、人間の慣れの方が勝つこともあるという事実。
そこに妙なリアリティを感じました。
ただし動画編集の現場では、慣れでごまかせる差ではありませんでした。
何時間にも及ぶ作業をこなす中で、エンコードそのものは時間短縮されないものの、キャッシュの動作が早いおかげで待ち時間が大きく減り、集中が途切れなくなった。
プレビューを確認するたびに長く待たされることがなく、テンポよく編集を続けられるようになったのです。
その結果、作業能率は驚くほど改善され、思わず机に向かいながら「これなら続けられる」と声が漏れました。
そして避けて通れないのが価格です。
Gen5は依然として高価で、全てをそれで統一するとなると財布への負担は無視できません。
さらに冷却強化や電力消費といった付随コストもついてきます。
私は最終的に、システムドライブにGen5を採用し、それ以外のゲームや日常データ領域はGen4に任せる構成に落ち着きました。
この組み合わせは性能とコストのバランスがよく、心理的にも納得できる選択です。
やみくもに最新だけを追うのではなく、自分の用途に応じた折り合いをつけることこそが正解でした。
思い返せば最初にPCを組むとき、勢いでGen5を選んだのですが、普段の利用では宝の持ち腐れのように感じて後悔した時期がありました。
日常と仕事、快適さと効率。
その両立をどう取るかを考えるのは、大人の楽しみの一つかもしれません。
私にとっては今の構成こそが最善だと信じています。
ゲームに関してはGen4があれば十分。
しかし仕事の場面ではGen5こそが力を発揮する。
この線引きがあるからこそ高価な投資をしても悔いが残らないのです。
もちろん、人によってはゲームも含めてすべてGen4で構わないでしょうし、その選択は決して間違いではありません。
私が言いたいのは、自分の用途に合わせて冷静に判断すべきだということです。
安心できる構成こそが最終的な満足度を生む。
これが私の答えです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
静音性と冷却のバランスを重視して選んだケースの話
RTX5090を搭載したゲーミングPCを組むとき、正直私が一番頭を悩ませたのはケースでした。
性能が高いGPUを最大限に活かそうと思えば当然冷却が最優先になるわけですが、同じ場所で仕事もする私にとっては静音性も無視できない。
冷却と静音、この二つをどう両立させるのかが壁になっていました。
最終的には「冷却を優先、そのうえで静音性を整える」という考え方に落ち着きましたが、その判断に至るまでには失敗と学びを繰り返しました。
冷静に振り返ってみると、これは自分の経験としてきちんと伝えたいですね。
実際、かつて私は見た目にほれ込んでケースを選んだことがあります。
重厚感あるデザインに加えて分厚い遮音パネルがついていたので、これなら静かに動くと信じ切っていました。
ところが、いざ長時間ゲームを続けるとGPU温度があっという間に高騰し、90度近くまで上がってしまったんです。
あのときの「やってしまった」という後悔の気持ちは忘れられません。
機械が止まるかもしれない恐怖と、選択を誤った不甲斐なさ。
背筋に冷たいものが走った瞬間でした。
その経験を経て再度ケースを探し直し、私はフロントとサイドが大きくメッシュ加工されたモデルに行き着きました。
通気性をしっかり確保しつつ、要所には遮音材が仕込まれていて音の高周波成分だけをうまく抑えてくれる構造。
これを使ってみて気づいたのは「抜けのいいエアフローのほうが静かになる」という意外な事実でした。
温度が下がればファンが無駄に回らない。
その効果は私の予想以上でした。
ここに来てやっと「冷却と静音は敵対する概念ではなく、実は順序立てて工夫すれば両立する」という確信を得られたのです。
RTX5090はサイズも重量も桁違い。
補強ブラケットやライザーケーブルが必要になることもあるし、ケーブルマネジメントが難しいケースでは作業のたびにストレスを抱えることになります。
現在使っているケースは裏配線用のスペースがしっかり確保されており、不要なストレージベイを外せる構造でした。
その柔軟性のおかげで、大型水冷ラジエーターを追加したときも取り回しに困ることはありませんでした。
剛性についても触れないわけにはいきません。
安価なケースにありがちな薄いパネルは、押せばペコペコとへこみ、ちょっとした振動でも不快な音を響かせます。
ところが、しっかりしたフレームのケースは違いました。
机の下に置いたときに伝わってくる安定感、稼働中でも揺すられない静けさ、これがどれほどの安心感につながるかは実際に使わないとわからないと思います。
私はこの堅牢なケースを導入してから「静音=遮音」だけではないことを実感しましたね。
さらに私はファン構成にも強いこだわりを持ちました。
付属のファンをそのまま使うのではなく、自分で選んだ静圧重視モデルをフロントに、静音性で定評あるファンをリアやトップに配置しました。
それだけで冷却効率が大幅に向上し、無理に回転数を上げなくても十分に安定した冷却環境を確保できました。
その結果を見たときの「ここまで変わるのか」という驚きは、忘れがたいものです。
実際、この環境で8時間以上の長時間プレイをしてもGPU温度は75度前後に収まりました。
以前のトラウマのような恐怖は影も形もなく、雑音を意識せずに没頭できる。
泣けるほど快適でした。
冷却を優先した判断は正しかった、心からそう確信しました。
そうはいっても、ケースにはデザインの魅力もありますよね。
最近は木製パネルを用いた、家具のように部屋になじむケースも増えてきました。
リビングに置いても違和感がない落ち着いた雰囲気は大きな魅力です。
ただ現状、RTX5090を使用する私にとっては冷却性能が第一。
正直なところ、次の世代でGPUの発熱が抑えられるなら、そのときこそ木製ケースに挑戦してインテリア性を満喫したいと思っています。
大切なのは選び方の順番だと今でははっきり言えます。
冷却性能を最優先に考え、そのうえで静音性を工夫する。
そして整備性や剛性といった基本性能をきちんと評価する。
これを守れば、大きな失敗は避けられる。
言い換えるなら、派手な見た目や広告文句に振り回されるのではなく、自分の用途を具体的に思い描くこと、それだけなんです。
安心感。
信頼感。
最終的に振り返ると、私がPCケース選びを通じて手に入れたのはこの二つでした。
結局のところ、ケース選びも仕事や人生と同じで「基本を見失わない」ことが一番大切なのだと、私は強く実感しています。










デザインだけでケースを決めて後悔したときの記録
正直に言うと、私はパソコンケース選びで派手に失敗をしました。
RTX5090を使ったゲーミングPCを組んだ時のことです。
強化ガラスの側面や洒落た木目調のパネルが目に入った瞬間、仕事帰りにデスクでその輝く姿を見る自分を想像し、衝動的に決めてしまいました。
その結果が、後に苦い後悔へとつながることになりました。
RTX5090は性能が飛び抜けている分、発熱も相当でした。
しかし私が選んだケースは完全にデザイン偏重で、吸気スペースが狭く、取り付けられるファンも限られていました。
高負荷のゲームを始めると一気に温度が跳ね上がり、GPUがサーマルスロットリングを起こして性能を落とす始末。
本来なら快適さを楽しむための投資だったはずなのに、自らその力を封じ込めてしまったのです。
この時は「なんでこんな大事なことを見落としたんだ」と、思わず机を叩きました。
さらに私を困らせたのは、その先に改善の余地がほとんどなかったことです。
大型の空冷クーラーは物理的に収まらず、水冷クーラーのラジエーターはサイズが合わない。
RTX5090そのものも大型なので、内部レイアウトと噛み合わなければ完全に詰みの状態です。
呆れて笑うしかない、そんな気分でした。
私の日課は夜に少しゲームをしてリフレッシュすることでした。
しかし現実には、PCが熱を持ち轟音を立てることで落ち着かない時間に変わりました。
「高級スポーツカーを納車したのに、渋滞しか走れない」。
そんな表現がぴったりの状態です。
贅沢なはずなのに、不満と苛立ちが募るばかり。
これは本当にストレスでした。
私は覚悟を決めてケースを買い換えました。
次に選んだのは、フロントがメッシュ仕様でエアフローがしっかり計算された大型ケースです。
ファンも自由に増設でき、240mmや360mmのラジエーターも問題なく収まる。
ストレージを増やしても余裕があり、組み込み時の作業もしやすい設計でした。
最初からこれを選んでいれば、余計な出費も時間の浪費もなかったのに。
自分に「なぜもっと調べなかった」と言いたい気持ちでした。
面白かったのは、実用性を重視したこのケースでも、デザインへの満足感がむしろ高まったことです。
内部のRGBライティングがメッシュ越しに柔らかく映り、派手さよりも落ち着きのある雰囲気を演出してくれます。
冷却性能が十分に確保されているという安心感があるからこそ、その見た目を本当に楽しめる。
つまり実用性の裏付けがあって初めてデザインも輝くのだと、この時実感しました。
ここから言えるのは明快です。
ハイエンドのGPUを支えるには、ケース選びではまず冷却を最優先にすべきだということ。
見た目にこだわるのは悪くありませんが、それだけでは性能を引き出せません。
むしろ宝を持ち腐れにするだけです。
冷却性能を備えたケースを軸に選び、その上で自分の好みに合うデザインを考える。
それが正しい順番なのです。
そう考えるようになってから、私はケースを単なる「箱」とは見なくなりました。
RTX5090はゲームだけでなく、AI処理や動画編集といった長時間の高負荷作業でも全力で動かす存在です。
そのため、冷却の見通しが立つことは安心に直結します。
この「悩まないで済む」状態は、思った以上に大きな価値がありました。
余計な不安に振り回されずに、やりたいことに集中できる。
これは精神的に大きな違いになります。
外見だけを追いかけても、実用性が伴わなければ後で必ず苦労するということです。
興味や憧れに流されやすい気持ちは誰にでもあると思いますが、それだけでは足りません。
私はその失敗をすることでようやく冷静になり、ケース選びの本当の意味を知ることができました。
これから自作をする方に伝えたいことがあります。
一見地味に思える部分ですが、実際に使っていればその違いに嫌でも気づくはずです。
私は痛い出費をした分だけ、このことを身をもって理解しました。
最初から正しい順番に気づいていたらと考えることもありますが、40代の今だからこそ失敗を笑って話せるのかもしれません。
経験のおかげで、自信を持って「ケース選びは冷却重視」と人に伝えられます。
落ち着き。
信頼できる機材。
これが私の到達した結論です。
RTX5090の性能を余すことなく楽しむには、冷却性能を支えるケースを選び、その上でデザインも楽しむ。
そうすれば長く安心してPCライフを満喫できます。
RTX5090 ゲーミングPCを長持ちさせるために冷却と電源で気づいたこと
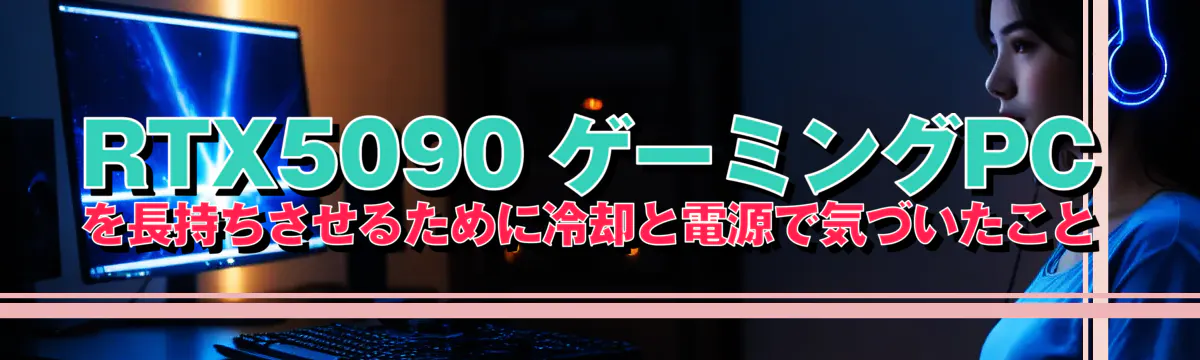
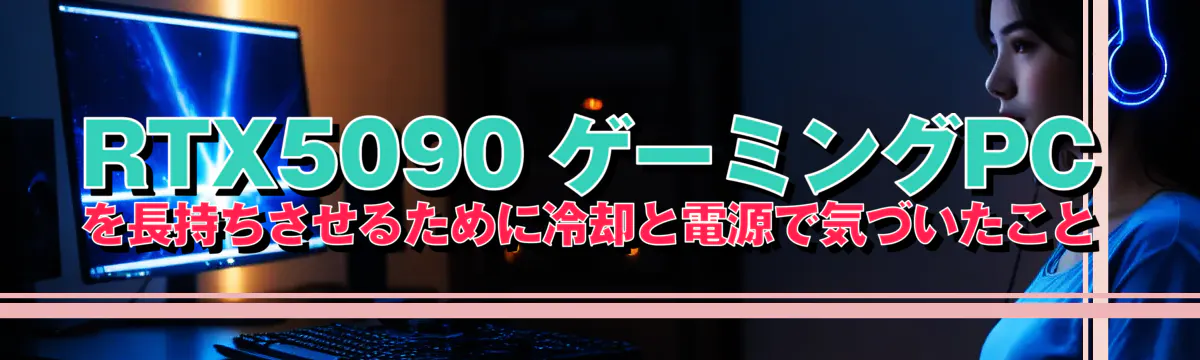
空冷と水冷を自分の環境に合わせて選んだ理由
私が冷却方式として最終的に選んだのは空冷です。
水冷の高い性能を一度は体験しましたし、その力強さもよく理解しています。
GPUを全力で回すようなシーンはあるにはありますが、それが毎日ではありません。
むしろ日常で大事なのは、いつでも安心して使えるということ。
そして余計な心配を抱かず、落ち着いた気持ちで使い続けられることだったのです。
RTX5090を導入した最初の頃は、不覚にも浮かれていました。
あまりに高性能で、これさえあればすべて快適になると信じ込んでいたのです。
しかし現実は甘くなく、熱の厳しさに直面しました。
本当に、小型ストーブを部屋に持ち込んだかのような暑さでしたね。
せっかくのパワーに浸るどころか、先に悩まされたのは熱対策。
そこで水冷を導入しました。
当時の私は、それしかないと心の底から思い込んでいたのです。
確かに水冷を設置した直後は驚くほど静かで、GPUを100%回してもびくともしませんでした。
ところが半年も経たないうちに状況は変わりました。
ポンプの小さなノイズが耳について離れなくなり、休日の数時間をメンテナンスに費やす週末も増えました。
やることが山積みの40代にとって、それは致命的な負担でした。
「あぁ、自分には合わないな」と気づいたのはこの頃です。
正直、気持ち的にも爽やかさどころか疲労感ばかり。
その後、思い切って空冷に戻したときには、本当にほっとしたんです。
最新の空冷クーラーは予想以上に静かで、冷却性能も十分実用的でした。
特にCore Ultra系やRyzen 9000シリーズに切り替えてからは発熱が抑えられるようになり、RTX5090との組み合わせでも安定しています。
手入れはといえば、気が向いたときに埃をとる程度。
不必要に時間を奪われないシンプルさが、私には何よりありがたかった。
気楽さこそ宝だと感じました。
冷却のためにピリピリして、大切な時間を削っていたころの自分を振り返ると、苦笑いしてしまいます。
CPUやGPUの温度の数字を追いかけ、上がれば一喜一憂し、下がれば安堵する。
それって、完全に温度に振り回されていたんですよね。
冷静になって考えれば、ケース内のエアフローを工夫すれば空冷でも十分冷やせますし、回転数の調整次第で静音性も申し分ないのです。
数字のために快適さを犠牲にするなんて、今思えば本当に愚かでした。
あの頃の自分へ一言、落ち着けと言いたいですよ。
ケース選びも冷却には直結します。
今使っているケースはサイドから中が見える大型タイプですが、これは見た目だけで選んだはずが、思わぬ正解でした。
内部の空気の流れがよく計算されていて、空冷のポテンシャルをしっかり活かせるのです。
昔はハイエンドGPUを入れるとケース内に熱がこもり、他のパーツにまで負担をかけがちでした。
それが今ではデザイン性と機能性が両立していて、本当に助けられています。
まさか見た目重視で選んだケースがここまで快適につながるとは当時の自分も想像していませんでした。
長時間の配信やAI処理を回し続けるような場面では、やはり水冷の強みは際立ちます。
ピーク温度を一気に抑え込む力も確かで、実際にBTOの水冷モデルを試した時の冷却余裕は「さすが」でした。
ただその恩恵を享受するには、定期メンテナンスやポンプの経年劣化への対処など、手間をいとわない前提が欠かせません。
性能を優先しても構わないスタンスを持てる人なら選んで良い。
ただ私には合わなかった、というだけの話です。
重要なのは自分の軸をどこに置くかです。
RTX5090を何時間も回して限界パフォーマンスを楽しみたいのか、それとも日常的に安定した状態で長く快適に使いたいのか。
この軸を曖昧にしたまま進めてしまうと、冷却方式の選択で必ずつまずきます。
私は性能ばかりを追って、自分の生活スタイルと照らし合わせる視点を欠いてしまっていました。
その盲目さが、余計な遠回りを生んだと実感しています。
小さな音が精神的な疲れを生むこともあれば、メンテナンスで予定を狂わされることもある。
私の場合は静かで安定した動作を優先し、結果的に心地よい環境を手に入れました。
落ち着きこそ答えです。
最高性能を追うのか、それとも穏やかに長く使うのか。
それが見えれば自ずと答えは出ます。
そう選んで良かったと、心から言えます。
最後に残るのは、自分に無理のないやり方こそが正解なのだ、という確信です。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RD


| 【ZEFT R60RD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HK


| 【ZEFT Z55HK スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GY


| 【ZEFT Z55GY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GJ


| 【ZEFT R60GJ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6800Gbps Crucial製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GW


| 【ZEFT Z55GW スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ ASUS製 水冷CPUクーラー ROG LC III 360 ARGB LCD |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
電源は850W以上が必要かどうか、実際に判断した基準
RTX5090を導入する際に、私は最終的に1000Wクラスの電源を選びました。
最初は850Wでも十分だろうと踏んでいましたが、実際にテストをしてみたときにシステムが突然落ちるという予想外のトラブルに直面し、考えを改めました。
あの瞬間の冷や汗は今も忘れられません。
パソコンの前で「あれ、なんで?」と声が出てしまうあの感覚。
仕事や遊びの集中した時間が突然途切れるあの恐怖は、もう二度と味わいたくないと思いましたね。
判断の基準はシンプルでした。
GPUとCPUの最大消費電力を合算し、更に150Wから200Wほど余裕をもたせる。
そのくらいの考え方が必要なのだと痛感しました。
実際にRTX5090とCore Ultra 9 285Kを揃えると、その時点で700Wを超える計算になります。
実体験を通じて、余裕のなさがどれほど危ういかを学んだのです。
1000Wの電源に切り替えてからは、長時間のベンチマークでも落ちることはなく、安心して使えるようになりました。
肩の力を抜いてパソコンを扱えるというだけで、こんなに作業効率や気持ちの余裕が変わるのかと驚いています。
「多少余っている」ことが、むしろ最大の快適さに直結するわけです。
私の年齢になって実感するのは、リスクを無視して突っ込むより、備えて余裕を残すことの大切さです。
若い頃なら勢いでどうにかするしかなかったですが、今は違います。
準備こそが安心を生むと分かりました。
正直に打ち明ければ、私も最初はGPUさえ強力なら他は問題ないと考えていました。
パソコンの電源を甘く見てはいけない。
私はそれなりに自作歴もありましたが、この件は心に刻み込まれる出来事になりました。
そしてもう一つ重要だと気づいたのは、将来を見据えることです。
メモリを64GBに増設する、SSDを追加する、あるいは冷却装置を強化する。
そのたびに電源ユニットを買い替えるのは経済的にも非効率で、無駄な作業を繰り返すことにもなる。
だからこそ最初の段階で余裕ある電源を導入することが、結局は長い目で見たコスト削減につながるのです。
これは仕事と重なる感覚です。
短期的なコストカットに見えても、結局後から高くつくことがある。
だからこそ初期投資を惜しまない姿勢が必要なんです。
BTOメーカーのラインナップを見ても「RTX5090+850W電源」という構成が普通に売られています。
その度に「これで本当に大丈夫か」と首をかしげます。
カタログの数字だけでは語れない部分がある。
自分のスタイルに合わせて必要な余裕を見極める力が、最終的な安定をつくる。
私は一度失敗したからこそ、今では同じ後悔を二度としたくないと強く感じています。
たとえるなら、高性能なEVに容量の小さいバッテリーを積んで遠距離ドライブに出るようなものです。
最初はいいですが、心のどこかで「いつ止まるか」という不安を抱え続けることになる。
それでは旅を楽しむどころか、常に計算しながらの緊張感ある運転になってしまう。
余裕のある電源を選ぶということは、そのまま「気持ちに余裕を与える」行為なんです。
だから私は声を大にしてここを強調したいですね。
もちろん1000Wが必ずしも万人にとっての正解ではありません。
構成内容や使い方次第では、850Wでも安定するケースは存在します。
しかしRTX5090のような高性能GPUを本気で活用しようと思うなら、妥協しない方が良い。
それが私の結論です。
私がPC構築を通して強く感じたのは「信頼できる土台があるかどうか」です。
結局どんなに性能の高いGPUやCPUを用意しても、根本を支えるのは電源です。
性能だけを追うのではなく、安定性まで含めてバランスを取ることが、本当の快適さなんだと気づけました。
経験としては大きな収穫です。
だから最終的に私がたどり着いた答えは「RTX5090を最大限活かすなら1000W一択」というものです。
差はただの数字に見えるかもしれません。
しかしその余裕が生むのは、日常の中で確かに感じ取れる安定感です。
この違いは、実際に体験してみなければ伝わりにくいのかもしれませんが、私は迷わず言い切れます。
選ぶべきは、余裕のある電源。
そこにこそ本当に価値のある投資があるのです。
安心できる選択。
電源や冷却を軽く考えて起きてしまったトラブル
RTX5090を積んでゲーミングPCを自作したときに痛感したのは、見た目のスペックや派手さに目を奪われがちだけれど、本当に大事なのは土台を支える電源と冷却なんだということでした。
いくら高性能なパーツを詰め込んでも、それらを安定して動かす環境が整っていなければ何の意味もない。
これは言葉ではわかっていたつもりでしたが、実際に自分でやってみて、しかも失敗して初めて身に沁みるものだと心底思いました。
最初に痛い目を見たのは電源でした。
スペックをざっと確認して「まあ750Wもあれば十分じゃないの?」と軽く考えてしまったんです。
40代にもなって、経験も積んできたつもりで、まるで初心者みたいな選び方をしてしまった。
ゲームを起動して負荷が少し上がると、音もなくプツンと電源が落ちる。
最初はソフトの不具合だろうと楽観していた私も、何度も同じ現象が続くと冷や汗が止まらなくなりました。
調べていくうちに判明した事実は、RTX5090が瞬間的に要求する電力に、選んだ電源が耐え切れていなかったということ。
正直、かなり恥ずかしかったです。
80PLUS認証が付いているから大丈夫だろうと安易に判断したのも痛恨のミスでした。
認証があることと、実際に安定した電力を供給できることは全然別の話なんですよね。
結局、メーカーごとの設計やコストのかけ方がものを言うわけで、その差が今回如実に出ました。
自分自身「もうちょっと考えて選んでおけばよかった」と後悔するばかりでした。
本当に悔しい経験だったんです。
次の落とし穴は冷却でした。
ケースに初めから付属していたファンが3基あったので、「まあこれでいけるだろう」と根拠のない自信を持ってしまった。
ところが数時間プレイしたらGPUの温度が90度近くに達し、サーマルスロットリングが発生。
クロックはガクンと下がり、明らかにフレームレートが落ち続ける。
画面に表示されるベンチマークの数値がどんどん下がっていくのを見て、思わず頭を抱えました。
熱。
これが恐ろしいほどの敵でした。
さらにGPUの近くに補助ファンを設置するなど、試行錯誤を繰り返しました。
するとどうでしょう。
GPUの温度が安定して高負荷時でも80度前後で収まるようになり、PC全体の挙動が驚くほど滑らかになったのです。
あの不安定な挙動に悩まされていた自分が嘘のように、今は落ち着いてゲームに集中できるようになりました。
努力が報われる瞬間でした。
やはり電源と冷却を甘く見てはいけない。
そう強く断言します。
RTX5090のようなハイエンドGPUを使うならば、1000Wクラスの余裕のある電源は必須だと思います。
そして冷却設計も、ただファンを増やすだけではなく、吸気と排気の流れを意識したバランスが不可欠です。
ここに投資を惜しまなかった人は、後々のトラブルを大幅に減らせるし、不安を抱えながら使うストレスからも解放されます。
逆に、ケチってしまえば必ず後で倍以上の出費や手間となって返ってきます。
実際、よく利用しているBTOショップでも、電源をひとつ上のランクに上げるのに数千円程度しか差がなかったりします。
その程度の違いで得られる安定感を考えれば、削る理由なんて本当にありません。
昔の自分なら「その金額で別のパーツを強化しよう」と考えていたでしょう。
でも今の私は違います。
安定して長く使えるという安心の方が、心から価値があると感じるからです。
思い返せば、10年前くらいのグラフィックボードならここまで神経を尖らせる必要はありませんでした。
しかし今のハイエンドGPUは桁違いです。
要求される電力も熱の発生量も格段に大きく、冷却と電源の甘さは致命的不具合へと直結します。
だからこそ、電源と冷却の選び方次第で快適なPC体験になるか、ストレスまみれになるかが決まってしまうと言っても過言ではありません。
だから私は声を大にして言いたい。
RTX5090を扱うなら、電源と冷却を絶対に妥協してはいけない、と。
少しくらいオーバースペックかなと思うくらいでも、長期的に見れば確実に報われます。
その安心感は何物にも代えられませんし、ゲームを楽しむ時間が本当の意味で自由になります。
結局のところ、RTX5090を全力で楽しみたければ電源と冷却にしっかり投資するしかない。
それがあって初めて、性能を余すことなく発揮し、安定動作という土台の上で長く快適に使い続けられます。
そうです。
これこそが真の意味での賢い選択だと私は思っています。
妥協は禁物。
最終的に出した答えは、それに尽きるのです。
RTX5090 ゲーミングPCでよく聞かれる質問と自分なりの答え
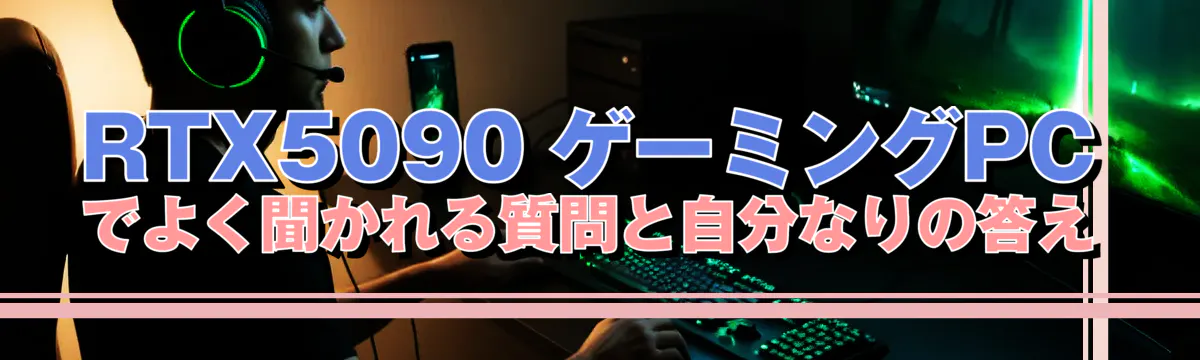
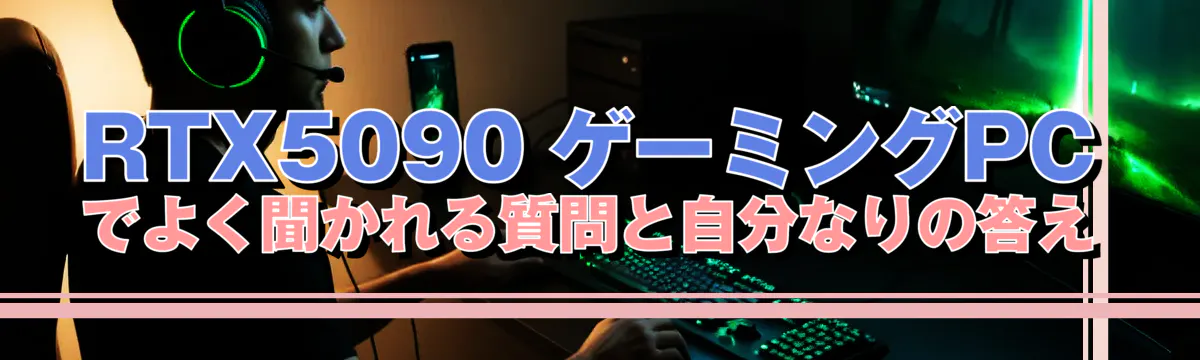
RTX5090なら原神をどの解像度で快適に遊べるか
数字上の性能は圧倒的に高いのですが、大事なのはその性能によって自分がどんな体験をするかという点であり、実際にゲームを立ち上げて体感した瞬間にその思いがはっきりしました。
1440pの環境ではフレームレートがモニターのリフレッシュレートを軽く超えていき、表示の滑らかさが目に心地よい。
それだけでなく、操作している指と画面の動きが自然にシンクロしている感覚が生まれます。
正直、少し大げさに言えば「ここまでスムーズに動くと人間の側がゲームに追いつけるか不安になる」と笑ってしまうくらいでした。
もちろん4Kの映像美も忘れるわけにはいきません。
高解像度の画面に映し出される璃月港の夜景は、長い一日の仕事を終えた後に見上げる街の明かりのようで、心が落ち着きました。
会社で気を張り続けている時間が長いと、家に帰っても気持ちを切り替えられないことがありますが、そういう時に4Kの映像に浸ると「ああ、やっぱりゲームの楽しみは癒やしなんだな」と再認識させられます。
数字で測れない、精神的な豊かさという価値。
一方で実力の片鱗を見せつけられるのが8Kです。
正直なところ、いまの段階では常用するには非現実的です。
しかし、DLSSを使って強引に動かしてみると、不思議と遊べてしまうレベルになるんですよね。
実際に操作してみて「GPUってここまで余裕を見せるのか」と思わず笑ってしまいました。
これは完全にロマン。
ただ、私はこのGPUの実力を100%発揮できるかどうかは冷却環境にかかっていると思っています。
最初に使っていたケースは正直詰めが甘くて、ゲームを長時間続けるとファンの音が「ゴーッ」と鳴り響き、せっかくの没入感が台無しになりました。
この経験は強烈に残っています。
ハードの性能だけではなく、支える周辺環境の大切さを痛感しました。
理由は単純。
軽快さに惚れ込んでしまったからです。
ゲームをしているときに動きがなめらかだと、頭で考えるよりも先に体が自然に操作に反応します。
その体感はまさに別物です。
仕事や家庭でちょっとしたストレスを感じる日々の中で、せめて遊ぶときくらいは軽やかで心地よい時間を過ごしたい。
そう考えたときに1440pの存在意義がすごく大きいと気づきました。
それでも結局は4Kと1440pの切り替えが肝心でして、気分や用途で選べる自由があるところが大きな魅力です。
人によって価値観は違うと思いますが、RTX5090ならどちらを選んでも性能面で妥協を強いられることがない。
その贅沢さがたまらないですね。
仕事終わりに椅子に体を預けて世界を歩き回ると、いつの間にか現実の疲れを忘れて画面の中に没頭している自分がいるのです。
これはただの趣味の時間以上の価値を持っています。
8Kを未来の可能性としてもう一度触れておきますが、確かに今はまだ遊びというレベルです。
ただ、時々試すことで「数年後にはきっと当たり前になっているんだろうな」と想像できますし、それは結構楽しいものです。
1440pでの快適さ。
4Kでの圧倒的な映像美。
これらが一枚のカードで手に入るのはとんでもなく贅沢なことです。
そして最終的に重要なのは、単なる性能比較では語れない「遊んで感じる心地よさ」だと、実際に触れて痛感しました。
私はこのGPUをただの部品としてではなく、信頼できる相棒だと思っています。
映像を堪能したいときは4K、軽快に動きたいときは1440p、夢を見たいときは8K。
選べる自由がそこにある。
ただそれだけの話なのに、こんなにも気持ちを豊かにしてくれる。
これがRTX5090の本当の価値だと確信しています。
だから私は自信を持って言えます。
RTX5090があれば、原神はどんな解像度でも最高の体験になる。
それは間違いない事実です。
RTX5090とRTX5080の違いを初心者目線で説明できるか
RTX5090とRTX5080の違いをビジネスパーソンとして日常的な感覚で見ていくと、結局は「必要とする性能を自分が本当に使い切れるのか」という一点に集約されるのだと思います。
数字やベンチマークは派手に見えますが、最終的に日常の使い方や仕事の場面にフィットするかどうかが何より大事です。
私はこれを身をもって痛感しました。
正直な話、5110や5090のようなフラッグシップモデルは魅力的に映りますが、その性能を十全に発揮できる環境を持っているかどうか、結局はそこに尽きます。
私は過去にRTX4090を購入したことがあります。
あのときは「せっかくだから一番上を」と気持ちが先走ってしまったのですが、使用していたのはWQHDモニター。
つまり、カードの実力の半分も引き出せていなかったんです。
ゲームをしていても確かに快適ではあるのですが、コスト感とのバランスを考えたら、やっぱりやっちゃったなと心の底から思いました。
興奮や憧れで判断すると、どうしても持て余す性能を手にしてしまう。
だからこそ今回は落ち着いて比較ができるのです。
RTX5090は、AI処理やレイトレーシングをがっつり活用する人には心強い存在です。
例えば映像制作や長時間の3Dレンダリング、さらには生成AIを本格業務に取り込む人。
そういった特定のシーンでは、5090が持つ力を日常的に引き出せます。
8KモニターやVR、複数ディスプレイを駆使する場合にも確かに頼もしさを感じるでしょう。
ただし、普通にフルHDやWQHD環境でゲームやちょっとした画像処理を楽しむ程度なら、正直過剰投資だと断言できます。
一方でRTX5080は、実にバランスが取れています。
性能は十分に高水準なのに、消費電力や発熱が5090ほど重くありません。
そして電源ユニットや冷却システムを無理に強化しなくても済む。
これが大きいんです。
現実的な話としてPCを組むときには、本体価格だけでなく電源やケース、冷却まで含めた「トータルコスト」を見る必要があります。
5080はそこに頭を悩ませずに済む安心感を与えてくれます。
これは決して小さなポイントではありません。
思い返すと、電源ユニットを強化する手間って結構面倒ですよね。
単純に金額が膨らむだけじゃなく、設置スペースや排熱との兼ね合いまで考えなければならない。
この「一つを変えると芋づる式に他も強化が必要になる」状況を体験すると、5090クラスは誰にでも勧められるカードではないと痛感します。
いざ取り付けたら「静音性が落ちたな」とか「部屋が少し暑いぞ」といった細かい点でも影響が出るんです。
こういうリアルな不便さは実際に試してみないと分かりにくいところです。
私の結論としては、ゲームが中心、または4Kまでの環境で活用するなら5080が堅実だと思います。
もちろん、長期的に8KやAIワークロードに本格的に進む構想があるなら5090を検討する価値は十分にあります。
ここを考えずに「せっかくなら最上位」を選んでしまうと、後から財布の痛みに気づいてしまう。
だから私はあえて冷静に5080を優先するスタンスを持っています。
5090は未来を先取りするようなカードです。
まるで折りたたみスマホや大型の電動SUVを手に入れたときのような感覚に近いと思います。
本当は必須じゃない。
でも確かに触れると「これが次の時代か」と感じる魅力があります。
それは否定しません。
しかし現時点での使い方や必要性を軸にすれば「5080で十分だよな」と自然に思えるのです。
迷う気持ちはよく分かります。
スペックを眺めれば眺めるほど心が揺れる。
幸いなことに、どちらを選んでも満足度の高い性能は得られます。
実際にも不満を持つことは少ないでしょう。
安心感があります。
私はこの比較を通じて学んだのは、最新の性能を追うよりも「どう楽しみたいか」を主軸に考えることです。
数字や技術的な話題に振り回されすぎず、自分が一日の中でPCをどう使うのか、どんな瞬間に満足を覚えるのかを素直に基準にする。
それを大切にして初めて、自分に合った正しい選択にたどり着けます。
最上位かどうかは本質ではなく、自分の生活に合っているかどうか。
5090を選んでも、5080を選んでも、答えはその視点の中にあるのです。
結局のところ、私は5080を選ぶ人の気持ちに一番共感しています。
そして同時に、5090を手にすることへの夢も理解できます。
どちらも間違っていません。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BG


| 【ZEFT R61BG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6800Gbps Crucial製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61AHB


| 【ZEFT R61AHB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HL


| 【ZEFT Z55HL スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | ブルーレイスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GJ


| 【ZEFT R60GJ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6800Gbps Crucial製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IK


| 【ZEFT Z55IK スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
RTX5090搭載ゲーミングPCはBTOと自作のどちらが安心か
最も大きな理由は単純で、あのクラスの消費電力や発熱を甘く見ていると、ほんの少しのズレで大きなトラブルに繋がってしまうからです。
余裕を持った設計や、実機を使った検証をショップがきちんと済ませてから届けてくれる。
これは、結果的に一番安心できるリスク対策だと感じました。
正直に言えば、私は過去にこの失敗をしています。
高額なパーツを前に、素人の過信がどれほど危ういものなのかを痛感した経験でした。
以前にRTX4090を組んだときの話ですが、電源周りの相性で予想以上につまずきました。
最初は動くようになってホッとしたのに、数時間後には突然の不安定化。
何度も調整しては不具合を繰り返し、休日のほとんどを潰してしまいました。
思っていた以上にお金もかかったし、自分のせいで壊したんじゃないかとヒヤヒヤし続ける感覚は、正直もう味わいたくないですね。
文字通り胃が痛くなります。
それでも、人に「じゃあ自作はダメなのか」と聞かれれば、即答はできません。
自作にはたしかに魅力があって、パーツを一つずつ吟味しながら組み上げていく楽しさは格別です。
数年前の私がそうでした。
木製パネルのケースを選んだとき、完成したマシンがリビングに置かれているだけで疲れた心が救われた瞬間があったんです。
その眺めながら「これ、自分だけの特別な一台だ」とひとりでに笑った記憶はいまも消えていません。
あのときの誇らしさは本当に大きなものでした。
電源ケーブルの一本の取り回しで安定感が吹き飛ぶ可能性があるし、冷却設計を誤ればGPUの本来の性能を発揮できない。
高額な投資を無駄にしてしまう危険を思うと、どうしても最初の一歩はBTOに軍配が上がると考えてしまうんです。
私が過去にやってしまった失敗の一つは、熱対策で追加のファンを積みすぎたことでした。
部屋に響く轟音だけが増していって、夜中に電源を切りながら「ああ、これはもうダメだな」とため息を漏らしました。
あの無力感は二度と繰り返したくない。
一方でBTOの場合は、必要な電源容量や冷却方法が最初から最適化されていて、届いたその日から電源を入れられる。
私は仕事から疲れて帰ってきて、机に向かって電源ボタンを押す瞬間に心が軽くなる。
そんな小さな安らぎが、日常にこそ大切だと感じています。
これが40代のいまの私の本音です。
余計な故障や不安定な挙動に振り回されるくらいなら、その分を家族との時間や自分のリフレッシュに使いたい。
二度目、三度目のチャレンジで、電源の理屈やエアフローを理解できるようになると、自作の世界は一気に広がって楽しいものになります。
一度BTOで安定動作を体験してからであれば、焦ることなく学びながら取り組める。
私もBTOを経てから改めて自作に挑戦してみましたが、そのときは全く違いました。
あのときの余裕と楽しさは今でもよく覚えています。
最終的にどうするのが良いかを私なりに答えるなら、やはりこうです。
最初はBTOを選ぶ。
そのうえで理想的な環境を確保したあと、少しずつ自作にシフトしていく。
決して背伸びせず、最初は堅実に行くのが最終的には一番早いのだと、私は強く思います。
要は、自分が何を優先したいかです。
安心と安定を取るのか、それとも自分だけのこだわりを全力で追求するのか。
選択肢は人それぞれですが、RTX5090のようなとてつもなく高性能で高額なパーツを扱う際だけは、安全策を選ぶ勇気も必要なんだと思います。
数十万円の買い物が不安定な動作でしか動かなかったら、誰だって立ち直れませんからね。
安心が欲しい。
結局この二つに尽きるんです。
40代になり、家庭や仕事に追われる日々の中で、私はこの気持ちに正直でありたい。
だからこそ、私は最初の一歩としてBTOを強く勧めます。
焦らなくても、楽しむための時間はまだまだ残っているのです。
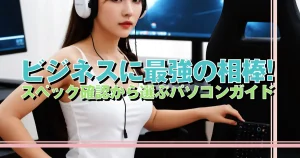
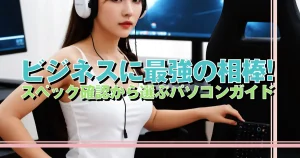
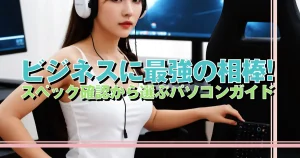



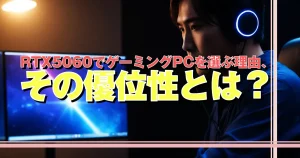
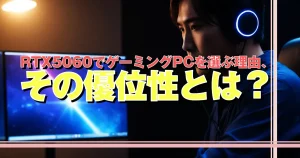
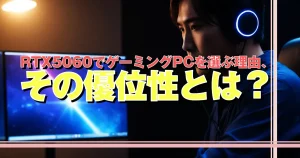
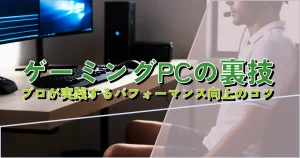
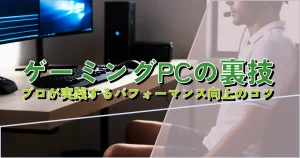
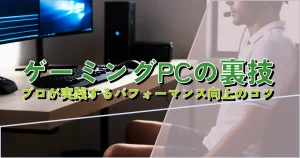
RTX5090搭載モデルを買うなら予算はどのくらいを考えるべきか
RTX5090を導入するなら、私は最低でも65万円を覚悟しておくべきだと考えています。
なぜならGPU単体で40万円近くかかるうえ、それを支えるCPUやメモリ、ケース、電源などの周辺パーツにもしっかりと投資しないと、せっかくの性能が宝の持ち腐れになってしまうからです。
安く済ませたい気持ちは痛いほど理解できますが、これまでの自分の失敗を振り返ると、むしろ妥協せず最初から資金を整えて動いた方が結局は安上がりで、精神的にもずっと楽なのです。
私が初めて大きなつまずきをしたのはCPU選びでした。
当時、RTX4090を導入したものの「CPUはそこそこでもいいだろう」と軽く考えてミドルレンジを選んでしまったのです。
結果としてGPUはまだ余裕を残しているのにCPUが足を引っ張り、せっかく数十万円をかけても性能が全く発揮されない。
正直、頭を抱え込みました。
RTX5090を本気で使いこなすなら、IntelならCore Ultra 9、AMDならRyzen 9、それくらいは覚悟して選ぶしかありません。
強烈なGPUを活かすには相応のCPUが必須であることを、私は痛いほど学んだんです。
後悔先に立たず、というやつです。
メモリも同じで、32GBがようやく最低ライン。
16GBで十分だと思い込んでいた昔の私は、動画編集をしながら高解像度でゲームを起動するたびに不安定になり、カクつく画面を見ては苛立ちを募らせていました。
64GBにして初めて「ようやく本来の力を出してくれている」と実感しました。
今振り返ると、安易に削った数万円が何倍ものストレスになって自分に返ってきていたのです。
痛みを伴った納得です。
ストレージについても学びがありました。
今のゲームは一つで200GB前後を要求し、アップデートでさらに肥大化していきます。
昔は1TBのSSDで足りると思っていたのですが、警告が出るたびに大事なデータを整理して削除し、やりたくもない家事をしているような気分でした。
PCIe Gen.5も試しましたが、発熱対策でヒートシンクが必要になり、そのコストと手間に辟易しました。
そこで今はGen.4を安定運用し、容量は2TB以上を基本としています。
冷静に判断すれば十分な性能を持ち、そして財布にも多少は優しい。
経験して初めて分かるバランス感覚でした。
ケース選びでも大失敗をしています。
集中なんて到底できませんでした。
あのとき、「なぜ素直にフルタワーを選ばなかったんだ」と本気で悔やみました。
ピラーレスケースが流行っていますが、実際に使用してみると見た目に映えるだけではなく、冷却性能も高い。
多少高価でも、安心して長期間使える環境を作るためには投資するだけの意味があります。
格好だけではなく、冷却という現実的な恩恵をもたらしてくれるのです。
電源はさらにシビアな問題です。
RTX5090を動かすなら1200Wクラスが安全圏。
私は当初「1000Wあれば大丈夫だろう」と楽観的になり、その結果、盛り上がる瞬間に限ってブラックアウト。
真っ暗な画面と無音になった部屋で、ただ一人「やっちまった」とつぶやくしかありませんでした。
高揚から一転する落差。
その悔しさは、忘れられません。
多少過剰なくらいが、むしろ心の安定剤になります。
安心につながるんです。
冷却も軽視してはいけません。
かつて空冷で行けると思い込んでいた私は、夏場に痛い現実を思い知らされました。
部屋の冷房を全開にしていても内部の熱はこもり、性能が抑制され、安定性を失っていきます。
静音性も犠牲になり、せっかく苦労して組んだはずの高性能PCがただの不安定マシンに成り下がった瞬間の無力感は、今思い出しても胸がざわつきます。
水冷や高性能空冷の導入こそ、本当の安全策だとようやく腹落ちしました。
こうして必要な構成を積み重ねていくと、GPUに40万円、CPUに10万円前後、メモリとストレージに10万円、ケースや電源、冷却環境でさらに5?10万円は必要になります。
合計65万円前後。
BTOならさらに工賃や保証費が上乗せされてくる。
自作ならもっと安く済むと思っていた頃もありましたが、パーツの選択肢や安定性を考えると実際はほぼ同額なのです。
幻想でしたね。
本当に。
結果として私がたどり着いた結論はひとつです。
RTX5090を搭載したゲーミングPCをしっかり活用したいのであれば、65万円を最低ラインとして腹を括ること。
少しでも削ればボトルネックが生じ、快適さが一気に失われるのを嫌というほど体感しました。
高い出費に躊躇するのは当然ですが、中途半端に妥協し、不満だらけのPC環境を抱えることほど虚しいものはありません。
だから私は、最初から資金計画を整え、必要な投資を惜しまない姿勢こそが最も短い道だと自信を持って断言します。
過去の失敗がすべて今の考えにつながっています。
私は身をもって痛みを味わい、そのうえでようやく学びました。
これが正直な心境です。