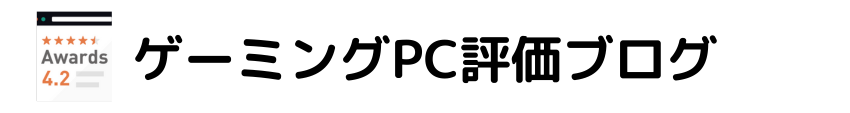Valorantを快適に遊ぶためのCPUの選び方ガイド
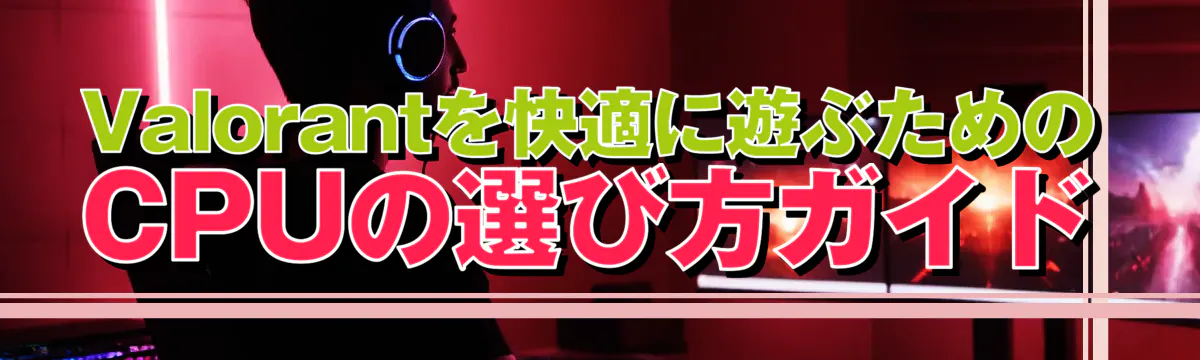
インテルとAMD、自分に合うのはどっち?
インテルを選ぶにしてもAMDを選ぶにしても、現行世代のCPUは十分に頼れる性能を備えています。
ですが、実際に手に入れてから長く付き合っていくことを考えると、自分にとって本当に落ち着ける選択はどちらなのかを見極める必要があります。
私自身、これまでに何度も構成を組み直してきましたが、最終的に残るのは「この環境なら安心して長期戦に臨める」と自分の心から思えるかどうか。
その一点です。
ここに尽きますね。
インテルのCore Ultraシリーズは、やはり長年「安定のインテル」と呼ばれてきただけあり、信頼性の塊のような存在だと私は感じています。
例えばValorantのような対戦ゲーム。
フレームが一瞬でも途切れると、勝機が目の前からすり抜けていってしまう。
その瞬間を何度も経験してきた私は、滑らかに動いてくれる環境であることにこそ救われてきました。
イライラせずに反応できる環境。
やっぱりそれが何よりなんです。
AMDのRyzen 9000シリーズはまた違った魅力を持っています。
特にX3Dモデルを試したときには率直に「ここまで伸びるのか」と驚いたのを覚えています。
あるとき仲間と丸一日ゲームをやり続けたのですが、最後まで安定して動いてくれました。
熱の不安に悩まされることもなく、本当にタフだと感じた。
その姿はまるで長丁場の試合を堂々と戦い続ける選手のようで、頼もしいなんて一言では言い表せません。
本当に感心してしまったんです。
ただし冷静に点を並べていくと、総合的な落ち着きや安心感ではまだインテルに軍配が上がる印象も拭えません。
新しいゲームエンジンが次々と登場し、どんな挙動の変化が起きるかわからない時代ですから、不確定要素をできるだけ減らす意味でクロックの高いインテルを選ぶのは「とりあえず間違いない」と思える選択です。
こうしたリスクの少なさは、仕事の現場で培われてきた私には特に大切に感じられます。
とはいえ、AMDにしかない価値も間違いなく存在します。
同じ価格帯ならコア数やスレッド数に余裕があるので、ゲームの裏で録画や配信をしながら、さらに調べものまで同時に行える。
それを実際にやってみて本当に便利だと感じました。
「欲張っても許してくれる環境」は、気持ちを軽くしてくれます。
器の大きさを感じましたよ。
発熱や消費電力の面も見過ごせません。
インテルもCore Ultra世代になり改善してきましたが、高負荷時にはやはりまだ熱がこもります。
一方のAMD Zen 5は空冷でも十分戦える印象を受けました。
追加コストをかけなくても安定して使えるのは、結局財布に優しいという安心感につながります。
電気代だって無視できませんからね。
勝率だけを追求するなら、インテルのCore Ultra 7クラスを選ぶのが一番堅実です。
200fpsを超える安定感は、競技を本気で取り組む人にとって武器そのものです。
もし私が大会での勝負に挑む仲間に勧めるとするなら、やはり迷わずインテルを推すでしょう。
これは揺るぎない鉄板の選択です。
一方で、仕事にも趣味にも同じPCを活用したいならAMD Ryzen 7 9800X3Dに大きな魅力があります。
動画編集や画像処理を並行して進めながら、息抜きにゲームをしてもストレスを感じない。
そういう万能さは会社と家庭を行き来する私のような立場にとって非常にありがたいのです。
すべてを安定感に寄せるよりも、日常で多様な活用を見据えた柔軟な選択肢を持ちたい。
これが私の素直な気持ちなんです。
つまり整理すると、激戦の一瞬に絶対の安定を求めるならインテル。
幅広さとコスト効率を重視するならAMD。
だからこそ、迷うポイントは結局「いまの自分が何を大切にしたいか」につきます。
安定か、効率か。
シンプルな話です。
悩んで迷った末に選んだCPUは、結局のところ自分にとって最も納得できる相棒になる。
そう思いながら、今日もPCと過ごしています。
これ以上の答えはないと思いますよ。
コストと性能のバランスが良い中堅CPUはこれくらい
CPUを選ぶときに一番肝心なのは、やっぱり自分が何を優先するかだと私は思っています。
Valorantをやるうえで感じてきたことですが、正直な話、グラフィックボードよりもCPUの出来次第でフレームレートの安定感は大きく変わるんですよね。
Unreal Engine 5に切り替わってから特にそう感じました。
映像は派手になったのに、ちょっとした処理のもたつきで「あれ、なんか重いな」と違和感を覚える瞬間が増えた。
いざ原因を探ってみると、多くの場合はCPUの処理力不足だったりする。
私はこの数年、友人や同僚と一緒にPCを組む機会が増えて、自分でも試行錯誤を繰り返してきました。
その中でたどり着いたのは、結局のところ中堅CPUの選択が一番安心できる、という答えです。
IntelでいえばCore Ultra 5、AMDでいえばRyzen 5。
このクラスのCPUが一番バランスが良いとしみじみ思います。
高価な上位モデルは性能こそすごいですが、冷却や電源、グラボとの釣り合いを考えると全体バランスが崩れがちになるんです。
いわば持て余す力。
私たちの仕事や生活でもそうですが、一部だけ突出しても他にしわ寄せが来れば全体はかえって不安定になる。
昨年、知人からBTO構成の相談を受けたときのことです。
私はCore Ultra 5 235を選びました。
心のどこかで「やっぱりCore 7のほうが無難か?」と迷いはあったのですが、組み上げて実際に動かしてみたら驚きました。
RTX5060Tiとの組み合わせでフルHDだとfpsがだいたい200前後に張りつき、撃ち合いの最中も全然ストレスがない。
むしろ自分用に作ったマシンよりも安定していて、「これで本当に十分なんだ」と思い知らされた瞬間でした。
いや、本当に驚きましたよ。
AMDのRyzen 5 9600にも触れましたが、これもまた良い味を出しています。
新しいZen5世代になってキャッシュ構造が改良されたことで、操作レスポンスが以前より明らかに向上していました。
特に、UE5系のタイトルを動かしたときにその差を実感できたんです。
Intelとの差もぐっと縮まっており、こうなると「価格を考えればこれでいいじゃないか」と自然に納得できる。
過剰に上位モデルを追う必要は、本当にないんだなと。
私はどうしても性格的に上を選びたくなるのですが、冷静に考えればValorantのために上位CPUを買う理由はあまりありません。
もちろんCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xは魅力的ですが、そこに手を出すとグラボや冷却にも追加投資が必要になり、結局PC全体の設計は窮屈になる。
性能ってそういうものなんですよね。
CPUだけで完結するわけじゃない。
メモリやSSD、電源や冷却すべてが噛み合ってこその快適さ。
チームの働き方と一緒です。
誰か一人だけが完璧でも組織は強くならないのと同じで、PCも総合力で動いている。
だから実際の選び方は意外とシンプルだと考えています。
フルHDで240Hzに挑みたいならCore Ultra 5かRyzen 5を選べばいい。
もしその先にWQHDや4K環境を視野に入れたいのなら、ようやくCore Ultra 7やRyzen 7に手を伸ばす。
バランスって本当に大事です。
背伸びをしてハイエンドを買ったとしても、後になって「こんなにいらなかったな」と思うより、自分が使う環境に見合った構成で堅実に積み上げていくほうが後悔は少ないです。
私がCPUを考えるときに必ず重視するのは、ベンチマークの数値よりむしろ「操作感」の方です。
Valorantでは一瞬の入力遅延が勝敗を分ける。
fpsの数字が高いだけじゃ意味がなくて、実際に使ったときに「違和感なく操作できるか」がすべてです。
結果として誤差の積み重ねが勝率を変えるんです。
ふと気づくと「今日はやけに勝ちが多いな」と思う日、それは間違いなくPCのレスポンスが快調な時なんですよ。
どこまで追求するか。
その線引きは永遠のテーマです。
でも私は結局、中堅CPUが最適解だと考えています。
その釣り合いが一番人間らしく付き合える範囲ですから。
理想と現実のシーソー。
悩んだあげく、最後に落ち着く場所。
これが私の答えです。
だから私ははっきり言います。
ValorantをフルHDで心地よく楽しみたいならCore Ultra 5 235かRyzen 5 9600を選んでおけば後悔しない。
上は贅沢、下は物足りない。
真ん中にこそ納得感があります。
安心できる選択です。
そして何より、予算に対して最大限の満足を引き出せる。
この事実だけは揺るぎません。
人に勧めるのも自分で使うのも、このラインが一番ちょうどいい。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42850 | 2438 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42605 | 2244 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41641 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40937 | 2332 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38417 | 2055 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38341 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37113 | 2330 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35491 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35351 | 2210 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33610 | 2184 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32755 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32389 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32279 | 2169 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29124 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28413 | 2133 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25336 | 2151 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22983 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22971 | 2069 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20762 | 1839 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19418 | 1916 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17651 | 1796 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15974 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15220 | 1960 | 公式 | 価格 |
配信や動画編集も視野に入れる人へのおすすめ領域
配信や動画編集まで視野に入れてゲーミングPCを選ぶとき、私が声を大にして伝えたいのは「とにかく動けばいい」では間違いなく後悔する、ということです。
焦りと苛立ちが積み重なって、結局は余計な出費に繋がったことを痛感しました。
だから今の私なら、最初の時点から余裕ある構成を選ぶ大切さを迷わず訴えたいのです。
安心して作業できる環境の価値は、想像以上に大きいものだと。
特に配信を意識するなら外せないのがCPU性能です。
例えばValorantは比較的軽い部類のゲームですが、その裏で配信ソフトを同時起動した瞬間にCPUの負荷は跳ね上がり、8コア程度のCPUではカクつきやフレーム落ちが目立ちます。
かつて私もそうでした。
視聴者に「ラグい」と言われるたびに冷や汗を流したものです。
しかしCore Ultra 7クラスに切り替えた途端、映像は安定し「見やすくなった」と直接フィードバックをもらえた瞬間には、本気で胸が熱くなりました。
やはり数値以上に、目に見える変化がある。
動画編集も同じです。
16GBメモリで挑んでいた頃、PremiereとDaVinci Resolveを同時に立ち上げると、プロジェクトが重くなるたびにカーソルが跳ねたり固まったりして、編集の流れが寸断されてしまう。
正直、イライラしか残りませんでした。
そこで32GBに増設したところ、それまでのストレスが嘘のように軽減され、複数のシーケンスをまたいで同時に作業するのも余裕になったのです。
この変化は単なる動作の快適さにとどまらず、作業そのものに前向きな気持ちを持てるようにしてくれました。
まさに余裕の力です。
ストレージも決して軽んじてはいけません。
ゲームの本体自体は数十GBで済んでも、録画データが数時間単位で溜まれば一気に数百GBを食いつぶすのは当たり前です。
私は以前1TBのSSDを使っていましたが容量不足に追われ、外付けHDDに逃げざるを得ませんでした。
その結果、編集のたびに読み込み速度の遅さでストレスを感じ続けるという負の連鎖を経験しました。
2TBのGen4 NVMe SSDへ切り替えた後は、編集作業が一変。
そしてGPU。
ゲーム用途だけで考えると軽視されがちですが、最近のRTXシリーズに搭載されているハードウェアエンコードの力は、配信や編集環境では無視できない存在になっています。
RTX 5070を導入してからは、WQHDの解像度でゲームと配信を同時にこなしても不満を感じることはほぼなくなり、画質についても「くっきりしたね」と言ってもらえた時は素直に嬉しかったです。
やはり人に喜ばれると報われる気持ちになるものです。
冷却についても、軽く考えていたことを後悔しました。
昔は「どのCPUクーラーでも同じだろう」と思い込んでいましたが、その結果は大きなファンの音と熱によるパフォーマンス低下。
集中力を乱され、作業が進まない状態でした。
静けさの力、大事です。
以前は見た目のコンパクトさを最優先にしてしまい、結果として熱がこもりファンが唸る騒がしい環境になってしまいました。
もう後悔しかありません。
今はエアフローを重視したケースに切り替え、電源も700W以上を搭載。
安定感は圧倒的に変わりました。
安心して負荷の高い作業を任せられる環境になったと同時に、大人になってからは「部屋に置いて心地よいデザイン」という視点も意外と大きいと気づいたのです。
機能と見た目、その両立は侮れない。
Core Ultra 7やRyzen 7以上のCPU、32GB以上のメモリ、大容量のGen4 SSD、そしてRTX 5070やRadeon RX 9070クラスのGPUを基準に据えること。
予算はそれなりに掛かりますが、その分確実に返ってくるものがある。
作業効率、気持ちの余裕、そして日々の満足感です。
中途半端な構成に妥協すると、結局そのツケが必ず回ってくると私は身をもって知りました。
最終的に重要なのは、自分が気持ちよく使える環境を整えられるかどうか。
ゲームも配信も編集も、ストレスをできるだけ消して集中できる場を作ることが、仕事や趣味を長続きさせる上で欠かせないと、40代になった今だからこそ強く思います。
だから私は、これから配信や編集に取り組もうとする人へ、心から迷わずワンランク上のゲーミングPCをおすすめするのです。
Valorantに向いたグラフィックカードの今どき事情
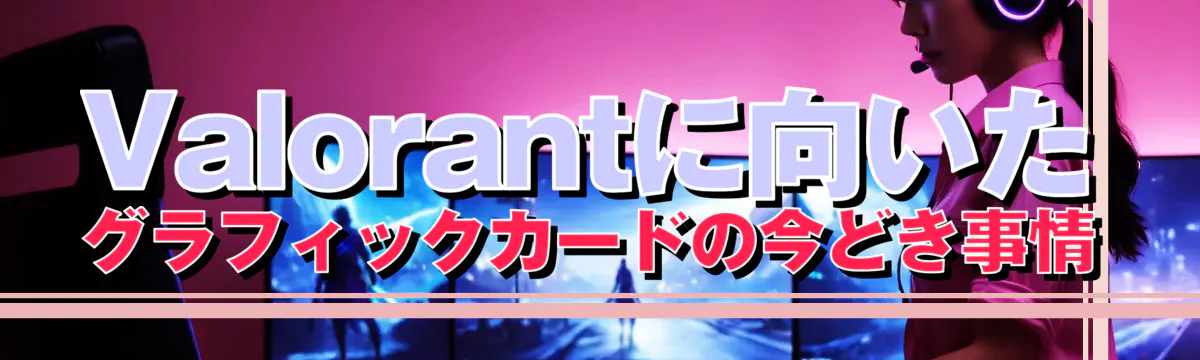
RTX 60番台同士の違いをどこまで意識すべき?
カタログスペックを眺めていると、わずかな違いにしか見えないかもしれませんが、実際にプレイしていると「あ、やっぱり違うな」と肌で感じる瞬間が出てくるんです。
特に撃ち合いがギリギリのところまで競った場面、わずかな描画の安定性が命取りにも勝利の一因にもなる。
あの差は本当に馬鹿にできません。
私が強く勧める理由はそこです。
私はかつてRTX4060と4060Tiを短期間で乗り換えながら使ったことがありました。
数値の上ではせいぜい誤差程度だと思っていたのに、実戦に出てみると全然違ったんです。
フレームが乱れずに最後まで安定してくれる安心感があると、気持ちに余裕が生まれる。
その余裕が結果につながるんだなと、はっきり実感したのを今も覚えています。
勝負どころで落ち着いて狙えたのは、機材に支えられていたからだと思うんです。
もちろん5060だって悪くありません。
フルHD環境で設定を落とせば十分に動くし、200fps前後出れば大半の人にとっては快適といえるでしょう。
決して「駄目な選択肢」なんて言いません。
ただし、もし将来的に240Hzモニターや高解像度環境に進みたいと考えているなら、最初からTiを選んでおいた方が懸命です。
これは実体験からも断言できますし、迷うぐらいなら背伸びしてでも買ったほうが後悔はぐっと減ります。
彼は「5060で十分だよ」と言い張っていたのに、最後に出した答えはTi。
それから数日後、「やっぱりこれで良かった」と笑いながら話してくれたんです。
私はただ頷くしかありませんでした。
長く付き合う道具だからこそなおさらです。
私自身、スマートフォンを買うときにも同じ経験をしました。
標準モデルと上位モデルで悩み、最終的に少し無理して上位を購入。
その後の満足度は圧倒的でした。
これは仕事道具選びにも直結する考え方なんです。
後から買い替えるという手間の方が、実は一番無駄に感じるものですから。
技術的な面でも、5060Tiはアドバンテージがあります。
メモリ帯域に余裕があり、DLSSやReflex 2などの機能が効く場面も増えてきました。
特にUE5に移行してからのValorantは、ロードマップ進行中とはいえ一部のシーンで急に描画負荷が跳ね上がることがあります。
その一瞬の処理落ちで流れが止まることがあるんです。
競技での一瞬がどれほど重い意味を持つか、プレイ経験がある方なら理解できるはずです。
ただ、用途が広がると話は違います。
動画編集や4Kグラフィックスまで重視したいのであれば、さすがに60番台では力不足。
5070以上を本気で考える段階に入ります。
しかし今の私の状況では、Valorantを軸に据えてプレイすることが中心なので、5060Tiこそ最もバランスが取れていると感じています。
むしろ他に迷う余地はないとも言い切れます。
時間をかけて悩むより、次の装備投資を考える方が建設的です。
快適さ。
私はむしろ、余った予算があるなら良いキーボードやモニターといった周辺機器に回した方が、全体のゲーム体験が確実に高まると考えています。
Tiを導入したうえで、指先から目までの環境を磨き上げていく。
その方が圧倒的に勝率に寄与するんです。
なぜならどんなにグラフィックカードが強力でも、入力や視認性でストレスが残っていたら本末転倒だからです。
総合力で勝負するために、最初に揺るぎない基盤を持っておくべきだと思います。
繰り返しになりますが、Valorantを競技意識を持ってプレイするならTiが最適です。
確かに5060は価格的に魅力ですが、将来性や持続性を見据えると「あと一歩」欠けている。
PCは毎日触れる道具だからこそ、中途半端さは不満につながりやすいんです。
小さな妥協は積み重なり、やがて大きなストレスへと膨らみます。
ビジネスでもよくある話ですが、最初に間違いない選択をしておけば、その後に余計な迷いも減る。
だからこそ、私はTiを選び続けています。
値段差は短期的な負担に見えるかもしれませんが、その安心感と安定はゲームを続けている限り、永く寄り添ってくれるんです。
Radeonの最新シリーズは選択肢としてアリか?
長年GeForceをメインに扱っていた私にとって、それはある意味で安心の選択肢だったからです。
しかしここ最近、実際にRadeon RX 9070XTを試してみて、その考えは少しずつ揺らぎ始めています。
最初は半信半疑だったものの、今では「これは十分にありだ」と胸を張って言えるようになったんです。
特に印象的だったのは、私がよく遊んでいるValorantでの挙動です。
フルHDで競技用の設定にしてプレイしたとき、240fps前後を安定してキープしてくれたのは正直驚きました。
さらにはフレーム生成の仕組みが効いて、画面の動きが以前より格段に滑らかに感じられる。
特に勝敗が一瞬で決まる場面では、ちょっとした描画の遅延ですら命取りになります。
もちろん、何もかもが完璧というわけではありません。
ドライバの更新に追われる感覚は相変わらず残っています。
夜中にやっとパソコンに向かえる時間ができて「今日は思う存分遊ぶぞ」とワクワクしながら起動した瞬間にアップデートの通知。
些細なことですが、こうした手間が積み重なると悩ましくもなります。
安定性の点ではまだまどろっこしい部分がありますし、トラブルがゼロとは言えない。
でも、それでも私が使い続けたいと思えるだけのパフォーマンスがあることも事実で、その点が今のRadeonの大きな転換点なのかもしれません。
FSR 4の印象についても触れたいのですが、これには良い意味で裏切られました。
1440pの出力で遊んでみたとき、画質に不満はほとんどなく、滑らかさも十分に出ていました。
それでもゲームを本気で遊んでいるときって、そんな細部は実はあまり気にならないんです。
ゲームは結局「楽しさ」と「没入感」が一番大事で、それを守ってくれる限りGeForceじゃなくても問題ない。
それに気づかされたのは新鮮な体験でした。
私個人としておすすめしたいのはRX 9060XTです。
理由はシンプルで、価格が抑え目でありながら競技設定で200fps以上を余裕で出してくれるからです。
大きな出費はためらうけれど、やはりゲーム体験は快適にしたい。
そう感じている人にとって、これは本当にちょうどいい選択肢になると思います。
一方で、解像度とリフレッシュレートにこだわりたい方は9070XTを選んで、WQHD以上のディスプレイと組み合わせるのがいいでしょうね。
そのときは、「ここまできたか」と感じさせる力を確かに持っているはずです。
クリエイティブ用途にまで視野を広げると話は変わってきます。
動画編集や配信をするなら、今でもNVIDIAのアドバンテージは健在です。
エンコードの安定感やアプリケーションの最適化はやっぱり一日の長がある。
なので「仕事にもゲームにも」と一本化したいならGeForceに軍配が上がるのは間違いないでしょう。
ただ、純粋にゲーム用として考えるならRadeonの存在感は一気に増してきている、と私は思います。
以前は「二番手で安価な選択肢」という歪んだイメージがあったのに、今では堂々と候補のひとつとして考えられるまでに変わったんです。
振り返ってみると、この気持ちの変化はやはり体験に勝るものはないということです。
机上のスペックや数字だけでは動かなかった心が、実際に触って操作して、体感して、そこでようやく「楽しい」と感じられた。
それ以上に説得力のあるものはありませんでした。
そのとき私は、自分の中に久しく味わっていなかった感覚を覚えました。
ワクワクしたんです。
ただ、現実的な視点も忘れないようにしています。
ドライバ改善や価格の上下、さらにはNVIDIA側の新製品の登場などで市場は刻々と動いています。
その中でどこまでRadeonが食い込んでくるかは、正直まだ読めない部分もあります。
だからこそ大げさに持ち上げすぎるのも違う。
ただ一つだけ確実に言えるのは、今現時点で快適にゲームを楽しめる手段の一つとして自信を持って推せるレベルには達しているということです。
言い換えれば、私の答えは案外シンプルなんです。
Valorantをはじめ競技系タイトルで快適さを第一に考えるなら、9060XTか9070XTを選べばまず失敗はない。
ドライバ更新の手間や少しのクセに目をつむれるなら、それ以上に得られる体験は確かに十分に価値がある。
そう思わせてくれるところに、私は魅力を感じています。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R59ABF

| 【ZEFT R59ABF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CF

| 【ZEFT R60CF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DC

| 【ZEFT Z55DC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59AO

| 【ZEFT R59AO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59CF

| 【ZEFT R59CF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
高フレームレート重視派に向いたグラボ選び
高フレームレートを目指すなら間違いなくグラフィックカードの選択が肝だと、私は強く感じています。
CPUの足を引っ張る要素がなければ、そのまま描画性能がフレームレートとして反映される。
この関係を、私は自分の経験で何度も思い知らされました。
昔はパーツ構成なんて「まあ平均的なら問題ないだろう」と気楽に考えていましたが、実際に試合を重ねると、ほんの一瞬の処理落ちが勝敗を分ける。
試合後に「あの場面さえ止まらなければ」と悔しさがこみ上げる経験をしたことが何度もあります。
だからこそ私は、対戦を本気で考えるならフレーム単位での安定感こそが最強の武器だと確信しているのです。
Valorantというゲームは登場初期は軽快な部類でしたが、Unreal Engine 5への移行を経て状況が変わってきました。
私は普段フルHD環境でプレイし、240Hz対応モニターを愛用しています。
ここで200fpsを安定して維持できるか否か、この違いは言葉にする以上に大きな体感差を生むのです。
逆に揺らぐと「なんで今、ここでカクつくんだ」とつい声に出してしまい、内心苛立ちながらマウスを握る瞬間が訪れます。
この差は実際の試合結果にも大きく響くのです。
以前私はGeForce RTX 5070を試しました。
ReflexとDLSS 4を組み合わせた動作は、驚くほどスムーズだった。
240fpsが途切れず画面に張り付く感覚に、思わず「やるなあ」と声が出ました。
旧世代のカードでは数値こそ届いても微妙な瞬間落ち込みがあり、それが集中を阻害し、高性能モニターを使っても「宝の持ち腐れだな」と嘆いていたのです。
だから今の世代、5060Tiや5070といったカードは、コストとのバランスも含め、まさにちょうどいい存在だと感じています。
対してRadeonシリーズの進化も侮れません。
RX 9060XTや9070あたりになると、FSR 4によってフレーム生成の品質が大幅に上がり、遅延の少なさも大きな魅力になっています。
正直、FSR 3時代の印象は良いけれどDLSSには一歩及ばない、というものでした。
しかし新版を触れてみると「ここまで追いついたのか」と驚く場面が増えました。
プレイしていてフレームが滑らかにつながる心地よさがあり、正直言って見直しましたね。
ただ、どのカードを選ぶかは環境次第です。
WQHD以上でのプレイを想定するなら、最初から5070や9070を選んだ方が安心できます。
その余裕があれば大会配信や複数タスクでも動揺せず、自分の機材を疑う余計な不安も減るのです。
逆にフルHD専用であれば、5060Tiや9060XTでも十分戦えます。
私は過去に「どうせなら上を狙おう」と背伸びしてオーバースペックのカードを買ったことがありましたが、結果として大半の時間が持ち腐れになりました。
そこから学んだのは、自分が必要とするフレームレートの基準を最初に定めることが大切だという点です。
選択を誤るとお金も時間も無駄になります。
だからこそ大事なのは、自分がどの環境で戦いたいかを見つめ直すことです。
フルHDで安定したfpsを求めるなら中堅で十分。
配信や映像美を考えるならば上位を狙う。
この判断は単なる性能数値の比較ではなく、自分のプレイスタイルや美学に直結してくる大事な場面なのです。
私が根本的に重視しているのは「余裕」です。
現状だけではなく、将来アップデートで負荷が増えたときでも対応できる安心感。
その気持ちを持てるかどうかで精神的な集中力が変わってきます。
ゲームは腕前だけじゃありません。
メンタルも大きく響くのです。
「この先のパッチで急に重くなるかも」と不安を感じながらプレイするのと、「まあ余裕で動くだろう」と思って試合に入るのとでは、判断や反応のキレがまるで違います。
心の余裕。
アップデートや新世代の展開は予想以上に負荷をかけてくることがあるのです。
そのためこそ、今の最適解を選びながらも将来の余裕を確保することが、結局は最もコストパフォーマンスに優れた方法になると私は信じています。
これを徹底すれば、Valorantのような熾烈な競技環境でも長期にわたって安定したプレイを続けられるのです。
頼れる相棒。
勝ちたいと願う心と、それを支える性能の両立。
この2つがかみ合った時に初めて、自分のプレイに納得感が宿るのだと感じています。
40代の私でも「まだまだ戦える」と思える瞬間があるのは、その支えがあるからです。
だから私はこれからもグラフィックカード選びで妥協はしません。
いや、妥協できないんです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48450 | 100766 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 31992 | 77178 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30003 | 65995 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29927 | 72584 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27029 | 68139 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26375 | 59548 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21841 | 56149 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19821 | 49904 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16479 | 38921 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15915 | 37762 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15778 | 37542 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14567 | 34520 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13675 | 30506 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13138 | 31990 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10768 | 31379 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10598 | 28257 | 115W | 公式 | 価格 |
Valorantで変わるメモリとSSDの組み合わせ

16GBで十分か?32GBが欲しくなる状況とは
もちろん、Valorantのように単体の軽めのゲームを楽しむだけなら16GBでも大きな不満は出ないでしょう。
ただし、それは「本当にそれだけしかしない」という条件つきの話なのです。
結果として、余裕を持たせた方が精神的にも断然ラクだと痛感しましたね。
私が強く印象に残っているのは、16GB時代に友人とボイスチャットをしながら配信を試みた夜のことです。
Discord、OBS、録画処理を同時に走らせた瞬間、タスクマネージャーに残った空きメモリはほんの数GB。
画面を見ながら「あ、これは危ない」と冷や汗をかきました。
正直、心臓に悪いですよ。
安心感を得たい。
私が32GBに増設して最初に感じたのはまさにその気持ちでした。
Unreal Engine 5に対応したゲーム環境では、見た目の派手さや美しい映像の裏でメモリが静かに多く消費されていきます。
ロードは速くても、録画編集を同時にすると16GBではガタつきが出る。
32GBに切り替えてからというもの、余裕感は段違いで、心そのものに余裕をもたらしてくれました。
単なる容量の話ではなく、「環境に信頼できるか」という問題なんですよ。
少し前ですが、同じタイミングで配信していた知人と映像を見比べた出来事もありました。
彼は16GB、私は32GB。
私の映像は途切れなく動いていて、その違いを確認したとき思わず「やっぱりか」とつぶやいてしまいました。
数字や環境表のスペックではなく、現場で体感できる差。
そこに重みがあるんです。
短時間で完結する作業なら16GBでも問題ないかもしれません。
私も当初、「動画編集程度なら大丈夫だろう」と考えていました。
それに耐えながら進める編集作業は、とにかくストレスの塊でした。
あの無駄な時間が再び来ると思うとぞっとします。
だから今は迷わず、余裕を投資だととらえるようになりました。
心底そう思っています。
安定した環境のありがたさ。
40代にもなると、仕事と家庭の両立を大事にしながら、限られた時間を自分なりに楽しむようになります。
そんな生活の中でPCの安定は小さそうでいて、とても大きな価値を持ちます。
疲れ切って帰ってきた夜にPCを立ち上げても、もし途中でカクついてしまったら、その一瞬で張り詰めた気持ちが萎えてしまうんです。
これは単なる技術的な数字の話ではなく、心の安らぎに直結しているのだと思います。
以前の私はコスト重視でした。
できるだけ安く構成を組んで、その分を別のパーツに振り分けてベンチマークを追いかける。
若い頃はそれ自体がゲームみたいで楽しかった。
しかし今は違います。
多少値が張っても、後々のストレスを軽減できるなら十分に元は取れる。
そういえばストレージでも同じ過ちを繰り返しました。
容量を抑えた結果、外付けに頼る羽目になる。
その不便さを経験して、余裕を確保する重要さは嫌でも学びました。
後で苦しむくらいなら、最初から備えておけばいい。
これは理屈というより実感からくる考えですね。
Valorantのようなゲーム一本に絞るなら16GBで大丈夫です。
ただし、配信や録画、あるいは将来の負荷増大を見越すなら、32GBが確かな選択。
私は実体験を通して「余裕が余裕を呼ぶ」ことを何度も味わいました。
未来の自分を助けるのは、今のちょっとした投資だと信じています。
正直に言って、戻りたくもないんです。
Gen4 SSDを選ぶときの利点とコスト感
もちろん数値だけを見ればGen5は目を見張る性能を誇りますし、技術的な最先端を手に入れたくなる気持ちも理解できます。
でも、日々のゲーム体験において本当に体感できる差は思っているほど大きくはないのです。
私は仕事を終えて限られた時間で遊ぶ立場なので、効率を上げつつ心地よい体験が得られることが一番重視すべき点だと感じています。
実際に私がそう確信するようになったのは、昨年末にシステムをGen3からGen4へ移行したときの体験がきっかけでした。
今までロード時間の少しの遅さを妥協点だと受け止めていたのですが、思い切って2TBのGen4 SSDを導入したところ、あらゆる動きが滑らかに感じられるようになったのです。
マップの切り替えが数秒短縮されるだけで、気持ちにこんなにも余裕が生まれるのかと驚きました。
心の余裕。
Valorant自体は超重量級のアプリではなく、CPUやGPUにかかる負荷もそれほど突出しているわけではありません。
しかし、ロード時間が数秒変わるだけでプレイ全体のテンポは確実に変わります。
試しに知人のPCでGen5を体験しましたが、通常のゲームプレイの範囲で見れば体感できる差はほとんどありませんでした。
確かにベンチマークのスコアは桁違いに映えるのですが、それが日常のゲームシーンにどう貢献するかといえば、正直「ほぼ差がない」としか言えません。
私の周りでも「実際の心地よさはGen4が勝つ」と話す声が目立っています。
でも遊ぶためにはGen4で十分」と語ったのが妙に心に残っています。
そう。
まさに納得の一言。
ここで現実的に考えざるを得ないのはやはりコストです。
Gen4のSSDは流通も安定していて、手を伸ばしやすい価格帯に落ちてきました。
1TBであっても十分に利用できる水準になり、2TBモデルを導入すれば複数のタイトルを同時に管理できるので、遊ぶたびにわざわざ削除とインストールを繰り返す必要がありません。
これは精神的にもずいぶん楽で、長い仕事を終えた夜に遊ぼうと思ったときにすぐゲームに入れるのは小さなようで大きな満足です。
安堵感。
逆にGen5は、どうしても価格が高く、発熱の問題も無視できません。
大きくて主張の強いヒートシンクが標準でくっついてくるため、ケースの構造やエアフローとの相性が悪くなる場合もあります。
静音性やデザイン性に気を配りたい私にとっては、その点だけで導入のハードルが上がりました。
見た目のインパクトが強すぎると、せっかく整えたケース内に違和感が出てしまうんです。
「やっぱり現場感覚は違うよな」と苦笑しながらため息をついたのを覚えています。
もちろん、全員に同じ答えが当てはまるわけではないと理解しています。
しかし多くの人、特に仕事や家庭の合間にゲームを楽しむ社会人ゲーマーにとっては、余計な部分へコストや労力を割くよりも、むしろCPUやGPUへの投資を優先し、ストレージはGen4で堅実に組むことが一番合理的だと思います。
その判断が結果的に「大人の選択」なんだろうと私は感じるのです。
率直に言えば、以前まではストレージが快適さにここまで影響を及ぼすとは想像できていませんでした。
しかしいったん体感してしまうと戻れなくなるほど差を感じるのです。
わずかな時間短縮でも、仕事終わりに遊びたいときには気持ちの切り替えがスムーズになり、無駄な待ち時間が減ると心身の疲れも軽減されている気がします。
驚き。
私が強く伝えたいのは決して難しいことではありません。
Gen4 SSDを選べば不安なくゲームを楽しめるうえに、容量の余裕も確保できます。
その結果、余った予算をほかの重要なパーツに振り分けることができ、システム全体のパフォーマンスが底上げされるのです。
スペック表に並ぶ数値の高さよりも、自分が触れて感じる体験こそが本当の満足につながる。
私はその実感を通じて「結局はGen4が最良のバランス」と心の底から信じています。
――これが、40代になった私の選択。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |







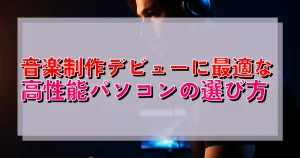
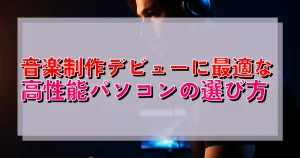
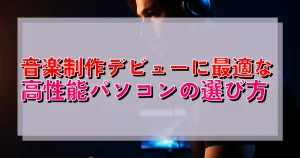
BTOの段階で大容量ストレージを仕込んでおく意味
ゲーミングPCを注文する際に私が一番大事にしているのは、CPUやGPUではなくストレージです。
もちろんグラフィックの性能や処理速度も大切ですが、最終的に効いてくるのは「余裕のあるストレージを最初から積んでいるかどうか」。
そう痛感するようになったのは、過去の私自身の失敗がきっかけでした。
増設は不可能ではないのでやれば済む話なのですが、毎回残容量を確認してヒヤヒヤするのは精神的にかなりの負担でした。
悔しかったですね。
ゲームの種類によっては必要なストレージが大きく変わります。
Valorantのように軽量なタイトルを中心に遊んでいると、「1TBもあれば十分だろう」と考えがちですが、昨今のAAAタイトルは巨大です。
私が最近試した海外の大作RPGは、インストールだけで180GBを要求してきました。
その時は心底焦りました。
しかもアップデートが入ればさらに容量が増えていきます。
こういう経験をすると、余裕のない構成がどれほどストレスになるか、身に染みて分かります。
配信をしていると、そのストレスはさらに膨れ上がります。
動画ファイルはたとえ数分の映像であっても簡単に数百MB単位に膨張します。
気まぐれで撮りためていたら、すぐに残容量を気にする生活へと変わっていきました。
「録画を始めても途中で容量が尽きたらどうなるんだろう」なんて、余計な心配をしながらゲームをするのは正直しんどいです。
楽しいはずの趣味が不安の種になってしまうのは本末転倒だと思いました。
だからこそ、BTOの段階で大容量ストレージを選ぶことが安心につながるのです。
余裕がある環境は、気持ちさえも支えてくれます。
残容量を逐一確認しないで済む。
さらにストレージには速度や発熱といった問題も絡んできます。
市場ではPCIe Gen.5対応のハイエンドSSDが注目されていますが、実際には発熱対策でヒートシンクや冷却ファンまでセットで考えなければならない。
結局コストがかさむうえに、メンテナンスに気を使う場面も増えます。
読み込み速度は十分すぎるほどですし、価格も落ち着いていて安心感があります。
性能と安定性の両立ですね。
私の生活スタイルから考えても、これは理にかなった選択でした。
昼間は数GB単位の動画や資料を扱い、夜はValorantをプレイして気分をリセットする。
仕事用と趣味用を一台で両立するなら、ストレージの快適性は欠かせません。
この環境こそが私にとっての仕事の効率でもあり、余裕のある遊びの時間でもあるのです。
だから妥協はできませんでした。
安心感が違います。
そしてもう一つ大事なことは、「ストレージは気持ちの余白を買うもの」という考えです。
撮りたいときに動画を録画でき、保存したいときにデータを残せる。
余計なことに頭を使わなくて済む環境は、それだけで圧倒的に快適です。
しかもBTOで事前に2TBを選ぶ程度の追加料金で済むのであれば、後で外付けを買い足すよりコスト的にも有利です。
だから私は声を大にして伝えたいのです。
Valorant用のゲーミングPCを注文するなら、最初から大容量SSDを搭載しておくべきです。
後から増設しても確かに動きますが、管理の手間、精神的な余裕、さらには作業効率を考えると、最初の構成で容量をしっかり確保する判断の方がはるかに合理的です。
経験から胸を張ってそう言えます。
これ以上ない選択。
大容量SSDを最初から積んでおくこと、それが結局、一番楽で賢くて、長く自分を助けてくれる。
冷却とケース選びで変わるValorant用PCの使い心地


空冷と水冷、実際どちらを選ぶのが現実的?
自作PCに取り組む人なら誰しも一度は頭を悩ませるテーマだと思います。
率直に言えば、ほとんどのゲーミングPCユーザーにとってはしっかりした空冷クーラーで必要十分だと感じています。
その理由は、今のCPUが昔に比べて発熱設計が格段に改善されているからです。
特にValorantのようにCPU依存度が高いタイトルでは、安定したCPU温度は快適さに直結します。
空冷ならシンプルな構造ゆえの壊れにくさ、コストの安さ、取り回しの良さと三拍子そろっていて、肩の力を抜いてゲームに向き合える安心感があります。
実際、私が長く空冷を使い続けられたのも、この気楽さがあるからなんです。
もちろん水冷の価値をまったく否定するわけではありません。
4KやWQHDといった高解像度でGPUを酷使する場面になると、さすがに空冷では処理しきれない熱をどうにかしたくなる。
そんなときに水冷の力を借りれば、しんと静まり返った動作音の中でパフォーマンスはきちんと維持できる。
実際に360mmクラスの簡易水冷を導入したときは、目の前の映像が安定していることに思わずうなってしまいました。
画面がぬるぬる動き続けるのは、本当に爽快なんですよね。
数年前に導入した水冷クーラーは、最初の一年こそ夢のような静音性と冷却性能を見せてくれましたが、二年目に入った瞬間からポンプの異音が耳を突き始めました。
最初は小さなカラカラ音。
それが日増しに大きくなり、ついにはゲーム中も気になって仕方がないレベルにまで悪化。
異音に気を取られて肝心の試合どころではありませんでした。
苛立ちしかありませんでしたよ。
結局はサポート対応に時間を取られ、交換品が届いて落ち着くまで数週間が無駄になった。
そのとき思ったんです。
「水冷ってかっこいいけれど、手間は覚悟がいるな」と。
その一件以降、私は再び空冷派になりました。
面倒ごとから解放される。
パーツを増やす必要もなく、気楽にPCを使える。
余計な心配から距離を置ける。
それが私には何より大きいのです。
とはいえ今の水冷は進化していることも確かで、最近登場しているモデルは外観が驚くほど洗練されています。
光るRGBがケース内を鮮やかに彩り、配線もすっきりとまとめられた見た目の魅力は、空冷ではなかなか味わえません。
私の知人もNZXTやCorsairの水冷を導入し、SNSに誇らしげに写真を上げています。
自分の小さな実験室を持っているようなワクワク感がにじんでいるのです。
ただし忘れてならないのが、ケース選びとの相性です。
大型のタワーケースなら空冷クーラーをしっかり収められ、十分なエアフローも確保できます。
そこで仕方なく水冷に頼らざるを得ないケースもある。
だから冷却方式とケース選びをセットで考えなければ、不本意な選択を強いられることになりかねません。
これは私自身が過去に痛い目で学んだ教訓でもあります。
特に強調したいのは、標準的な設定でValorantを遊ぶなら空冷で十分ということです。
現代のCPUは発熱が暴れにくいため、空冷の実直さが活きる環境のほうが多い。
逆に映像体験を極めたい、4K解像度で妥協したくないという場合は水冷が意味を持ち始めます。
私から言わせてもらえば、「どこまで冷却に投資する気があるか」と「その手間に付き合える覚悟があるか」で結論は自ずと出るのです。
ですが裏方が安定しない限り、主役となるGPUもメモリもフルに実力を発揮することはできません。
特にFPSでほんの一瞬のカクつきが勝敗を分けることだって珍しくない。
Valorantの試合を重ねるたびに、「冷却は単なるオプションではなく、命運を握るパーツだ」と強く痛感します。
それを知ってしまったからこそ、私は空冷を信じている。
堅実さこそ安心して戦える土台だと思うのです。
最終的に言えることはシンプルです。
フルHDやWQHD程度で遊ぶ一般的なスタイルなら空冷が最も合理的です。
一方で4Kでの没入感や水冷ならではのロマンを求めるなら、それを手に入れる価値はある。
だから私は言います。
でも挑戦したい方には水冷を勧めます。
これが、私の答えです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BC


| 【ZEFT Z52BC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55AT


| 【ZEFT Z55AT スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G


| 【ZEFT Z56G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DB


| 【ZEFT Z55DB スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ガラスパネルケースと冷却性能の落としどころ
どちらか片方だけでは満足できない。
使ってみてよく分かりました。
冷却だけを優先して無骨なケースを選ぶと、机に置いたときのワクワク感がまるでないんです。
逆に、見た目に惹かれてガラス張りのケースを選ぶと、夏場に熱がこもってパフォーマンスがガタ落ちする。
これ、実際に私が経験したことです。
以前、サイドパネルが全面ガラス仕様のケースを使っていました。
最初は「透明感があってカッコいい」と心が躍ったのですが、真夏の夜にValorantをプレイするとGPUが90℃近くまで跳ね上がる。
しかもフレームレートが乱れるせいで集中できない。
頭のどこかで「このままじゃ壊れるかも」と不安がずっとつきまとい、ゲームに没頭できない状況になりました。
結局、排気ファンを天面に増設して、吸気用にメッシュフィルターを組み込んだところ、7℃ほど下がっただけなのに動作が安定し、こんなにも違うのかと本気で感動しました。
これが私の最初の学びでしたね。
ただ、私もそうでしたが、一目惚れして選んでしまうのが人情でもあります。
だからこそ今伝えたいのは、最初の「かっこいいな」という気持ちと、その後の「長く快適に使いたい」という現実的な要望をどう両立するかを、冷静に考えてほしいということなんです。
最近人気のあるピラーレスケースなどは、まるでインテリア雑誌に載るような存在感があります。
それ自体は素晴らしいのですが、冷却対策が欠かせないのも事実です。
空気の流れを前後と上下でスムーズに作ること。
それさえ意識すれば、見た目重視のケースでも十分性能を発揮できます。
私自身も水冷クーラーの導入を考えましたが、最近のCPUは昔ほど発熱がひどくなく、小型の簡易水冷で十分でした。
無理して大型にする必要もないと分かったときは、ホッとしました。
そして静音性。
これも軽視できません。
深夜、仕事を終えた後に静けさの中でゲームをしたいのに、ファンの轟音が響くと気持ちが萎えます。
せっかく気分を切り替えて遊ぼうと思った瞬間に水を差される。
余裕があると静音化パーツを選びやすく、後で後悔しなくて済むんです。
最近、木製パネルを取り入れたケースを試してみる機会がありました。
これが意外にも心地いい。
木の温かみが部屋に馴染むのに、冷却性能はメッシュフロントで確保されているというバランス。
以前のガラスケースのような不安はなく、安心してゲームに集中できました。
そのとき「やっぱり落ち着いてプレイできる環境こそが一番大切なんだ」と再確認しました。
だから私が思うのは、ケース選びにおいて「見た目か性能か」の二択ではなく、どう両立させるかという考え方です。
そうした工夫が、最終的に240fpsを安定して叩き出せるかどうかという結果に直結します。
安心感は、ゲーム環境の中で何よりも価値があると私は思います。
とにかくこれが大事。
冷却性能が安定していれば、不安なくPCに向かえる。
その安心があるから集中できる。
逆に言えば、いくら見た目が美しくても「これ大丈夫かな」と思いながら使うケースは、結局楽しみを削ってしまいます。
長い時間ゲームと付き合うには、毎日目にして喜びをくれるデザインと、負荷をかけても安心できる冷却性能、この二つが相互に支え合う状態が必要です。
片方だけでは長続きしない。
大人になって感じるのは、その中間点をどう見つけるかなんです。
これこそが快適さを長く維持する方法だと私は思っています。
だから、ガラスケースの魅力に惹かれても、必ず冷却と静音についての設計を並行して考えてほしい。
派手さだけで突っ走る必要はなく、実用性のみで妥協する必要もない。
その間にある選択こそが、自分のライフスタイルに合った答えなのだと気づきました。
そして今になって振り返ってみると、一目惚れしてケースを選んだあの感情も決して無駄ではなかったと思います。
あのとき失敗だと感じた経験があるからこそ、試行錯誤して解決策を探し、より良い環境にたどり着けたのです。
失敗すら学びに変わる。
そう感じられるのは、年齢を重ねた今ならではかもしれません。
「デザインも冷却も、必ず両立できる方法がある」と。
見た目を優先したい気持ちを否定せず、長く使う現実も見つめる。
その両方に折り合いをつけることこそ、最終的に自分にとって最高のPCを作る唯一の道なのです。
机に向かうとき、思わずニッと笑ってしまうPC。
その二つを両立できたとき、初めて真の満足感が手に入る。
私は今そう確信しています。
静音性を確保しつつデザインにもこだわる方法
静かなゲーミング環境をつくるうえで私が一番大事だと思うのは、冷却性能とデザインの調和です。
どちらか一方でも欠けると、どうしても長くは満足できません。
ファンの音が響けば集中力は途切れますし、逆に見た目が気に入らなければ部屋に置いたときにどうにも違和感を覚えてしまう。
ゲームという趣味は長時間向き合うことも多いからこそ、納得できる機材が必要なのです。
特に緊張感の高い勝負ごとになると、わずかな雑音ですら大きなストレスになることがありますからね。
だから私は、性能と外観、この両輪を揃えることが必須だと信じています。
ファンの音を抑える工夫は、単に静音パーツを取り付ければ良いという話ではありません。
ケース自体の設計で解決できることも多くあります。
しっかりと風の流れを考えて作られたケースを選び、そこへ静かに回る冷却パーツを組み合わせれば、大型の空冷クーラーひとつで驚くほど落ち着いた環境をつくれるのです。
水冷を使うにしても、ラジエーターのファンが低速で安定していれば耳障りにはなりません。
さらに最近は吸音材を最初から組み込んでいるケースも増えていて、かつては夢物語だった「静かに冷やす」という考え方が現実味を帯びてきています。
これは本当にありがたい進化だと感じます。
昔は静音を取るなら見た目を犠牲にするしかなく、選択肢が乏しかったのをよく覚えています。
黒やグレーの地味で無骨な箱ばかりで、正直妥協の連続でした。
しかし今は、ガラスで開放感を演出したタイプや、木材パネルを用いた温もりあるモデルまで多彩です。
私も最近、木製パネルを採用したケースを導入したのですが、リビングに置いた瞬間に「家具の仲間入り」と感じられるほど馴染んで驚きました。
その心地よさ。
配信や実況をしている方には、この外観の意味を過小評価してほしくありません。
カメラに映り込むケースの質感や光が、視聴者の印象を大きく左右するからです。
映像における小さな要素ですが、実際に目にする人の記憶には残るもの。
スーツと同じで、見映えの良さは自信の源にもなる。
私はそう実感しています。
「どうせなら見た目にも納得したい」そう思って選ぶことに、決して無駄はないのです。
ただし、静音とデザインばかりを追求して冷却力が落ちてしまえば本来の目的を見失います。
GPUは通常常時全力では動いていませんが、長時間のゲームや配信を並行して行えば熱は確実に溜まります。
だから必要なファンを適切に配置し、吸気と排気のバランスをしっかり設計することが重要になるのです。
温度に応じて自動で回転数を調整できる仕組みがあれば、普段は驚くほど静かさを保ちながら、負荷が上がったときには自然とパワフルな冷却に切り替わる。
その切り替えこそが快適さを保つカギです。
今人気のフレームレスやガラス主体のケースは確かに美しい。
ですが私はつい警戒してチェックしてしまいます。
見た目に魅かれて購入した結果、実際に使い始めるとファンがうなりを上げて大失敗、そんな経験をしてしまう人も多いでしょう。
それは、見た目だけを優先して空調を軽視した照明器具を導入し、部屋が暑くて居心地が悪くなった感覚に似ています。
華やかな演出にも必ず裏があります。
要注意。
だからこそケースのレイアウトとファン制御は大事なのです。
吸気ルートを前面にしっかり確保し、側面には遊び心やデザイン性を加える。
この両立こそ理想です。
本当に満足できた買い物です。
意外に見落とされがちなのが電源ユニットです。
これを静かなモデルにするだけでも、日常の快適さは大きく変わります。
私が80+ Gold認証付きの電源を導入したとき、負荷が低い場面ではファンが完全に停止するという仕様に驚かされました。
正直、動作しているのか忘れるほどの静かさです。
細部をおろそかにしないことの積み重ねが、最終的に「長い付き合いができる一台」へとつながっていきます。
冷却、静音、デザイン。
これらの要素が揃ったとき、ゲーミング環境は本当に豊かになります。
ファンの位置や回転制御、配線の整理といった細かい部分も手を抜かず、最後に自分が心から納得できるケースを選ぶ。
性能ばかりを追ったゴツゴツした箱では、心のどこかで物足りなさを感じ続けるでしょう。
静かで落ち着いた動作と、部屋に自然と溶け込む見た目。
この両立によってゲームは生活リズムに心地よく融けていきます。
最終的に私が伝えたいのはただひとつ。
快適さそのものが戦いの大きな武器になるということです。
追い込まれた場面で真価を発揮できる人は、雑音に邪魔されない落ち着いた空間を持っています。
私はこれからもその信念を持ち続けたいと思っています。
Valorant向けゲーミングPCを買う前に確認したい疑問
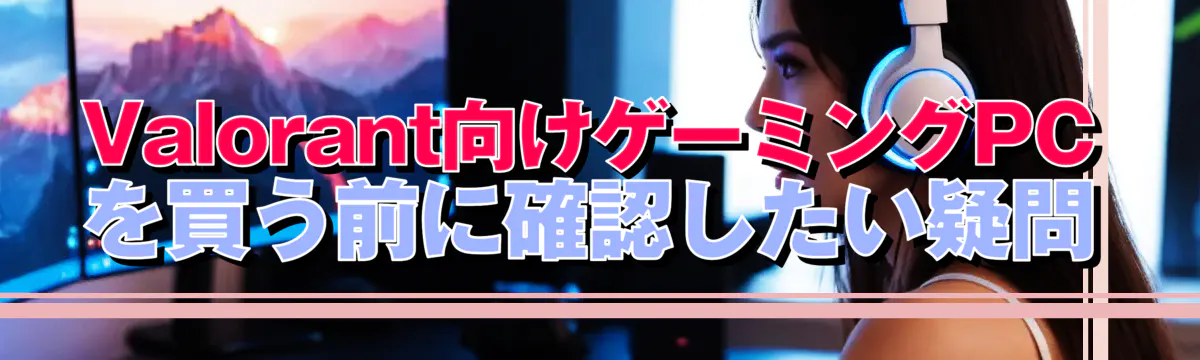
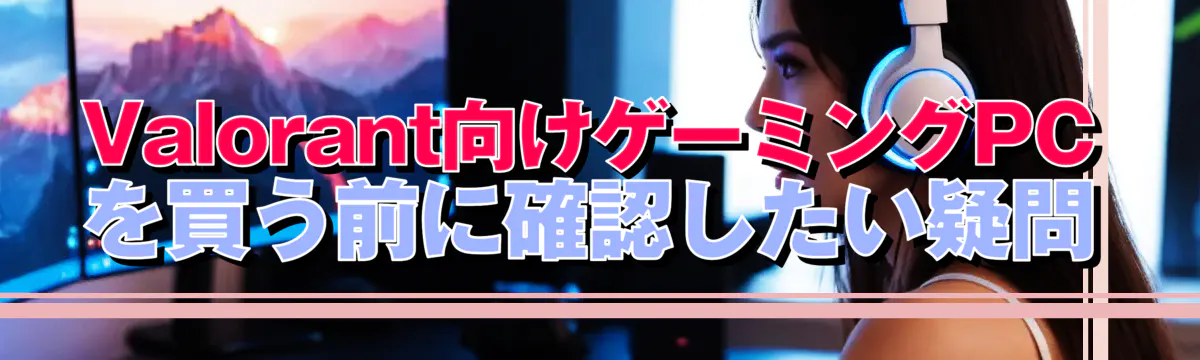
144fpsを安定させるために必要な構成は?
144fpsを安定して出して快適にValorantをプレイするために一番欠かせないのは、やはりCPUの性能だと私は思います。
昔、まだ古い世代のCPUを使っていたころは、決定的な場面で一瞬だけ画面がカクついて、集中力を一気に削がれてしまったことが何度もありました。
ところが現行のミドルクラスCPUへ乗り換えた途端、あの不快な引っかかりがほとんどなくなり、自然な挙動に戻ったときには思わず深くうなずきました。
反応速度の小さな差が、そのまま勝敗に直結するという事実を、あの時に身をもって知ったのです。
では、どの程度のCPUが必要なのかというと、今の基準で言えばCore Ultra 5やRyzen 5クラス以上がちょうどいいと思います。
確かに数値だけ見れば、エントリー向けでも条件次第で144fps近く出る場面はあります。
しかし実際にスモークやモロトフが重なる場面など、ラウンド後半になると一気にフレームレートが100fps台へ落ち込むことがあるのです。
その瞬間に勝敗が決まってしまうことを思うと、スペック不足をわざわざ選ぶ理由はどこにもない。
私はそう実感しています。
一方でGPUは、Valorantそのものが比較的軽い部類に入るため、極端に高級なモデルは必要ありません。
とはいえ最近はエンジンが進化して描画負荷が以前より重くなる場面も増えましたので、RTX 5060 TiやRadeon RX 9060 XTといったミドル帯を押さえておくと安心だと感じています。
贅沢なのではなく安心のための選択です。
次にメモリですが、16GBが最低限の水準です。
現在のDDR5世代は速度や安定性も桁違いなので、将来のことまで考えると32GBを用意しておく方が理にかなっていると思います。
他の大作ゲームや複数作業を同時並行でこなすときにも、余分なストレスを感じにくくなるからです。
ストレージに関しては、今ではNVMe SSDが当たり前になりました。
私自身、過去には容量不足に悩まされ、やむなくお気に入りのタイトルを削除した経験があり、その度に大きな虚しさを感じました。
しかし2TBを導入してからは「今日はどれを遊ぼうか」と迷えるようになり、気持ちに大きな余裕が生まれました。
1TBでも足りることはありますが、経験上2TBが大人の現実解だと思います。
冷却に関しても軽く見てはいけません。
私は夏場の暑さでフレームレートが落ちていくのを経験してから、本格的に空冷から簡易水冷へ切り替えました。
すると不安はなくなり、都度144fpsを維持できるようになったのです。
静音性も大きく改善され、深夜に集中して遊ぶときも気兼ねなく没入できるようになりました。
安定性がここまで集中力を支えてくれるとは正直驚きでした。
静かな安心。
ケース選びも地味に重要です。
昔は外見を気にして安価で見栄えだけのケースを選んでしまったことがありました。
その結果、内部温度が高騰して部品の力を十分に引き出せず、もったいない思いをしました。
デザインと冷却の両立、それが今の時代の正解だと私は考えているのです。
結局のところ、私が思う144fps安定の構成はとてもシンプルです。
CPUは現行ミドルクラス以上、GPUもミドルクラス、メモリは16GB以上、ストレージはGen.4 NVMe SSD、そして冷却とケースにまで気を配ること。
この基準を満たせば、競技設定で大きな不満を感じることはほとんどありません。
逆にどこかで妥協してしまえば、その負担は必ず大切な勝負の瞬間に返ってきます。
だから私は自分自身の経験を踏まえ、迷うことなくこの構成を選びたいと思うのです。
納得感。
私は40代になってから、ようやく余裕を持ってPC環境を整えることの意味を理解するようになりました。
若い頃なら見過ごしていた小さな不安や不便さを「減らせるなら減らした方がいい」と素直に思えるようになった。
144fpsという数値の安定は、その象徴のように私には映ります。
だから今日も私は迷わず、自分が信じる構成を選んでいくのです。
長く使うならCPU優先かGPU優先か
Valorantを快適にプレイするためのパソコン構成を考えると、多くの方が悩むのは「CPUを優先すべきか、GPUを優先すべきか」という点だと思います。
高リフレッシュレートのモニターを使えばその差が露骨に表れます。
CPUが足を引っ張ると、どんなに強力なGPUを積んでいても快適には戦えない。
これが現実です。
解像度をWQHDや4Kまで引き上げれば、描画処理の大半を担うのはGPUだからです。
実際に私自身、4K環境でValorantを試した時は、GPUの性能差が勝敗の感覚に直結することを強く実感しました。
緻密な映像の迫力は素直に感動しましたね。
映像美を楽しみたいならGPUが物を言う、これは揺るぎない事実なのです。
ただし、多くのプレイヤーは競技性を重視してパソコンを選ぶのではないでしょうか。
私もそうでした。
大会や配信を意識した快適な環境を考えると、重く描写を磨きすぎるよりも、フレームレートを安定させる方が圧倒的に重要です。
ValorantはUnreal Engine 5に移行して多少は負荷が増えましたが、AAA級の重量級ゲームと比べればGPU負担はまだ軽めに収まっています。
その一方で、CPUのシングルスレッド性能には依存し続けている。
だからCPUを一世代更新しただけでfpsが飛躍的に伸びることも珍しくありません。
CPUがボトルネックになる、典型的な構造を持ったゲームなのです。
長い目で見て快適に使える構成を求めるなら、やはりCPUに余裕をもたせるのが最も現実的な策です。
私は過去にGPUばかりに投資して痛い思いをしました。
正直に言えば、最初の1年は夢のように快適で「この選択は正解だ」と本気で思いました。
ところが2年目に入り、CPUの限界によってfpsが頭打ち。
高価なGPUが完全に持ち腐れの状態になり、当時の私は愕然としました。
「パソコンはCPUで決まるんだ」と。
苦い体験でしたね。
それ以来、私はCPUを重視してきました。
Core Ultra 7やRyzen 7といったクラスを選んでおくと、後々GPUを交換して環境をスケールアップする際にも対応力が段違いです。
配信を並行して行っても余裕があるし、新しいグラフィック機能にも追従できる。
柔軟性。
最近のGPUは目覚ましい進化を遂げています。
AIを活用したアップスケーリングや強烈な描画力を持ったモデルが次々に登場し、確かに憧れを抱きます。
ただ、ValorantのようにフルHDからWQHDまでが主流のゲームでは、240fpsを狙う戦いにおいて大切なのはGPU以上にCPUの働きです。
選ぶ部品が一つ違うだけで、試合中の安定感に直結する。
私の経験では、勝利の鍵はまさにCPUなのだと断言できます。
私は迷っている方がいれば、迷わず伝えたい。
CPUにお金をかけましょう。
GPUは後から強化できます。
でもCPUは簡単に入れ替えられない。
マザーボードやメモリまで巻き込まれる買い替えは、本当に面倒でコストも重いです。
だからこそ最初にCPUを選ぶことが、後悔を減らすためのベストな選択になるのです。
これは理屈ではなく、実際に失敗を経て得た結論です。
安定性が勝敗を決める。
後悔しないための道はCPU優先。
もし「結局どうすればいいのか」と問われれば、私は迷いなく答えます。
長期的にValorantを楽しみたい人、そして大会に近い環境でプレイしたいと考えている人にとって正解は「CPUを優先し、GPUは必要に応じて強化する」というシンプルな方針です。
私自身がそうして選び取り、結果として安心してゲームを続けられています。
これは机上の空論ではありません。
実際にお金も時間も使い、失敗から学んだ血の通った答えだと言えます。
そして同じように悩んでいる方がいれば、私は胸を張ってこの考えを勧めたいのです。
選択を誤ればすぐに不満が出ます。
しかしCPUを優先して構築すれば、数年経っても不安なくプレイが続けられる。
その価値は何よりも大きい。
パソコン選びに正解は一つではありませんが、ことValorantに関しては土台を固めることこそが正義です。
そこからすべてが始まります。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AZ


| 【ZEFT R60AZ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56F


| 【ZEFT Z56F スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AS


| 【ZEFT R60AS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AS


| 【ZEFT Z54AS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
コスパの観点で見るBTOと自作の違い
私はこれまで何度もBTOパソコンと自作パソコン、その両方を選んできました。
どちらが正解かと聞かれれば、それはそのとき自分がどんな状況に置かれているかによって変わるのだと思っています。
急いで仕事で使う必要があるならBTO、じっくりと納得のいく一台を組み上げたいなら自作。
結論としてはシンプルですが、体験の中で感じたことは決して単純なものではありませんでした。
ネットで注文して数日、早ければ翌日には届いてしまう。
私はあるとき、突然仕事のリモート環境を整える必要が生じ、即納モデルを注文しました。
段ボールを開けて電源を押した瞬間、ちゃんと起動する。
その当たり前の動作が、疲れ切った私には大きな安心になったのです。
正直、心底助かった。
この安心感は大きいです。
以前、自作を深夜まで組み立てたものの電源が入らず、翌朝出社する顔が真っ青になった経験があります。
あの胃がきりきりする感覚。
今となっては笑い話ですが、当時は本当に泣きそうでした。
そういうとき、BTOの「届いた日にすぐ使える」強みが胸にしみます。
ただ、一方で私は自作の自由さにどうしようもなく惹かれます。
例えば会社の案件でどうしても動画編集が重くなることが分かっていたとき、自分でCPUに予算を割き、昔使っていたケースと電源を流用することで全体コストを下げました。
お金を掛ける場所を選び、逆に妥協できる場所も自分で決める。
これがすごく楽しい。
最初に電源が入って、OSが立ち上がった瞬間の達成感は格別でした。
達成感。
けれど、自作は面倒の連続でもあります。
特に相性問題は壁です。
今でも鮮明に覚えているのは、メモリがどうしても認識されず、何日も悩み続けた夜のことです。
ネットで情報を漁って同じように苦しむ人の書き込みに励まされながら、最終的にはBIOSの更新で解決しました。
面倒だけど、やみつきになるのです。
BTOは便利ですが弱点もあります。
特に電源や冷却機構は「見えない部分のコストカット」となりがちです。
かつて買ったBTOでは、派手なライティングのケースに喜んだのも束の間、数時間ゲームを回すと中が灼熱になり、夏場はファンが悲鳴を上げていました。
あのときの「これは長くは持たないかもしれない」という感覚、忘れられません。
やっぱり見た目より中身。
パーツ選びの楽しさはSSDを選ぶときにも感じました。
BTOでGen.5にカスタムすると妙に割高になる一方、自作なら予算を見ながらGen.4を選び、必要になったら後から増設すればいい。
仕事が山積みで一刻も早く稼働したいならBTOが頼もしい。
逆に時間と気持ちに余裕があるときは、自作こそ大人の趣味として、いや人生の寄り道として最高に面白い。
もっとわかりやすい例えをすると、自作はDIYの家具づくりに似ています。
材料選びに手を抜けないぶん時間はかかりますが、完成品を目の前にしたときの感慨はたまらない。
BTOは完成品の家具を店で買うようなもので、すぐに部屋に置けてすぐに使える。
どちらが上か下かではなく、自分が今欲しいのは手軽さか、達成感か。
そこに違いがあるだけです。
私は正直なところ、自作をしている時間が好きで仕方がない。
夜中にパーツを眺めながら「次はどこから手をつけようかな」と悩む時間すら楽しい。
本当に助かるんです。
だから、人に相談されたときに私が言うのは「どちらを選んでも大きな後悔はしないと思うよ」という一言です。
BTOなら届いたその日から快適に作業ができる。
自作なら「これが自分の一台だ」という誇らしい瞬間を味わえる。
どちらにしても、手に入るのは便利さか誇りかの違いだけ。
迷う必要はありません。
最終的に私の答えはこうです。
時間を惜しいと思うならBTOを選ぶべきです。
逆に少しの苦労を楽しみに変えられると思えるなら、自作こそおすすめです。
それぞれがそのときの自分に合った選択をすればいい。
悩みすぎる必要なんてないのです。
拍子抜けするくらいシンプルでしょう。



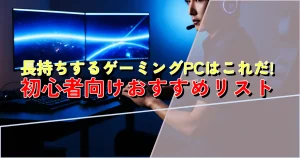
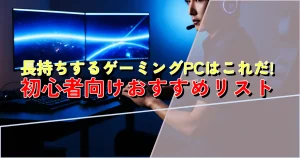
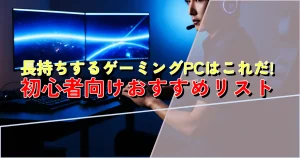






モニターのリフレッシュレートとPC性能の付き合い方
モニターのリフレッシュレートとPC側のfpsの出力との釣り合いをどう整えるか、そこに勝敗を左右する大きなカギがあります。
正直なところ、私自身も最初はその本質を理解していませんでした。
高リフレッシュレートのモニターさえあれば一気に環境が整うと勝手に思い込んでいたのです。
しかし実際はそうではなく、自分の使うパーツや環境を全体で見直して、はじめてそのモニターが本当に力を発揮するのだと痛感しました。
私が初めて240Hz対応のモニターを手にしたときのことは今でも鮮明に覚えています。
当時は「これで一気に勝率が上がるに違いない」と本気で信じていました。
ですが、実際にプレイしてみるとPCが頑張っても180fpsくらいしか出ず、期待していた快適さはまったく感じられなかったんです。
そのときの落胆といったらありません。
そんなもやもやに悩まされていました。
ところが後になってCPUを新調し、グラフィック設定も調整した結果、250fpsを安定して超えるようになった瞬間、視界が嘘のようにクリアになったんです。
弾の当たり方が違う。
実際にそのとき私は思わず「これだ!」と声を出してしまいました。
40代になった今思えば、あのときの心境はちょっとした成功体験にも似ていました。
準備するだけでは成果は出なくて、条件を満たしたときに初めてモニターが真価を発揮するという当たり前の事実を思い知らされたのです。
多くの人が誤解しているのは「240Hzのモニターを買ったら240fps出せればいい」という考え方です。
確かに間違いではありませんが、本当に滑らかさを実感するには少し上乗せした260fpsや280fpsが安定して維持できることが望ましい。
数十fpsの差なんて大したことはないと思う人もいますが、Valorantのように一瞬の判断で勝敗が決まるゲームでは、この小さな差が大差に変わるものなんです。
ほんのわずかの違いが勝敗の差。
プレイしているとその意味が実感できます。
では実際にどこまでの構成を目指すのか。
フルHDであれば比較的現実的に240fpsを維持できますし、ミドルレンジのGPUとCPUの組み合わせでも十分に達成できるのが実情です。
そのうえで設定を調整すれば、しっかり240Hzの世界を感じられます。
でもWQHDになると条件は厳しくなりますね。
昔のように「240HzモニターといえばフルHD」という単純な話ではなくなってきました。
解像度と画質、そして勝敗。
悩ましさが増すわけです。
そうそう、最近友人が最新のRadeon搭載PCを購入して、WQHD・165Hzの環境で遊んでいたんですよ。
正直「中途半端じゃないの?」と思っていたのですが、実際触らせてもらうと驚きました。
160fps以上を安定して出していて、映像は滑らかで途切れがない。
これは競技用として十分だと心から納得しました。
昔なら諦めていた環境ですが、いまは違う。
ほんの数年でここまで進化したかと思うと、技術の進歩には感謝したくなります。
ただ一点、忘れてはいけないのは冷却と電源です。
どんなに良いパーツを積んでも、熱でパフォーマンスが落ちたり電源不足で不安定になれば台無し。
これは仕事にも通じるところがあって、成果だけを求めて基盤をおろそかにすると、いずれ組織も崩れるものです。
基礎が大事。
私にも苦い経験があります。
冷却を甘く見ていて、夏場に突然fpsが落ちて試合にならなかったんです。
そのときは「まあ仕方ない」と言い聞かせてプレイしましたが、終わったあとに不思議な疲労感を覚えました。
最終的に私が考える最適解は、フルHD環境なら240Hzモニターを導入し、常時250fps以上を出せる構成にすることです。
ミドルハイクラスのGPUと力のあるCPUの組み合わせなら十分可能です。
そしてWQHDであれば144Hzを基本にしつつ、余裕があれば165Hz以上を狙うのが現実的です。
そのうえで冷却と電源をしっかり整える。
これでようやく「勝てる環境」が完成するのだと思います。
最後に強調したいのは、スペックは数値で語られがちですが、本当に快適さを生み出すのは数値ではなく全体の調和です。
fps、リフレッシュレート、解像度、冷却、電源、そのすべてがちょうどよく噛み合ったときに初めて、「ああ、これならやれる」と心から思える環境が整うのです。
仕事や人生にも通じる話だとつい思ってしまうんです。